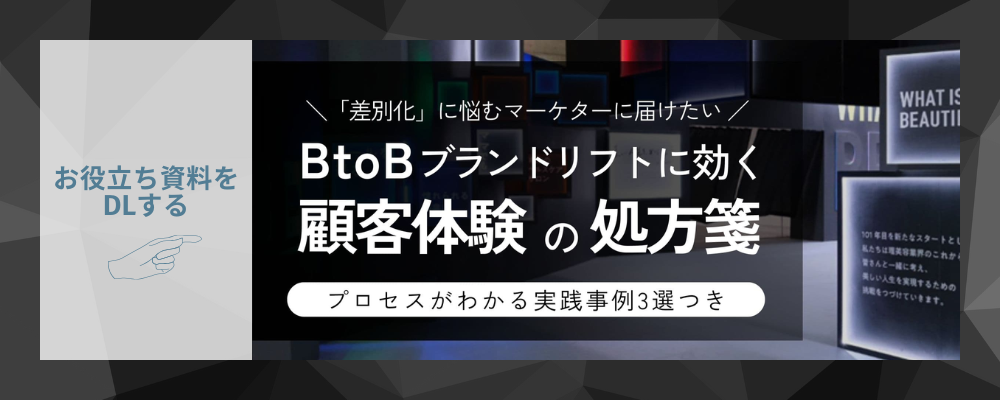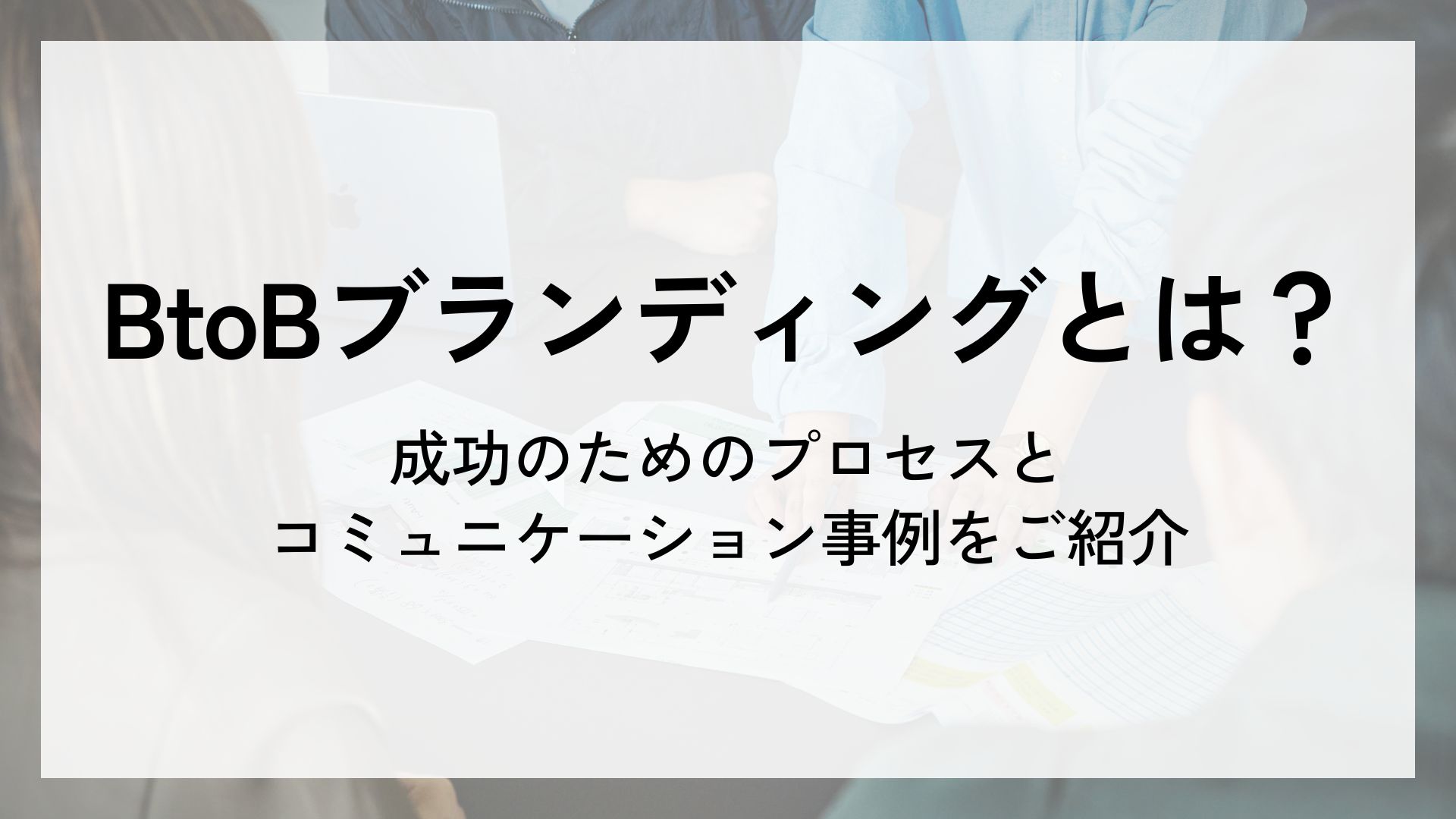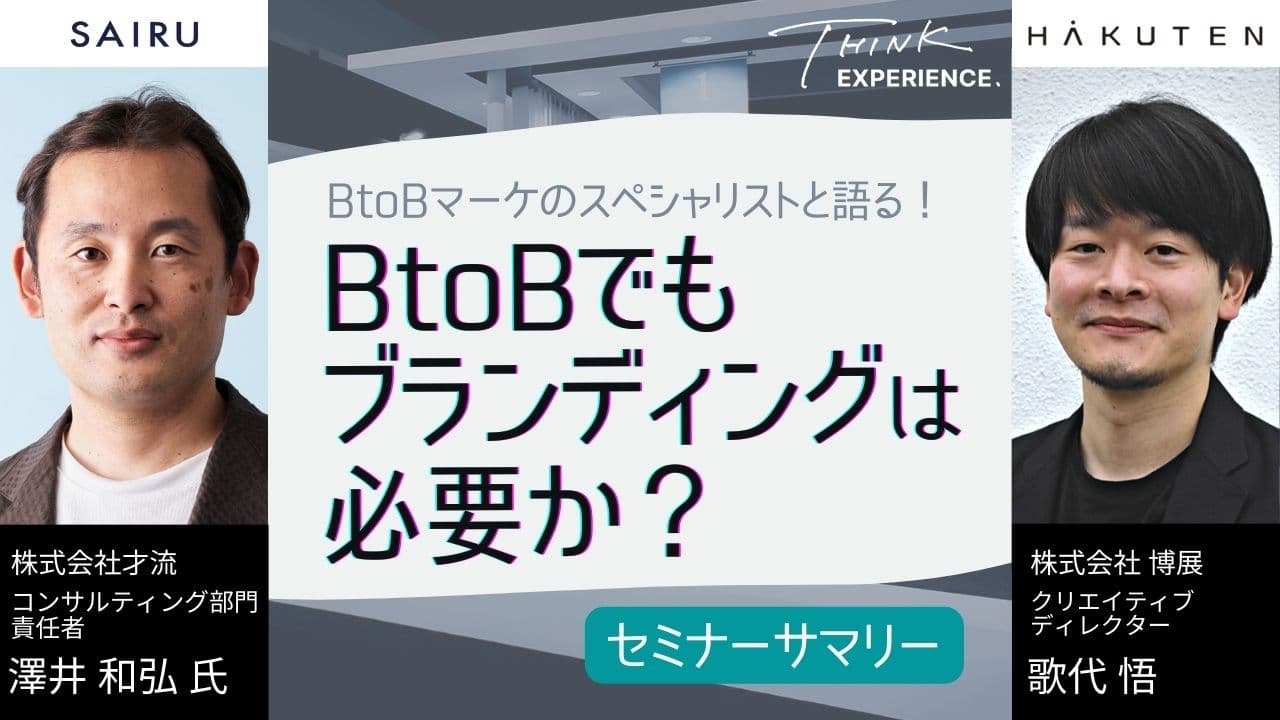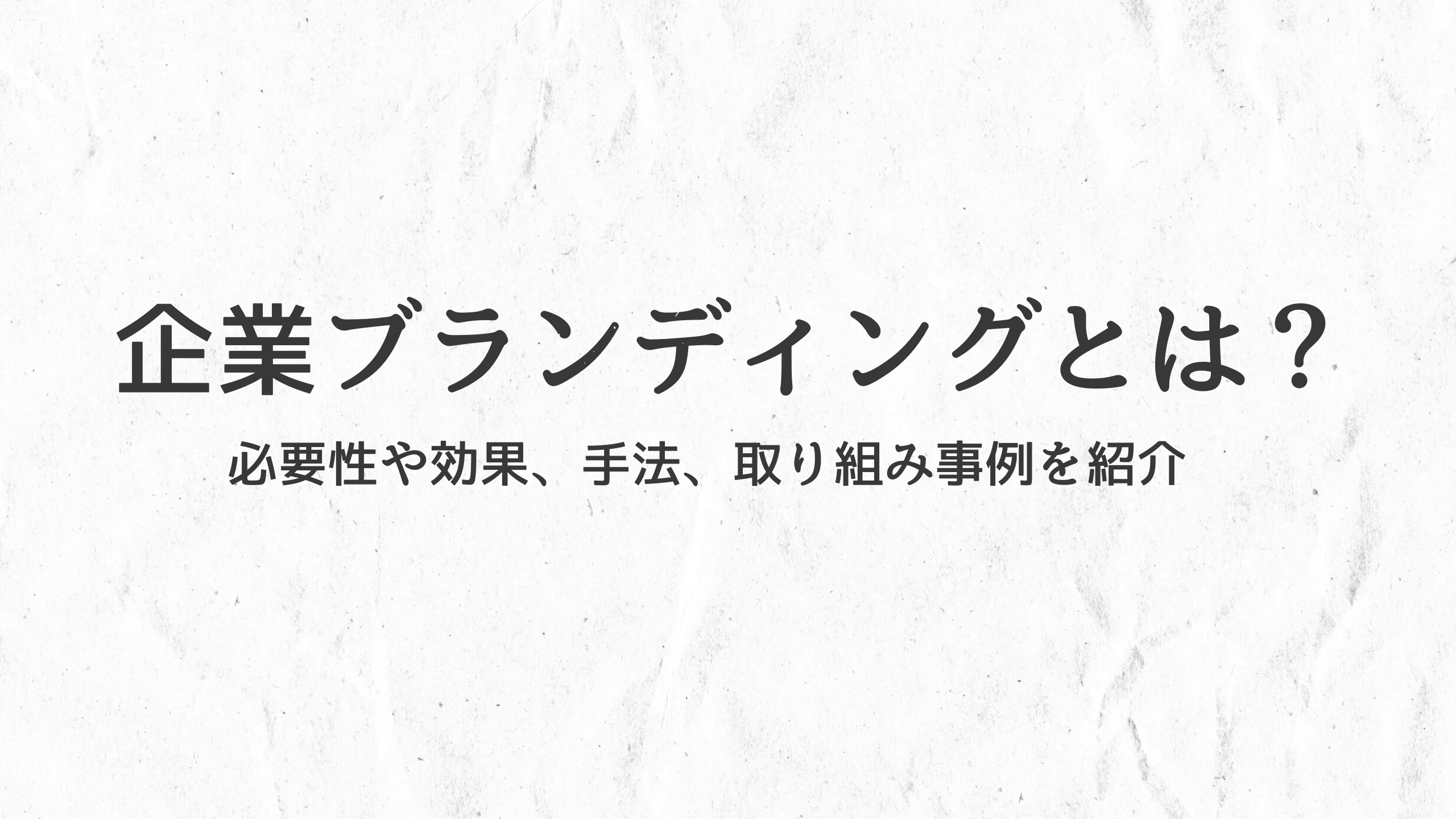展示会は新規顧客獲得の場として活用されることが多いですが、近年は「ブランディング」効果を狙い出展する企業も増えてきています。
本記事では、展示会におけるブランディングの重要性から具体的な施策、成功事例まで、マーケティング担当者が実践で活用できる情報を詳しく紹介します。
Index
■なぜブランディングに展示会が有効なのか
■商材特性を明確にアピールする戦略的アプローチ
■展示会で直感的な信頼感を醸成する環境づくり
■展示会におけるブランディングの成果・効果の測定
■事例1:株式会社ブリヂストン様
■事例2:ホシザキ株式会社様
■事例3:株式会社モリタ様
■まとめ
■なぜブランディングに展示会が有効なのか
特定の業界にブランドイメージを的確に浸透させることが可能
展示会ブランディングとは、展示会という場を活用して自社の価値観やメッセージを効果的に伝え、来場者の心に印象を残す活動全般を指します。従来の売上直結型の展示会運営とは異なり、中長期的な視点でブランド価値向上を目指すアプローチです。
現代のBtoB市場では、製品やサービスの機能的差別化が困難になっており、企業の信頼性や価値観に基づいた選択が重要視されています。このような背景から、展示会でのブランディングはマーケティングの枠に留まらず、企業戦略とも密接に関わる活動となっています。
顧客獲得を目的とする展示会との違い
従来の展示会運営が早急な顧客獲得に重点を置いていたのに対し、ブランディング重視の展示会では「将来の潜在顧客」との関係構築を優先します。これにより、短期的な成果は見えにくくても、長期的には強固な顧客基盤の構築が可能になります。
また、製品スペックの説明中心だった従来のアプローチから、企業の理念や価値観を体感できる体験型コンテンツへとシフトすることで、より深い印象を残すことができます。
BtoB市場におけるブランディングの価値
BtoB市場では購買決定プロセスが複雑で、複数の関係者が意思決定に関わります。そのため、機能的な優位性だけでなく、信頼できるパートナーとしての印象を与えることが重要です。
展示会でのブランディング成功により、営業活動における初回アポイントメント獲得率の向上や、提案時の競合優位性確保が期待できます。また、既存顧客との関係深化や、長期的な売上安定化にも貢献します。
■商材特性を明確にアピールする戦略的アプローチ
展示会場では来場者が短時間で多くのブースを回るため、一瞬で自社の特徴を理解してもらう必要があります。会社名の認知度が低い場合、単に社名を大きく掲げるだけでは効果は期待できません。重要なのは「何ができる企業なのか」を瞬時に伝えることです。
成功する企業は、商材の機能説明よりも「顧客の課題解決」にフォーカスしたメッセージング戦略を採用しています。これにより、来場者は自分事として商材を捉えやすくなり、ブースへの興味関心が高まります。
効果的なキャッチコピーの作成方法
優れたキャッチコピーは「誰の」「どんな課題を」「どのように解決するか」を簡潔に表現しています。例えば「製造業の品質管理を自動化」「小売店の在庫ロスを50%削減」など、具体的で定量的な表現が効果的です。
また、業界特有の専門用語を避け、決裁権者にも理解しやすい平易な言葉を選ぶことで、より幅広い来場者にメッセージが届きます。キャッチコピーの検証には、社内の異なる部署のメンバーに意味が通じるかテストすることが有効です。
複数商材を扱う場合の整理術
複数の商材を展示する場合、それぞれのターゲット層と訴求ポイントを明確に区分することが重要です。商材間の関連性や相乗効果を活用し、統一感のあるストーリーで全体を構成します。
成功企業の多くは、商材を「課題別」や「業界別」にゾーニングし、来場者が自分に関連する情報を効率的に収集できる導線設計を行っています。また、各商材の共通する価値観や企業理念を上位概念として設定し、ブランド統一性を保っています。
視覚的インパクトを高めるデザイン戦略
商材特性の可視化には、インフォグラフィックや体験型デモンストレーションが効果的です。複雑な技術や抽象的なサービスも、視覚的に理解しやすい形で表現することで、来場者の記憶に残りやすくなります。
カラーリングやフォント選択においても、ターゲット業界の慣習や好みを考慮し、親しみやすさと専門性のバランスを取ることが重要です。
■展示会で直感的な信頼感を醸成する環境づくり
人は短時間で物事を判断する際、論理的思考よりも直感に頼る傾向があります。展示会という限られた時間の中で信頼関係を構築するには、来場者の「第一印象」を重視した環境づくりが不可欠です。
信頼感を得るためには、客観的な信頼性の提示と、心理的な安心感の創出という2つのアプローチがあります。両方をバランスよく実装することで、来場者に「この企業なら安心して任せられそう」という印象を与えることができます。
客観的な信頼性の効果的な提示
受賞歴、導入実績、顧客からの評価などの第三者評価は、自社の主観的な説明よりも高い説得力を持ちます。これらの情報をブース内の目立つ位置に配置し、来場者が自然に目にする設計にすることが重要です。
特に具体的な数値や事例を示すことで、信頼性がより高まります。「導入企業数1,000社突破」「顧客満足度95%」といった定量的な実績や、有名企業のロゴ掲載許可を得ている場合は積極的に活用しましょう。
スタッフの立ち居振る舞い
来場者が最初に接触するのはブースの雰囲気とスタッフの印象であり、その振る舞いは企業が伝えたいブランドイメージを体現する重要な要素です。目指すブランドイメージによって、スタッフに求められる服装や立ち居振る舞いは大きく異なります。
例えば、若く勢いのあるブランドとして認知されたい場合は、スタッフはポロシャツなど少しラフな服装で、元気に明るく来場者に声をかけることで、親しみやすさと活気を演出できます。一方で、業界をリードする権威ある企業としての信頼感を示したい場合は、服装もややフォーマルに寄せ、専門知識に基づいた落ち着いた口調で接客することで、来場者に安心感と説得力を与えることができるでしょう。
■展示会におけるブランディングの成果・効果の測定
展示会ブランディングの成果を正確に把握し、継続的な改善を行うためには、適切な効果測定が不可欠です。従来の来場者数や名刺獲得数といった定量指標だけでなく、ブランド認知度や印象の変化など、定性的な指標も含めた総合的な評価が重要です。
効果測定の結果を次回の展示会企画に活かすことで、ブランディング効果の継続的な向上が期待できます。また、測定結果を社内で共有することで、展示会投資の意義を明確にし、継続的な予算確保にもつながります。
KPI設定と測定方法
ブランディング効果の測定には、認知度向上、印象改善、関係構築の3つの観点からKPIを設定することが効果的です。認知度向上については展示会前後のブランド認知度調査、印象改善については来場者アンケートによる印象評価、関係構築についてはフォローアップ率や商談化率で測定します。
| 測定観点 | KPI例 | 測定方法 |
|---|---|---|
| 認知度向上 | ブランド認知率の変化 | 展示会前後のアンケート調査 |
| 印象改善 | 企業印象スコア | 来場者アンケート5段階評価 |
| 関係構築 | 商談化率 | フォローアップ後の商談数÷来場者数 |
これらのKPIを継続的に測定することで、ブランディング施策の効果を定量的に把握し、改善点を明確にすることができます。
来場者フィードバックの活用
来場者からの直接的なフィードバックは、ブランディング効果を測る上で極めて価値の高い情報源です。アンケート調査だけでなく、SNSでの言及やメディア掲載内容なども含めて総合的に分析することが重要です。
特に、来場者が自発的にSNSで投稿した内容は、リアルな印象や感想を反映しており、ブランディング効果の客観的な評価指標として活用できます。ハッシュタグの設定や投稿キャンペーンの実施により、より多くのフィードバックを収集することも可能です。
継続的改善のためのPDCAサイクル
展示会ブランディングは一回の実施で完成するものではなく、継続的な改善が必要です。各回の展示会終了後に詳細な振り返りを行い、成功要因と改善点を明確にすることで、次回のさらなる効果向上が期待できます。
改善サイクルを回す際は、社内の関係部署とも連携し、営業部門からの商談状況フィードバックや、マーケティング部門からの市場反応分析なども含めて総合的に評価することが重要です。
■事例1:株式会社ブリヂストン様

株式会社ブリヂストン様は、2023年1月に開催された東京オートサロンにおいて、「Tomorrow Road」をテーマにしたブースを出展しました。博展は、コンセプト設計から空間デザイン、コンテンツ制作、施工に至るまでトータルでサポートし、来場者に対してブリヂストンブランドが描く「持続可能な“走るわくわく”」を体験できる空間を提供しました。
サステナビリティと走る喜びを融合させたコンセプト
ブリヂストン様は、モータースポーツ活動60周年を迎える節目の年に、サステナビリティをテーマにした出展を決定しました。博展は、サステナビリティと走る喜びを融合させた「Tomorrow Road」というコンセプトを提案し、これにより、来場者に対してブランドが目指す未来のモビリティと環境への配慮を感じさせる展示を実現しました。
モータースポーツファンの心をくすぐるブースデザイン
ブースデザインは、モータースポーツファンである博展のデザイナーのこだわりが詰まったものとなりました。タイヤのトレッドパターンやピットウォールなど、モータースポーツに関連する要素を取り入れ、来場者が写真を撮りたくなるような演出が施されました。さらに、タイヤを手で回すことで、映像と音が連動する体験型コンテンツも提供され、技術の高さを実感できる展示となりました。
このようなデザインや体験を通し、ブリヂストン様のブランドやサステナビリティへの取組みを来場者に深く印象付ける場となりました。
■事例2:ホシザキ株式会社様

ホシザキ株式会社様は、2023年に開催された展示会において、業務用厨房機器の革新とブランドの信頼性を体現するブースを出展しました。博展は、空間デザインからコンテンツ制作、施工に至るまで、ホシザキ様のブランドメッセージを来場者に伝えるためのトータルサポートを行いました。
業務用厨房機器の革新を体感できる展示
本ブースでは、ホシザキ様が誇る業務用厨房機器の最新技術や製品を展示し、来場者が実際にその機能や利便性を体験できるような設計が施されました。インタラクティブなデモンストレーションを通じて、製品の特長や使用シーンを直感的に理解できるよう工夫されていました。
ブランドの信頼性と安心感を伝える空間設計
ブース内の空間設計は、ホシザキ様のブランドイメージである「信頼性」と「安心感」を体現するようなデザインが採用されました。落ち着いた色調や素材の選定、照明の工夫など、細部にわたる演出が施され、来場者に対して企業の姿勢が明確に伝わるようになっていました。また、ブース内ではホシザキ様の持続可能な未来に向けた取り組みや、環境への配慮が紹介され、来場者に対して企業の社会的責任や未来志向の姿勢が伝わる設計を目指しました。
■事例3:株式会社モリタ様
株式会社モリタ様は、2023年に開催された「第9回 World Dental Show 2023」において、従来の目的であった販売促進やリード獲得、新商品発表とは異なるアプローチで出展しました。博展は、本出展において企画・デザイン・施工のトータルサポートを担当し、モリタ様の新たな挑戦を支援しました。
体験を軸にした企業ブランディングへの転換
これまでの展示会では出展製品の選定やブースデザインの形がある程度決まっていましたが、モリタ様は今回、「体験を軸にした企業ブランディングの場」へと目的を大きく変更しました。来場者に対し、「モリタがどのようなことをするのか」という期待感を持たせ、楽しんで来場してもらうことを目指したのです。
モリタの「見えないこだわり」を“魅せる”コンセプト
博展のプロジェクトメンバーは企業や製品への理解を深めるためにモリタ様の製作所を直接見学しました。その中で、モリタ様が製品を作る過程に多くの「こだわり」が存在するにもかかわらず、その多くが外部に伝えられていないことに気付きました。製作所の社員にとっては当たり前のことでも、使い手を一番に考えた工夫が数多くあることを発見したのです。この発見から、「見えないを魅せる」というコンセプトが生まれました。このコンセプトは、お客様に対してだけでなく、営業担当者などの社内の方々にも自社製品のこだわりを深く理解してもらうという、インナーブランディングの目的も兼ねていました。
■まとめ
展示会をブランディングに活用することで、単発的な営業活動を超えて、長期的な企業価値向上と信頼関係を構築することができます。商材の価値を的確に伝える論理的なアピールと、企業の姿勢で共感を呼ぶ感情的なアプローチを組み合わせることで、来場者の記憶に残る強い印象を与えることが可能です。
成功事例から学べるように、自社の特徴を明確に定義し、ターゲット層に響くストーリーやコンテンツを設計することで、競合他社との差別化を図ることができます。また、適切な効果測定と継続的な改善により、ブランディング効果を最大化し、投資対効果の向上も期待できます。
展示会ブランディングは即効性よりも継続性が重要な取り組みです。明確な戦略に基づいた活動により、自社ブランドの確立と市場での競争優位性確保を実現してください。