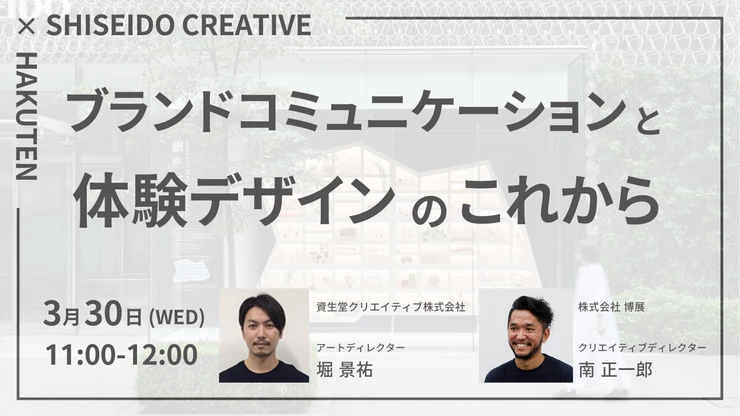企業のマーケティング活動において、顧客との直接的な接点を生み出すイベントプロモーションは非常に重要な手法です。商品やサービスの認知度向上から新規顧客獲得、既存顧客との関係強化まで、様々な効果が期待できる一方で、具体的な実施方法や成功のポイントが分からないという担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、イベントプロモーションの基本概念から実施手順、実際の成功事例まで体系的に解説し、自社での効果的な活用につながる実践的な情報をお届けします。
Index
■イベントプロモーションとは
■イベントプロモーションで期待される効果
■イベントプロモーションの主要手法
■イベントプロモーション実施の流れとポイント
■事例1:パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 CEATEC 2024
■事例2:野村不動産株式会社 あなたの未来のくらしと時間展(野村不動産住宅事業60周年イベント)
■事例3:ビー・エム・ダブリュー株式会社 FREUDE by BMW – THE GARDEN
■事例4:STATION Ai株式会社 STATION Ai 開業プロモーション
■事例5:韓国観光公社 韓国 Dramatic Night
■まとめ
■イベントプロモーションとは
イベントプロモーションとは、企業が主催または協賛するイベントを通じて、商品やサービス、ブランドの認知拡大や顧客との関係構築を図るマーケティング手法です。従来の広告や宣伝とは異なり、参加者との直接的なコミュニケーションを重視し、体験型のアプローチで訴求効果を高められるという特徴があります。
マーケティングミックスの4P(製品・価格・流通・プロモーション)において、イベントプロモーションはプロモーションの一要素として位置づけられます。しかし、単なる販売促進にとどまらず、商品体験の場(流通)や価値提案(製品)の側面も併せ持つ統合的なマーケティング活動といえるでしょう。
他のプロモーション手法との違い
イベントプロモーションの最大の特徴は、顧客との双方向コミュニケーションが可能な点です。テレビCMやWeb広告などの一方向的な情報発信とは異なり、参加者からのリアルタイムなフィードバックを得られ、その場で疑問解決や関係性構築が行えます。
また、五感に訴える体験型アプローチにより、商品やサービスの魅力をより深く伝えることが可能です。実際に触れる、試す、体感するという行動を通じて、参加者の記憶に強く残る印象を与えられるのも大きな違いといえるでしょう。
マーケティング戦略における役割
現代のマーケティング戦略において、イベントプロモーションは顧客との長期的な関係構築を担う重要な役割を果たします。単発的な売上向上だけでなく、ブランドロイヤルティの向上や口コミ効果の創出など、持続的な価値創造につながる効果が期待できます。
特にBtoBマーケティングにおいては、商談機会の創出や既存顧客との関係深化において重要な位置を占めています。展示会やセミナーを通じた見込み客の発掘、既存顧客向けユーザー会での満足度向上など、営業活動と密接に連携した戦略的活用が可能です。
■イベントプロモーションで期待される効果
イベントプロモーションの実施により、企業は多面的な効果を期待できます。これらの効果は短期的なものから中長期的なものまで幅広く、マーケティング目標に応じて重点を置く効果を明確にすることが重要です。
効果測定においては、定量的な指標と定性的な指標の両面から評価することで、投資対効果を適切に判断できるでしょう。まずは主要な効果について詳しく見ていきましょう。
認知度向上とブランドイメージの定着
イベントプロモーションは、ターゲット層への直接的なリーチにより、効率的に認知度を向上させることができます。特に新商品発表会や業界展示会への出展は、短期間で多くの見込み客に自社の存在を印象づける絶好の機会となります。
また、イベントのテーマや演出を通じて、企業が目指すブランドイメージを具体的に表現できるのも大きな特徴です。参加者の五感に訴える体験型アプローチにより、単なる社名認知を超えた深いブランド理解を促進できるでしょう。
新規顧客獲得とアポ創出
イベント参加者との直接対話により、従来のマーケティング手法では接触困難な潜在顧客を発掘できます。特にBtoBマーケティングでは、決裁権者や影響力のあるキーパーソンとの直接対話機会が貴重な営業資産となります。
名刺交換や個別相談の実施により、質の高いリード獲得が可能になり、後続の営業活動につながる具体的な商談機会を創出できます。展示会では年間の営業目標の30%以上をイベント経由で達成する企業も珍しくありません。
既存顧客との関係強化
既存顧客向けのユーザー会や感謝イベントの開催により、顧客満足度向上と継続取引の促進が期待できます。顧客同士の交流機会を提供することで、コミュニティ形成によるロイヤルティ向上効果も得られます。
また、新機能紹介や活用事例共有を通じて、アップセルやクロスセルの機会創出にもつながります。継続的な関係構築により、競合他社への流出防止と長期的な売上安定化を実現できるでしょう。
■イベントプロモーションの主要手法
イベントプロモーションには多様な手法があり、目的や予算、ターゲット層に応じて最適な形式を選択することが重要です。近年はデジタル技術の発展により、オンライン形式やハイブリッド形式の選択肢も拡大しています。
それぞれの手法には固有のメリットとデメリットがあるため、自社の状況と目標を踏まえた戦略的な選択が求められます。以下、代表的な手法について詳しく解説していきます。
展示会・見本市への出展
展示会や見本市への出展は、短期間で大量の見込み客と接触できる最も効率的なイベントプロモーション手法の一つです。業界関係者が一堂に会するため、ターゲット層への集中的なアプローチが可能になります。
出展においては、ブース設計から来場者との対話内容まで、綿密な準備が成功の鍵となります。競合他社も多数出展する環境下で差別化を図るため、独自性のある展示内容や体験型コンテンツの企画が重要でしょう。
セミナー・ウェビナー開催
専門的な知識やノウハウを提供するセミナーやウェビナーは、見込み客の課題解決に貢献しながら自社の専門性をアピールできる手法です。教育的価値を提供することで、参加者との信頼関係構築と専門企業としてのポジショニング確立が同時に実現できます。
オンライン形式のウェビナーは、地理的制約を超えて多くの参加者を集められるメリットがあります。録画配信との組み合わせにより、イベント終了後も継続的な集客効果を期待できるでしょう。
体験型イベント・デモンストレーション
商品やサービスの実際の使用感を体験してもらう体験型イベントは、購買意欲の向上に直結する効果的な手法です。特に機能性や操作性が重要な商品においては、実際の体験を通じて得られる納得感が購買決定の重要な要因となるでしょう。
デモンストレーションでは、単なる機能紹介にとどまらず、参加者の具体的な利用シーンを想定した実践的な体験機会を提供することが重要です。専門スタッフによる個別対応により、参加者一人ひとりのニーズに合わせたカスタマイズ提案も可能になります。
オンライン・ハイブリッド形式の活用
新型コロナウイルスの影響を受けて急速に普及したオンライン形式は、現在では選択肢として一般的に定着しています。参加者の移動コスト削減と企業の会場費削減の両面でメリットがあり、従来以上に多くの参加者を集められる可能性があります。
ハイブリッド形式では、リアル参加者とオンライン参加者の双方に価値を提供する工夫が必要です。インタラクティブな要素を盛り込むことで、オンライン参加者の満足度向上と継続的な関係構築を実現できるでしょう。
■イベントプロモーション実施の流れとポイント
効果的なイベントプロモーションの実施には、企画立案から事後フォローまでの一連のプロセスを体系的に管理することが不可欠です。各段階でのポイントを押さえることで、投資対効果の最大化と継続的な改善につながります。
特に準備段階での綿密な計画立案が、当日の成功と期待される効果の実現を左右します。以下、実施フローに沿って重要なポイントを詳しく解説していきましょう。
企画立案と目標設定
イベントプロモーションの成功は、明確な目標設定と測定可能な指標の確立から始まります。認知度向上、リード獲得、売上拡大など、具体的な目標を数値化することで、企画内容の方向性と成果評価の基準が明確になります。
目標設定においては、短期的な効果と中長期的な効果を分けて考えることが重要です。イベント当日の参加者数や名刺交換数などの直接的指標に加え、その後の商談化率や顧客満足度向上などの間接的効果も含めた包括的な評価軸を設定しましょう。
ターゲット設定と集客戦略
効果的な集客のためには、参加してほしいターゲット層を明確に定義し、彼らに響くメッセージと適切なチャネルでの告知が必要です。既存顧客データベースの活用に加え、業界メディアやSNS、パートナー企業との連携など、多角的なアプローチにより認知拡大を図ります。
集客においては、参加者にとっての価値提案を明確にすることが重要です。単なる商品紹介ではなく、参加することで得られる具体的なメリットや学び、体験価値を前面に打ち出した訴求により、質の高い参加者の確保を目指しましょう。
当日運営と顧客対応
イベント当日の運営では、参加者一人ひとりに対する丁寧な対応が、その後の関係構築の基盤となります。受付から会場案内、個別相談まで、すべての接点で一貫したブランド体験を提供することで、参加者の満足度と企業への信頼度を向上させることができます。
スタッフの役割分担と対応マニュアルの整備により、統一された品質での顧客対応を確保することが重要です。また、参加者の関心度合いに応じた適切なフォローアップ計画を事前に準備しておくことで、機会損失を最小限に抑えられるでしょう。
効果測定と改善活動
イベント終了後の効果測定は、投資対効果の検証と次回イベントの改善につながる重要なプロセスです。参加者アンケートによる満足度調査に加え、名刺交換後の商談化率や売上貢献度など、ビジネス成果に直結する指標での評価が不可欠です。
測定結果をもとにした改善活動により、継続的なイベントプロモーションの品質向上を実現できます。成功要因と課題要因の分析を通じて、次回企画に活かせる具体的な改善策を導き出すことが重要でしょう。
■事例1:パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 CEATEC 2024
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社は、AIやIoT、技術ロボットなどの先端技術を発表する展示会「CEATEC2024」に出展され、株式会社博展はそのブース企画設計から施工までトータルプロデュースを担当しました。
イベント概要
パナソニックグループが独自性としているAIは、「人によって創られ人に寄り添う有機的な存在であること」を体現すべく、博展はクリエイティブコンセプト「FUSION TO ACT」を策定しました。これは、技術や思考、新たな価値といった「幸せのチカラ」が理想の社会を創るアクションへ繋がり、人とテクノロジーの多様な「融合」により体験価値を創造し、「物と心がともに豊かな理想の社会実現」へ繋がるよう体験設計されたものです。
展示の中心はPanasonic×AI開発事業で、「人間のための、人間による、人間に寄り添うAI開発」が行われているというResponsible AIとScalable AIの2つの考え方が表現されました。ブースでは、AIに持たれがちな『無機的な印象』ではなく、『有機的な存在』であることを照明と風によって表現しました。
上部造作には微かに揺れ動くファブリック、壁面のグラフィックにはAI開発に携わる従業員を掲出し、それぞれから創出されるシナプスをグラフィック全体に行き渡らせることで、人によって創られているAIであることを強調しました。
また、中央のステージではCEATEC2023で好評だった従業員によるトークセッションを実施し、本年は協業パートナーなどのステークホルダーもゲスト出演し、より多くの関心を集めるステージを提供しました。
効果に繋がった取り組み
Panasonic GREEN IMPACTの取り組みに関連するサステナビリティ展示では、同社が有する有機的な素材が実装されました。“木材に代わる新しい材料”として森林破壊に歯止めをかける効果も期待されている「PALM LOOPボード」と、高濃度セルロースファイバー成形材料であるkinariで成形したジョイントを用いて、環境配慮型の什器を製作しました。これは、今後サステナブルな展示会を実現するために、他の展示会等で再利用できる展示什器の設計・製作を目指したものです。
ブース全体で、「人によって創られ人に寄りそう有機的な存在であるPanasonic×AI」を体現することで、独自性のあるプロモーションを形成し、認知度向上に繋がる機会を創出することができました。
■事例2:野村不動産株式会社 あなたの未来のくらしと時間展(野村不動産住宅事業60周年イベント)
野村不動産株式会社は、マンション事業60周年・プラウド20周年の節目としてオーナー様を対象とした感謝祭「あなたの未来のくらしと時間展」を主催されました。博展は、このイベントにおいて空間全体のアートディレクション・環境デザインに加え、動く家具などのエンジニアリングを含めた実施制作を担当しました。
イベント概要
この感謝祭は、お客様へのこれまでの感謝を込め、野村不動産が思い描く「あなたの明るく豊かな未来の時間」を体感してもらうことを目指して企画されました。
イベントでは、『野村不動産と日本の60年史』をプロジェクションマッピングを活用して展示したヒストリーエリアや、近未来の「会」「楽」「学」「食」「休」をテーマにした『未来のくらし体験エリア』が展開されました。その他にも、サステナブルな体験やトークショーなど、多種多様なコンテンツが企画されました。
効果に繋がった取り組み
博展が空間全体のアートディレクションや環境デザイン、そして動く家具などのエンジニアリングを含む実施制作を担当したことで、ご来場いただいた多くのお客様に楽しんでいただけるイベントとなりました。
■事例3:ビー・エム・ダブリュー株式会社 ポップアップ・エキシビション FREUDE by BMW – THE GARDEN
ビー・エム・ダブリュー株式会社は、2023年7月14日(金)から9月17日(日)にかけて、東京・表参道にて期間限定ポップアップ「FREUDE by BMW – THE GARDEN」を開催しました。博展は、本イベントの企画・デザイン・施工・運営をトータルで担当しました。
イベント概要
このポップアップイベントのテーマは、表参道の都会の喧騒から離れて、訪れる人々を心地よいくつろぎへと誘う「日本とドイツ・バイエルン地方の融合を成したBMWガーデン」でした。
会場内には、BMWの故郷であるドイツ・バイエルン地方の伝統的なカルチャーをフードとドリンクメニューに組み込んだ屋外カフェ&バーを展開しました。また、会場内のショップでは、車両テーマに絡めたHighsnobiety(ハイスノバイエティ)とBMWの限定コラボレーション・アイテムや、ポップアップ・エキシビションでのみ購入できるBMWライフスタイル・コレクションが販売されました。
効果に繋がった取り組み
イベント期間を通して様々なブランド・パートナーとのコラボレーションを実施することで、BMWが表現する多様な世界観をライフスタイルの観点から楽しめる空間が提供されました。
■事例4:STATION Ai株式会社 STATION Ai 開業プロモーション
STATION Ai株式会社は、2024年10月に名古屋・鶴舞に新たに開業したオープンイノベーション拠点「STATION Ai」の開業プロモーションを実施されました。博展は、このプロモーションを戦略段階から一貫してサポートし、1年間にわたりマーケティングとブランディングの両軸で伴走しました。
イベント概要
開業成功に向けた年間プロモーション戦略の立案からブランディング基盤の構築まで、キービジュアル開発を含む広範囲な施策設計を担当しました。
広告・PR・イベント施策として、名古屋駅コンコース100面サイネージやナナちゃんストリートジャックなど、大規模な広告展開を通じて認知拡大を図りました。これには名古屋市営地下鉄鶴舞線の額面広告も含まれます。また、名古屋駅コンコース内では入居スタートアップ企業の技術体験イベントも実施されました。
効果に繋がった取り組み
名古屋地域との連携を深める取り組みとして、名古屋駅でのイベントでは、名古屋市西区の菓子メーカーであるカクダイ製菓株式会社とのコラボレーションが実現しました。「クッピーラムネ」のキャラクターを使用したオリジナルノベルティが制作され、スタンプラリーの景品として配布されました。
■事例5:韓国観光公社 韓国 Dramatic Night
韓国観光公社は、韓国への観光促進のためのBtoCイベント「韓国 Dramatic Night」をベルサール高田馬場で開催されました。博展は、このイベントの企画、デザイン、施工、運営進行をサポートしました。
イベント概要
本イベントでは、韓国ドラマのOSTで有名なアーティストや、話題の若手の韓国人俳優などを日本へ招き、コンサートやトークショーを通じて韓国の魅力を伝えました。ステージコンテンツに加え、より韓国に行きたいという機運を醸成するため、限られたホワイエのスペースを工夫しました。
会場では、現地の様子を模した韓屋カフェ、韓国ドラマ展示、韓国地方都市の展示ブースなど、来場者が楽しめる多種多様なコンテンツが用意されました。イベントの最後には、「韓国旅券が当たる大抽選会」も実施されました。
効果に繋がった取り組み
ステージ装飾だけでなく、入口からホールに続くホワイエに大きな韓国の家を模した壁面を立てるなど、来場動線から雰囲気づくりを実施したことが施策のポイントとなりました。
その結果、会場装飾や各種コンテンツが来場者に好評を博し、イベント後のSNSで多くの反響を呼びました。集客も好調で、定員1,500人の抽選制のところ、10,000人以上の応募があるなど、イベントは大成功を収めました。
■まとめ
イベントプロモーションは、顧客との直接的なコミュニケーションを通じて、認知拡大から関係構築、売上向上まで多面的な効果をもたらす重要なマーケティング手法です。成功のためには、明確な目標設定と体系的な実施プロセス、継続的な改善活動が不可欠となります。
展示会やセミナー、体験型イベントなど多様な手法の中から、自社の目的とターゲットに最適な形式を選択し、参加者にとっての価値提供を重視した企画設計を行うことが重要です。今回紹介した事例や実践ポイントを参考に、自社の状況に適したイベントプロモーション戦略を立案し、継続的な改善を通じて確実な成果創出を目指していただければと思います。
博展では、これまで数多くの企業イベントをサポートしてきた実績と知見を活かし、イベントプロモーションの成功をお手伝いしております。イベント実施を検討されている方、より効果的な手法をお探しの方は、お気軽にご相談ください。