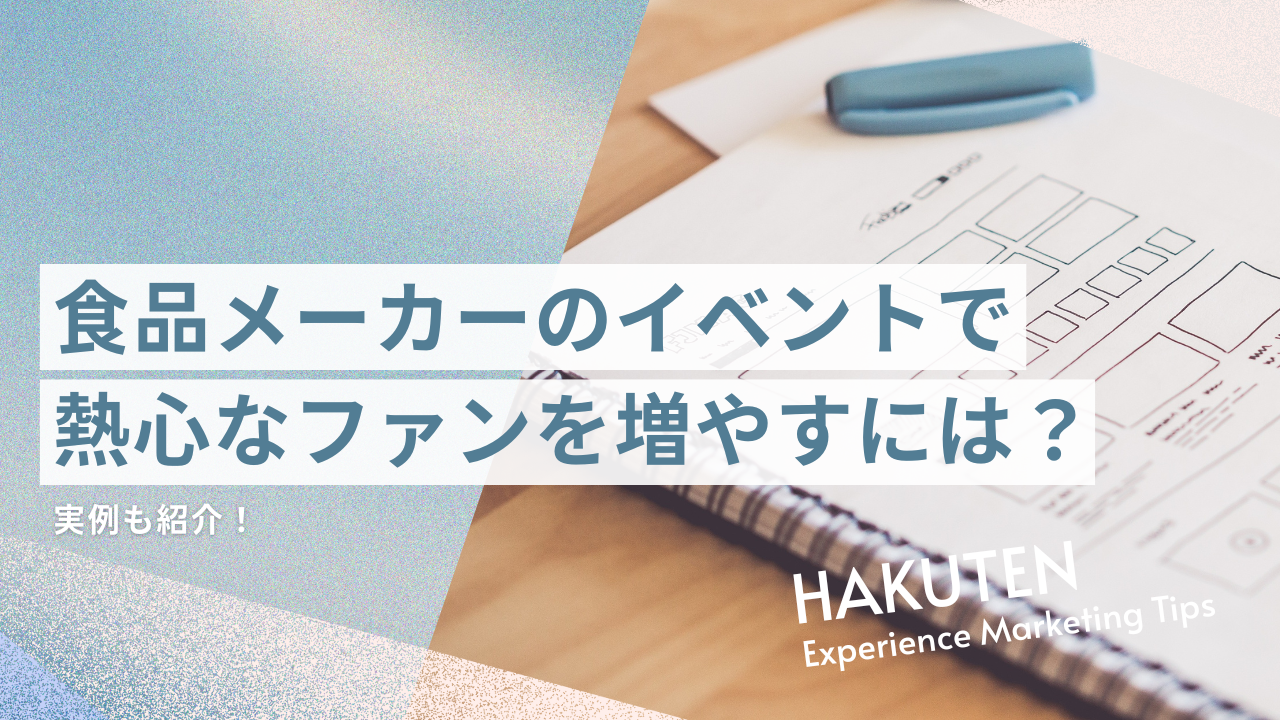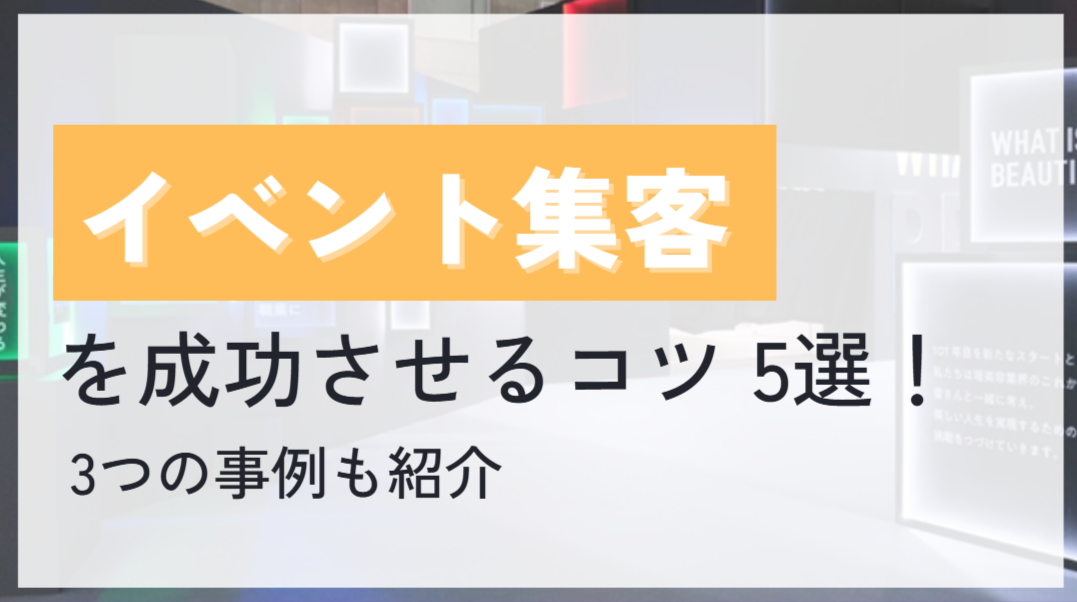食品メーカーにとって、商品を単に販売するだけでなく、企業やブランドのファンを獲得することは長期的な成長に欠かせません。
SNSやデジタルマーケティングが主流となった現在でも、試食体験による五感への訴求、従業員との直接的なコミュニケーション、参加者同士の交流など、デジタルでは得られない価値を提供できることから、リアルイベントには顧客との深い関係性を築く独特の力があります。
本記事では、カルビーをはじめとする食品メーカーの成功事例を詳しく分析し、ファン化につながるイベント企画の具体的な手法やポイントを解説します。明日から実践できるノウハウまで含めて、体系的にお伝えしていきます。
Index
■食品メーカーがイベントでファン化を成功させるメカニズム
■食品メーカーのファン化イベントの実例
■イベントを通じたファン育成のためのフォローアップ
■ファン化を目的とするイベントの効果測定
■事例1:カルビー株式会社様 「じゃがりこの日」
■事例2:日本フェレロ株式会社様 「Nutella Morning Slot 〜おはようヌテラで楽しい朝食〜」
■まとめ
■食品メーカーがイベントでファン化を成功させるメカニズム
食品メーカーのイベントがなぜファン化につながるのか、その背景にあるメカニズムを理解することが成功への第一歩です。
ブランドストーリーの共感とエモーショナルな結びつき
イベントでは商品だけでなく、企業の理念や開発ストーリー、従業員の想いなども伝えることができます。参加者がブランドの背景にある物語に共感することで、単なる顧客から「応援したい」という気持ちを持つファンへと変化していきます。
例えば、創業者の想いや商品開発エピソード、地域への貢献活動など、企業の人間性を感じられる要素を盛り込むことで、参加者との感情的な距離を縮められます。このエモーショナルな結びつきこそが、競合他社との違いを生み出す要因となります。
コミュニティ形成による継続的な関係性構築
成功するイベントは単発で終わらず、参加者同士や企業との継続的な関係性を生み出します。SNSでの情報共有や次回イベントへの参加など、コミュニティとしての結束が強まることで、個々の参加者がブランドアンバサダーとしての役割を果たすようになります。
このコミュニティ効果を最大化するためには、自然発生に任せるのではなく、企画段階で参加者同士の交流を意図的に促す「仕掛け」が不可欠です。具体的には、グループワークや共同作業の時間を設けたり、食事やお茶の時間を通じてリラックスした雰囲気で会話できる機会を作ったりすることで、参加者同士の関係性構築をサポートできます。これにより、イベント終了後もSNSなどで情報交換を続ける関係性が生まれ、ブランドに対する愛着がさらに深まっていきます。
このコミュニティ効果により、一人のファンが家族や友人にブランドを推薦する口コミ効果も期待できるため、費用対効果の高いマーケティング施策となります。
■食品メーカーのファン化イベントの実例
実際の食品メーカーの事例を詳しく分析することで、自社でも応用可能な具体的な手法を学べます。特に継続的にファンを増やし続けている企業の取り組みには、共通する成功パターンが存在します。
カルビー株式会社様「Fan With! Project」の双方向コミュニケーション戦略
カルビー株式会社様が展開する「Fan With! Project」は、ファンとの双方向コミュニケーションを重視した代表的な成功事例です。単なる商品PRではなく、ファンの声を商品開発に活かす仕組みを構築することで、参加者の当事者意識を高めています。
具体的には、新商品の開発段階からファンの意見を取り入れるワークショップを開催し、実際に商品化された際には協力者として名前を紹介するなどの施策を実施しています。この手法により、参加者は「自分も商品づくりに関わった」という特別感を持ち、強いブランドロイヤルティを形成しています。
さらに、イベント後もSNSでの情報発信や次回企画への優先案内など、継続的な関係性維持にも力を入れており、一度のイベント参加で終わらない長期的なファン化を実現しています。
地域密着型工場見学イベントの展開パターン
多くの食品メーカーが実施している工場見学イベントも、適切な企画設計により高いファン化効果を実現できます。単なる製造工程の紹介に留まらず、地域との結びつきや従業員の想いを伝える工夫が重要です。
成功している工場見学イベントでは、地元食材の活用ストーリーや工場で働く人々の日常を紹介することで、参加者に「この地域、この会社を応援したい」という気持ちを抱かせています。また、見学後の試食会では通常販売していない限定商品を提供したり、参加者限定の特典を用意したりすることで、特別感を演出しています。
SNSキャンペーンと連動したリアルイベントの相乗効果
デジタルとリアルを組み合わせたハイブリッド型のイベント企画も、現在のトレンドとして注目されています。SNSでの事前キャンペーンでイベント参加者を募集し、当日の体験をSNSで共有してもらう仕組みを構築することで、イベントの影響力を大幅に拡大できます。
例えば、Instagram用のフォトスポットを会場に設置し、専用ハッシュタグでの投稿を促すことで、参加していない人にもイベントの魅力を訴求できます。この手法により、イベント参加者数の数倍から数十倍のリーチを獲得し、潜在顧客への認知拡大も同時に実現しています。
■イベントを通じたファン育成のためのフォローアップ
イベント当日の成功だけでなく、その後の継続的なフォローアップがファン化の成否を左右します。一度築いた関係性を維持・発展させるための仕組み作りが、長期的なブランドロイヤルティの向上につながります。
イベント後の関係性維持のための接点創出
イベント終了後も参加者との接点を継続的に持つことで、一時的な盛り上がりを持続的な関係性へと発展させられます。メールマガジンやSNSでの情報発信、次回イベントの優先案内、限定商品の先行販売など、参加者だけが受けられる特別な価値を定期的に提供することが重要です。
また、イベントで撮影した写真の共有や、参加者の感想を紹介するコンテンツの配信なども、思い出を振り返る機会として効果的です。このような継続的なコミュニケーションにより、ブランドとの関係性を日常生活の一部として定着させることができます。
参加者からのフィードバック活用
イベント参加者からの感想や要望を積極的に収集し、次回の企画改善に活かすサイクルを構築することで、参加者の満足度を継続的に向上させられます。アンケート調査だけでなく、座談会形式でのヒアリングや、SNSでの自然な発言の分析なども有効な情報収集手段です。
特に参加者の提案を実際に次回イベントに反映し、その旨を告知することで、「自分の意見が聞き入れられた」という特別感を演出でき、より強いつながりを獲得できます。
アンバサダー制度による自発的な口コミ促進
継続的に参加している熱心なファンを公式アンバサダーとして認定し、口コミ活動を支援する制度も効果的です。アンバサダーには新商品の先行体験や特別イベントへの招待などの特典を提供する代わりに、SNSでの情報発信や友人への紹介などを依頼します。
この手法により、企業からの一方的な情報発信ではなく、実際の顧客からの信頼性の高い推薦として情報が拡散されるため、新規顧客獲得の効率も大幅に向上します。また、アンバサダー自身にとっても特別なステータスとして誇りを持てるため、さらなるファン化促進にもつながります。
■ファン化を目的とするイベントの効果測定
ファン化を目的とするイベントの成果を客観的に評価し、継続的な改善を図るためには、適切なKPI設定と効果測定が不可欠です。短期的な成果だけでなく、長期的なブランドロイヤルティの向上も含めて多角的に評価する必要があります。
ファン化の進度を測るための指標設計
ファン化の成果を測定するためには、参加者の行動変化や意識変化を定量的に把握できる指標を設定することが重要です。イベント前後での商品購入頻度の変化、SNSでのブランド関連投稿数、友人への推薦行動の有無などが代表的な指標となります。
また、NPS(Net Promoter Score)を活用してブランドへの推薦意向を数値化したり、ブランドへの愛着度を5段階評価で測定したりすることで、ファン化の深度を客観的に評価できます。これらの指標を継続的に追跡することで、施策の効果を定量的に把握し、改善点を明確に特定できます。
ROI算出のための総合的な効果測定手法
イベントの投資対効果を正確に算出するためには、直接的な売上効果だけでなく、ブランド価値向上や口コミ効果なども含めた総合的な評価が必要です。参加者の生涯顧客価値(LTV)の向上や、口コミによる新規顧客獲得コストの削減効果なども考慮に入れる必要があります。
特に食品メーカーの場合、ファン化により実現される継続購入や単価向上の効果は長期間にわたって持続するため、短期的なROIだけでなく中長期的な視点での評価が重要になります。
■イベント事例1:カルビー株式会社様 「じゃがりこの日」
カルビー株式会社様の主力商品である「じゃがりこ」の発売日(10月23日)を記念したプロモーションイベント「じゃがりこの日」は、商品理解の深化とブランドの再発見を目的に企画された体験型POP UPイベントです。ミュージアムをテーマに据えた空間演出と、参加者一人ひとりに合わせたデジタル体験の設計を通じて、ブランドの魅力を最大化するプロモーションを支援しました。
ブランドの世界観を体感できる体験型空間
本イベントでは、「じゃがりこ」の親しみやすさと奥深い魅力を伝えるため、ミュージアムのような展示を構築しました。試食体験などのリアルな体験を通じて、商品の魅力をより鮮明に伝えることのできる空間づくりを実現しました。
デジタルコンテンツによる新体験
単なる商品展示にとどまらず、デジタルコンテンツ「パーソナルじゃがりこ診断」を導入し、来場者が自分にぴったりの商品を発見できる仕掛けを用意しました。明確なテーマ性とインタラクティブ性を両立させた設計が、多くの来場者の記憶に残るイベント体験を生み出しました。
■イベント事例2:日本フェレロ株式会社様 「Nutella Morning Slot 〜おはようヌテラで楽しい朝食〜」
日本フェレロ株式会社様のプロモーションイベント「Nutella Morning Slot」は、朝食の楽しさとヌテラの多彩な楽しみ方を提案することを目的に、巨大スロットマシンを核とした五感体験型イベントとして企画しました。博展は、空間体験の設計に加え、PR施策やSNSキャンペーン、広告出稿までを一貫して支援しました。
五感に響く体験設計でブランドの世界観を訴求
イベントの中心には、回すごとに異なる朝食メニューが現れる「巨大朝食スロットマシン」を設置し、来場者が楽しみながらヌテラの魅力に触れられる仕掛けにより、製品の新たな楽しみ方を体感できる空間を創出しました。単なる展示にとどまらず、身体的・感覚的な没入体験を通じて、ブランドの世界観を直感的に伝える演出を展開しました。
企画立案の総合支援
本プロジェクトでは、イベント単体に留まらず、TVCM、媒体タイアップ、SNS広告、キャンペーンなど多様なチャネルを活用した一貫したプロモーション戦略を展開しました。これにより、高い話題性とSNSでの拡散力を獲得し、フォロワー増加といった成果にもつながりました。
■まとめ
食品メーカーのイベントを通じたファン化は、参加者の心を動かし、エモーショナルな結びつきを創出することがカギとなります。カルビーのプロジェクトに代表されるように、双方向コミュニケーションと継続的な関係性構築を重視した取り組みが、真の意味でのファン化を実現します。
成功するためには、参加者の感情に訴える体験設計と段階的なエンゲージメント向上の仕組み作り、そしてイベント後の継続的なフォローアップが不可欠です。また、適切なKPI設定による効果測定と継続的な改善サイクルの構築により、投資対効果を大きくしていくことが可能です。
ここまでご紹介した手法や事例を参考に、自社の商品特性や顧客層に合わせたオリジナルのファン化イベントを企画し、長期的なブランドロイヤルティの向上を目指しましょう。一度きりのイベントでファンとの関係性を終わらせることなく、継続的な関係性構築を通じて、真に愛されるブランドを築いていきましょう。