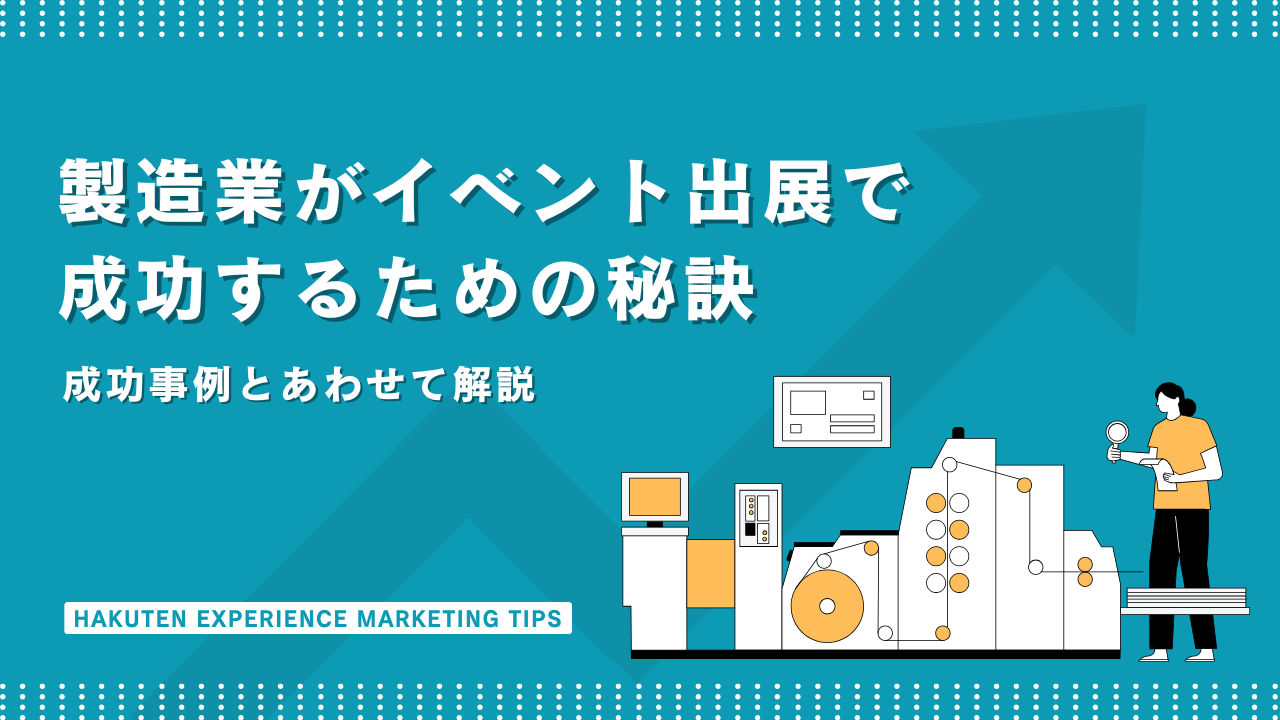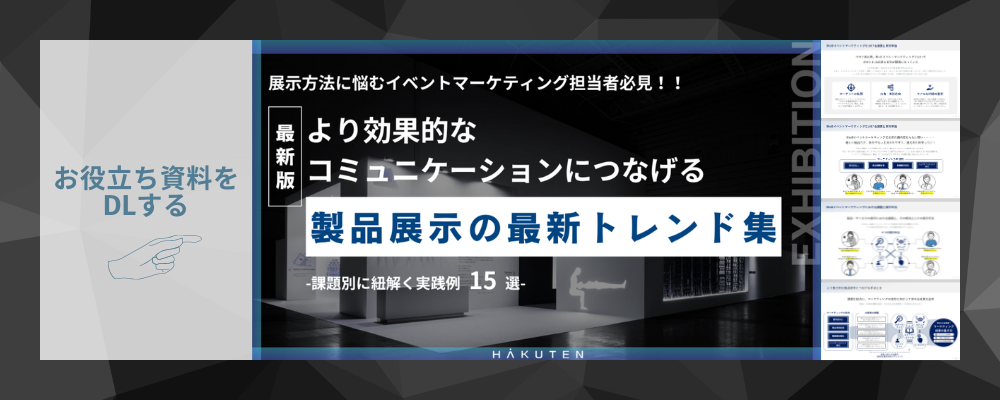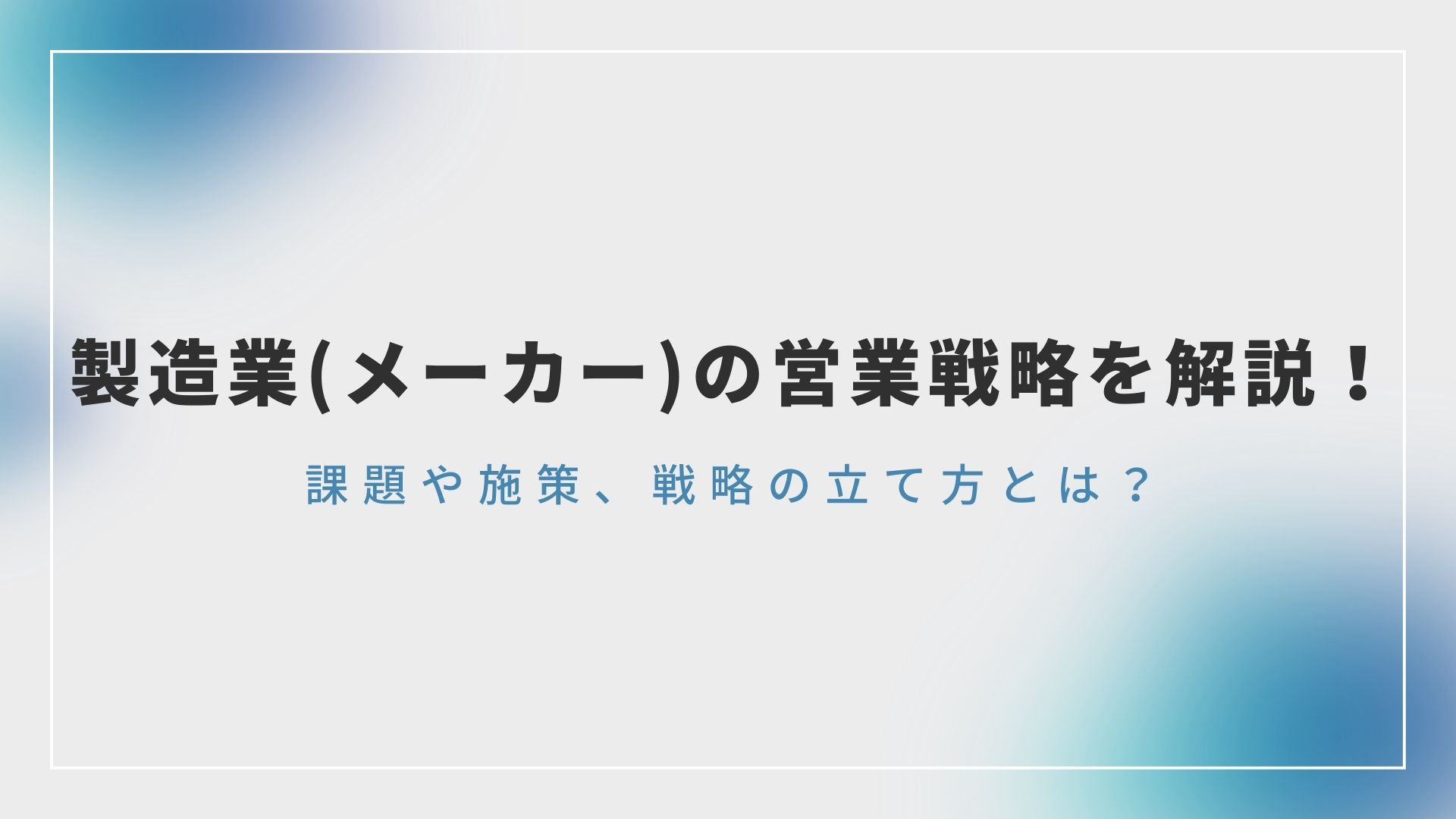製造業にとって、自社製品の「実物」を見せられる展示会やイベント出展は、新規顧客との貴重な接点を生み出す重要なマーケティング活動です。
しかし、出展さえすればよいというものではなく、「費用をかけて出展したものの、期待していた成果が得られなかった」といった結果となる企業がいるのが事実です。
成功する企業と失敗する企業の差は、戦略的なアプローチにあります。適切な展示会選びから事前準備、当日の運営、そして効果的なフォローアップまで、体系的に取り組むことで確実に成果を上げることが可能です。
この記事では、製造業の展示会出展を成功に導くための具体的な手法と、実際の成功事例を交えながら、実践的なノウハウをお伝えします。
Index
■製造業におけるイベント出展の価値
■製造業が出展するイベントを選ぶ際の基準
■製造業のイベント出展を成功させるコツ【事前準備編】
■製造業のイベント出展を成功させるコツ【当日編】
■製造業のイベント出展を成功させるコツ【アフターフォロー編】
■製造業のイベント出展事例
■まとめ
■製造業におけるイベント出展の価値
デジタルでの情報発信が主流の現代においても、製造業にとってリアルなイベント出展が持つ価値は計り知れません。複雑な技術や製品を扱うからこそ、直接対話し、実物を体験してもらうことの効果は絶大です。ここでは、製造業がイベント出展で得られる4つの特別な価値について解説します。
実物を見せることができる
製造業の製品価値は、カタログのスペックやウェブサイトの動画だけでは決して伝わりきりません。精密加工部品の滑らかな面粗度、新素材の質感、工作機械の静粛な動作音などは、五感を通じて初めて深く理解されるものです。展示会では、この「実物」という最大の武器を活かすことができます。
特に、普段の営業活動では見せることが難しい大型の機械や、複数の製品ラインナップを一堂に会して披露できるため、来場者は製品のスケール感や技術力をダイレクトに体感できます。実物を見せながら商談を進めることで、顧客の深い納得感と信頼を獲得し、購買意欲を大きく高めることが可能です。
商談を加速させる
製造業の製品は高価で、導入検討に数ヶ月から数年かかることも少なくありません。そのため、顧客との信頼関係の構築が不可欠です。展示会は、決裁権を持つキーパーソンと直接顔を合わせてじっくりと対話できるため、長期にわたる検討プロセスを大幅に短縮し、商談を加速させる絶好の機会となります。
また、大規模な展示会には、普段なかなか訪問できない地方の企業も情報収集や商談のために来場します。こちらから出向くことなく、全国の見込み顧客と効率的に接点を持てる点は、費用対効果の面でも非常に大きなメリットです。
普段会えない人と会いやすい
展示会は、社外だけでなく社内の「普段会えない人」を結びつける価値も持っています。ブースに営業担当者だけでなく、製品を熟知した企画開発担当者や技術者が参加することで、来場者からの専門的な質問にその場で即答でき、商談がスムーズに進みます。これにより、顧客の信頼感は格段に高まります。
同時に、開発担当者にとっては、顧客が製品を前にしてどのような反応を示すのか、どんな課題を持っているのかといった「生の声をヒアリングする」貴重な機会にもなります。この一次情報は、次の製品開発やサービス改善に繋がる重要なヒントの宝庫です。
競合他社の製品をリアルかつ一堂に見れる
自社製品をアピールするだけでなく、競合他社の動向を合法的に、かつ深く調査できるのも展示会の大きなメリットです。普段はウェブサイトやカタログでしか見ることのできない他社製品を、実際に目で見て、触れて、その質感や操作性を確かめることができます。
競合がどのようなメッセージで製品を訴求しているのか、ブースにはどのような顧客が集まっているのかを肌で感じることで、市場のトレンドや自社の立ち位置を客観的に把握できます。ここで得られたリアルな情報は、自社の製品戦略やマーケティング戦略を練り直す上で、非常に価値のあるインプットとなります。
■製造業が出展するイベントを選ぶ際の基準
展示会出展の成否は、どのイベントを選ぶかという最初のステップでその大部分が決まります。単に来場者数が多いという理由だけで選ぶのではなく、自社の戦略に基づいた客観的な判断が求められます。
ここからはどんなイベントを選ぶべきかについて、3つの観点からお伝えしていきます。
目的に合ったイベントかどうか
すべての意思決定の出発点として、「何のために出展するのか」という目的を一つ、明確に定める必要があります。目的が曖昧なままでは、その後のすべての活動がぶれてしまい、成果を測定することすら困難になります。
製造業における主な出展目的には、
・新規顧客獲得・リード創出
・ブランディング・認知度向上
・既存顧客との関係強化
・市場調査、競合分析
などがあります。
目的が定まれば、それに合致した種類の展示会が見えてくるため、選定プロセスが格段に効率化されます。
自社の製品・サービスとイベントテーマの親和性はあるか
出展するイベントや展示会のテーマと、自社の製品・サービスが提供する価値が一致していることは絶対条件です。テーマとの不一致は、貴重な時間とコストの浪費に直結します。
親和性を確認するためには、過去の出展企業リストを精査することが有効です。自社の競合企業やサプライチェーン上で関係の深い企業が名を連ねていれば、その展示会が適切なターゲット層を惹きつけている有力な証拠となります。
費用対効果や集客力が大きいかどうか
展示会出展は大きな投資です。出展料、ブース設営費、スタッフ人件費、交通費、販促物制作費など、総額でのコストを正確に算出し、設定した目的に対してそのコストが見合っているかを検討する必要があります。
重要なのは、来場者の「数」よりも「質」です。来場者数が少なくても、自社のターゲットとする大手企業の決裁権者が多数参加するような専門性の高いイベントであれば、費用対効果は非常に高くなる可能性があります。
ひとえに「製造業向け展示会」と言っても、その規模や専門性は様々です。来場者の「量」を重視する総合展から、「質」を重視する専門展まで、自社の目的に合ったものを選ぶための参考として、いくつかの主要な展示会の特徴を見てみましょう。
| 展示会名 | 主なテーマ | 対象来場者 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ものづくりワールド | 機械部品、加工技術、DXソリューション | 設計、開発、製造、生産技術、購買部門 | 製造業の総合展として高い集客力 |
| スマート工場 EXPO | IoT, AI, FA/ロボット | 工場長、生産技術、経営企画 | 工場自動化に特化した専門性 |
| インターネプコン ジャパン | エレクトロニクス製造・実装技術 | 電子機器、半導体、自動車・電装品メーカー | エレクトロニクス業界の決裁権者が集結 |
| 高機能素材Week | 先端材料、加工技術 | 素材メーカー、製品開発、研究・開発部門 | 新素材・新技術の情報交換の場 |
■製造業のイベント出展を成功させるコツ【事前準備編】
展示会の成功は、会期当日ではなく、準備期間に決まります。特に製造業は「実物」という最大の武器をどう活かすか、そのための周到な事前準備が成果を左右します。
ここからは、事前準備において重要なポイントを詳しく解説していきます。
具体的な目標(KPI)の設定
展示会選びで定めた大目標を、さらに具体的で測定可能な行動目標に落とし込みます。SMART原則(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)を用いた目標設定が効果的です。
定量的目標として「3日間で300枚の名刺獲得」「導入時期が半年以内の見込み顧客50件創出」「会期後1ヶ月以内に20件の商談アポイント獲得」などを設定し、定性的目標として「ブース訪問者の40%が自動車業界の担当者である状態」などを定めます。
「実物」を活かすブース装飾とレイアウト
ブースは策定したマーケティング戦略を物理的に具現化する空間です。製造業のブース設計は、「いかにして実物を見せ、体験してもらうか」が最大の論点となります。
特に大型機械を展示する場合、その迫力や精巧な動きが通路からでも一目でわかるような、開放的なレイアウトが鍵となります。遠くからでも製品の存在感が伝わるよう、高さのある看板や統一されたブランドカラーを用いることが効果的です。また、来場者が実機に触れたり、質感を確かめたりできるよう、製品に近づける動線設計と、製品のディテールが美しく見える照明計画が重要になります。
資料やプレゼンテーションの準備
来場者の関心度には温度差があるため、それぞれに応じた情報提供ができるよう、複数の種類の資料を準備します。チラシ・リーフレットは気軽に受け取ってもらうための要点をまとめた資料、詳細カタログ・パンフレットは強い関心を示した来場者向けの詳細資料として使い分けます。
・実機デモ用のプレゼン資料:展示会場の騒音の中でも伝わるよう、「ワンスライド・ワンメッセージ」を徹底し、大きな文字と図で視覚的に訴える資料。
・技術資料(スペックシート):専門性の高い質問を持つ開発・研究職の来場者に対応するための詳細な技術仕様書。
・導入事例集:具体的な成功事例で、費用対効果や信頼性を訴求する資料。
事前集客とアポイント設定
会期前から積極的に情報発信を行い、ターゲット顧客を自社ブースへと誘導する事前集客は極めて重要です。既存顧客や過去の見込み顧客への招待メール、自社サイトでの出展告知、SNSを活用した準備状況の発信などを組み合わせます。
特に重要顧客や有力な見込み顧客に対しては、事前にブースでの面談アポイントを設定しておくことで、確実な商談機会を創出できます。
その際、「新製品の〇〇の実機を国内で初展示しますので、ぜひ直接ご覧ください」「当日は、本製品の開発担当者△△も同席し、技術的なご説明も可能です」といった、「実物」と「人」をフックにした招待メールを送ることで、確実な商談機会を創出できます。
■製造業のイベント出展を成功させるコツ【当日編】
入念な準備を経て迎える展示会当日は、準備した「実物」と「人」という資産を最大限に活用する場です。受動的に待つのではなく、能動的に価値を提供することが重要です。ここではイベント当日の運営に関する重要なポイントを解説していきます。
「営業+技術者」で来場者対応する
ブースの成功は、スタッフの対応で大きく変わります。製造業のブースでは、営業担当者だけでなく、製品を熟知した技術者や開発担当者が必ず参加する体制を組みましょう。通路を歩く来場者に対し、積極的かつ丁寧な声かけでまずは足を止めてもらうことが第一歩です。
「何かお探しですか?」といったありきたりな言葉ではなく、「今日はどのような課題解決のヒントを探しにいらっしゃいましたか?」のように、相手の目的に焦点を当てた質問が効果的です。
また、来場者からの「この部品の材質は?」「この制御は可能か?」といった専門的な質問にその場で即答できることは、他社に対する圧倒的な信頼と優位性に繋がります。また、営業担当者が商談を進める傍らで、技術担当者が顧客のリアルな課題やニーズを直接ヒアリングすることは、次の製品開発に繋がる何よりの財産となります。
競合他社の製品と動向をリアルタイムで調査する
展示会は、自社をアピールする場であると同時に、競合他社の製品をリアルかつ一堂に調査できる絶好の機会です。スタッフ間で時間を調整し、必ず競合ブースのリサーチを行いましょう。
普段じっくり見ることのできない他社製品の質感、操作性、動作音、価格帯などを直接確認します。彼らがどのようなメッセージを打ち出し、どのような来場者が集まっているかを肌で感じることで、市場のリアルなニーズや自社の強みを再認識し、差別化戦略を練るための重要な手がかりとなります。
デモンストレーションの実施
製品の価値を最も雄弁に物語るのは、言葉ではなく、その製品自身の動きです。ライブデモンストレーションは、来場者の理解を深め、信頼を勝ち取るための最も強力な武器となります。
可能であれば、来場者が実際に製品に触れたり操作したりできる「参加型」のデモを取り入れましょう。自ら体験することで得られる実感は、ただ見ているだけの何倍も記憶に残りやすくなります。大型機械で全体の動きを見せることが難しい場合は、一部の機構を実演しつつ、大型モニターで工場での稼働風景を流すなど、リアルとデジタルを組み合わせる手法も有効です。
名刺交換と情報管理
ブースでのすべてのコミュニケーションの重要な目標の一つが、リード情報の獲得、すなわち名刺交換です。会話が自然に盛り上がり、相手の課題に対して具体的なソリューションを提示できるタイミングで名刺交換を提案します。
名刺を受け取ったら、その場で裏面に会話の要点を記録するか、リード獲得用のアプリに入力します。相手が抱える課題、興味を示した製品、見込み度、約束した次のアクションなどを記録することで、後のフォローアップの質を大幅に向上させることができます。
メモしておくと良い内容は下記にまとめております。
・相手の課題や困りごと
・興味を示した製品・サービス
・見込み度(A:今すぐ客、B:見込み客、C:情報収集中)
・決裁権限の有無
・導入検討時期
・約束した次のアクション
■製造業のイベント出展を成功させるコツ【アフターフォロー編】
展示会は、イベントが終了してからが本当の始まりです。特に製造業の製品は高額で導入検討期間が長いため、展示会で得たリードを「成果」に変えるためには、迅速で体系的なアフターフォロー活動が不可欠だからです。
アフターフォローにおいて重要なポイントを詳しく解説していきます。
迅速な初回フォローアップ
展示会後のフォローアップにおいて、最も重要なのは「スピード」です。来場者の記憶と熱意は時間の経過とともに急速に薄れていき、競合他社も同様にアプローチを開始するため、対応の速さがそのまま競争優位性につながります。
理想は展示会終了後24時間以内、遅くとも翌営業日までには最初のお礼メールを送付することです。この初動の速さが数多くのブースの中から自社を思い出してもらう鍵となります。
また、お礼メールは決して一斉送信の定型文であってはなりません。会期中にヒアリングした内容に基づき、見込み度合いに応じてリストをセグメントし、内容をパーソナライズすることが極めて重要です。
「検討期間の長さ」を前提としたリードナーチャリング
展示会で獲得したリードの多くは、すぐに購買を決定する「今すぐ客」ではありません。特に製造業では、導入までに数ヶ月~数年かかるのが普通です。彼らの関心を維持し、時間をかけて購買意欲を高めていく「リードナーチャリング」というプロセスが必要です。
例えば、メールマガジンやターゲットを絞ったメール配信、ウェブセミナーへの招待、お役立ち情報の提供などを通じて、定期的に有益な情報を提供し続けます。売り込み一辺倒ではなく、あくまで顧客の課題解決に役立つ情報を提供し、自社を「信頼できる専門家」として認識してもらうことが重要です。
商談化を高めるための個別提案
リードナーチャリングを進める中で、顧客の行動(価格ページの閲覧、導入事例のダウンロードなど)を追跡し、購買意欲が高まった「ホットリード」には、営業部門が個別アプローチを開始します。
その際、「展示会で対面している」というアドバンテージを最大限に活かします。「先日は弊社ブースで、技術担当の△△の説明にも熱心に耳を傾けていただきありがとうございました」と、当日の会話を起点にすることで、スムーズに具体的な商談フェーズへと移行できます。
長期的な関係構築とリピート受注戦略
一度受注して終わりではありません。新規顧客を長期的に取引を続ける優良なリピート顧客へと育てていく視点が、企業の安定的な成長には不可欠です。
購入後の手厚いカスタマーサポート、既存顧客限定のセミナーや特典の案内、製品改善のためのフィードバック依頼などを通じて、顧客との関係を深化させていきます。新規顧客を獲得するコストは既存顧客の維持コストの数倍かかるため、既存顧客との良好な関係維持は費用対効果の観点からも重要です。
改めて今回お話したプロセスを下記にまとめますので、振り返りにお使いください。
| フォロー段階 | タイミング | アプローチ方法 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 初回フォロー | 展示会後24時間以内 | お礼メール、資料送付 | 記憶の定着、関係継続 |
| ナーチャリング | 2週間~3ヶ月 | メルマガ、セミナー招待 | 関心維持、信頼構築 |
| 商談化 | 1~6ヶ月 | 個別提案、デモ実施 | 具体的な購入検討促進 |
| 長期関係構築 | 継続的 | サポート、新製品案内 | リピート受注、アップセル |
■製造業のイベント出展事例
ここまでイベント出展を成功させるためのポイントを解説してきましたが、ここでは実際に企業がどのようなブースを展開しているのか、具体的な成功事例を見ていきましょう。
事例1:株式会社ダンロップタイヤ様 TOKYO AUTO SALON 2025
DUNLOPファンの拡大および、ブランドへの愛着を背景とした購入層の獲得を目指し、「TOKYO AUTO SALON 2025」の出展ブースを企画・設計から運営まで一貫してプロデュースした事例です。
『Exploring Every Route』というテーマのもと、どんな道でも走破できるという世界観を表現。山道・雪道・橋・星空・全天候という5つのシーンを設け、それぞれに対応したタイヤを展示しました。各シーンでリアルな演出にこだわることで、DUNLOPタイヤの特長と魅力を際立たせる空間を実現しています。
また、お気に入りのタイヤを撮影・投稿するSNSキャンペーン『推しタイヤをみつけよう』では多くの来場者から反響があり、ブランド認知向上と関係性強化に寄与しました。
事例2:株式会社コマツ様 第6回 建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO2024)
働き手の高齢化や労働力不足といった建設業界の課題に対応するため、国内最大級の展示会「CSPI-EXPO2024」にて、DXソリューションを活用した新しい建設現場の在り方を提案した事例です。
未来の仮想空間を模した「GRID空間」に建設機械の実物を展示し、デジタルとフィジカルが融合した持続可能な建設現場のビジョンを表現。デジタルソリューション「スマートコンストラクション®」の年間1万3000件を超える導入実績を、約1万3000個のGRIDで視覚化し、圧倒的な量で来場者に強いインパクトを与えました。
また、展示物は木工とファブリックに分解してリサイクル率を向上させるなど、サステナビリティへの取り組みも体現しています。
事例3:トヨタ紡織株式会社様 JAPAN MOBILITY SHOW 2023
自動車用シート・内装部品を手掛けるトヨタ紡織株式会社の「Japan Mobility Show 2023」ブースにおいて、企画・デザイン・施工・運営・コンテンツ制作・PRサポートまでを包括的に担当した事例です。
出展の重要テーマであった「モビリティの技術が暮らしや未来まで広がる可能性」を来場者に伝えるため、会社の源流である繊維事業を想起させる「織」をモチーフとしたブースデザインを制作。ライブ感溢れるステージコンテンツや、分かりやすい製品カテゴリ分けを通じて、企業のビジョンを体現しました。
さらに、りんかい線の駅や車両内に交通広告を出すなど、ブースへの来場を促進する施策も合わせて提案・実施しました。
事例4:ヤマザキマザック株式会社様 日本国際工作機械見本市(JIMTOF 2022)
大手工作機械メーカーのヤマザキマザック株式会社が、世界最大級の工作機械見本市である「JIMTOF 2022」に出展した際の事例です。「カーボンニュートラルに向けた、マザックのデジタル製造ソリューション」をテーマに掲げました。
最新技術であるデジタルツインの世界観を表現するため、ブース内にオリジナルAIを登場させ、デジタルとリアルの境界線を超えた近未来的な体験空間を創出。テクノロジーの力で環境問題を解決するという企業の姿勢と、デジタルとリアルが融合することで生まれる新しい製造業の未来を、デザインの力で表現しました。
■まとめ
製造業におけるイベント出展の成功は、決して偶然の産物ではありません。明確な戦略に基づき、体系的なプロセスを実行した結果としてもたらされるものです。
成功の鍵は、周到な「事前準備」、能動的な「当日運営」、そして迅速かつ規律ある「アフターフォロー」という三つのフェーズがすべて高いレベルで実行されることにあります。最も重要なのは、出展の「目的」を明確に定め、それに基づいてすべての意思決定を行うことです。
展示会出展は多大なリソースを要する投資ですが、正しい戦略と実行計画に基づけば、他のどのマーケティング手法よりも強力なビジネス成長のエンジンとなります。本記事で解説したノウハウを活用し、貴社の次なる展示会出展を成功に導いてください。
もし、この記事でご紹介したような戦略的なブース企画や、来場者の記憶に残る体験価値の創出にご興味がございましたら、私たち博展にぜひ一度ご相談ください。多くの製造業の出展を成功に導いてきた経験を元に、貴社の課題解決に向けた最適なプランをご提案します。