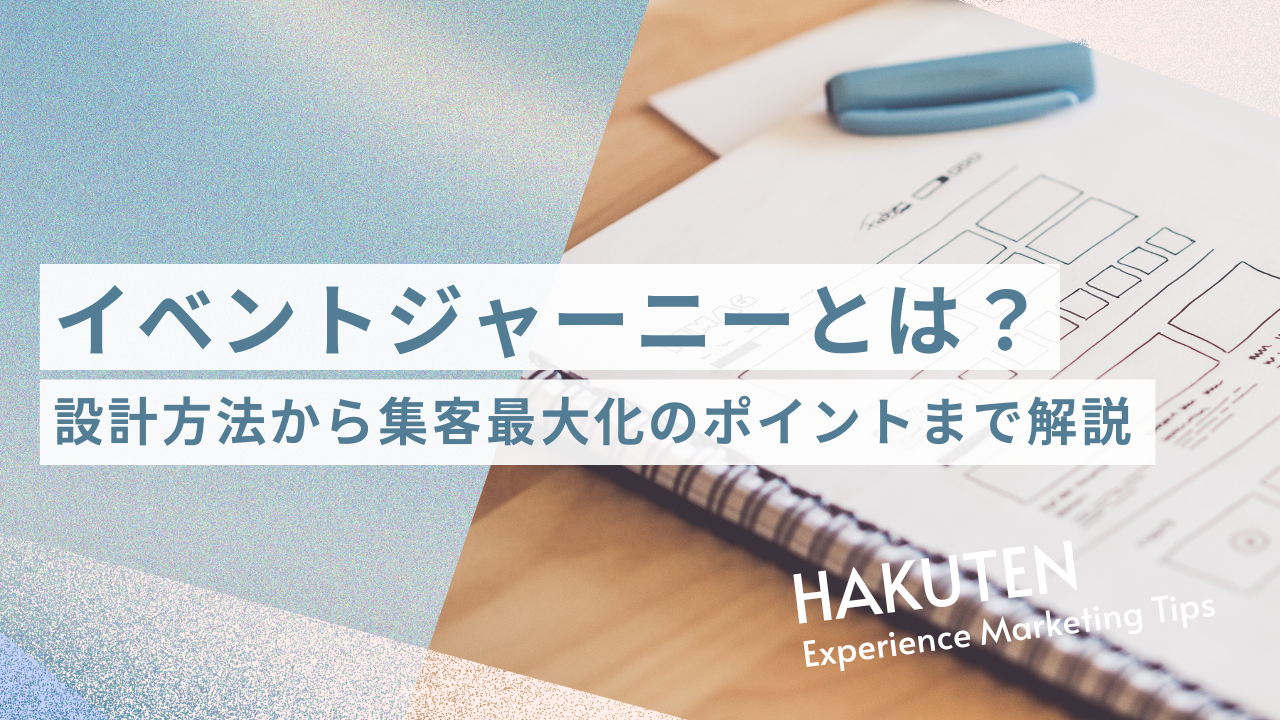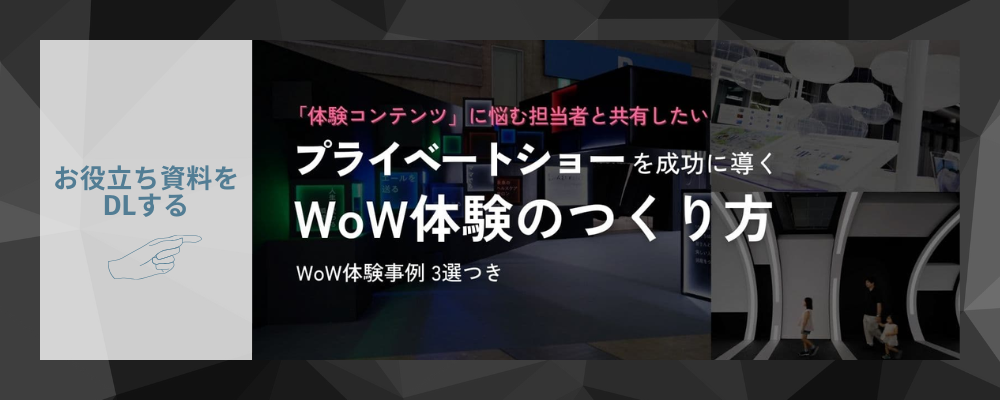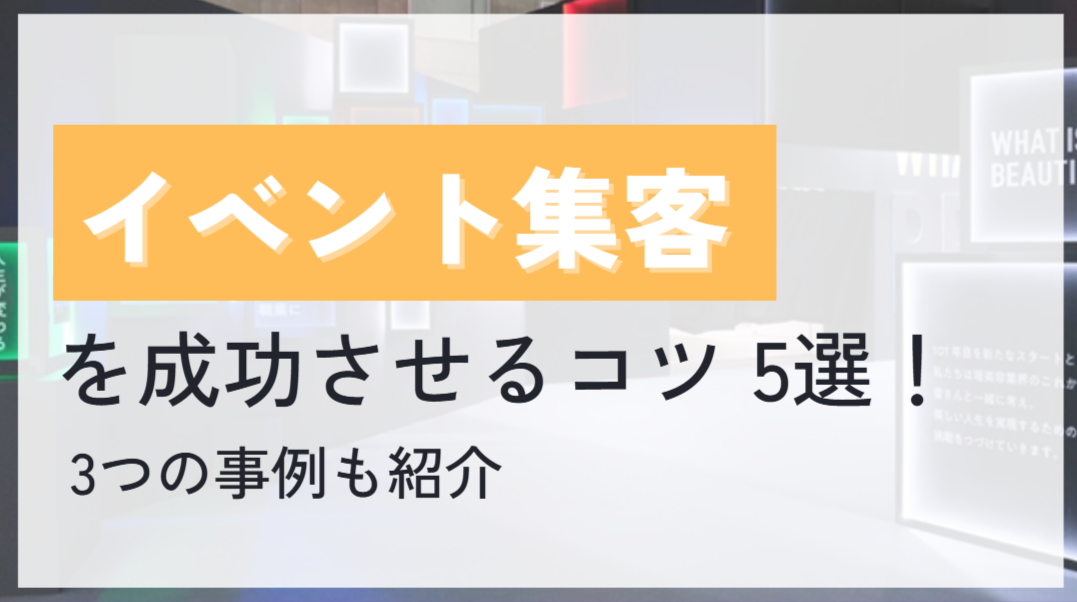「あれだけ告知したのに、申込数が全然伸びない…」
「イベント当日は手応えがあったのに、その後の商談にまったく繋がらない…」
このように、イベントの集客やその後の成果に、頭を悩ませている担当者の方は少なくないのではないでしょうか。「とりあえず集客して、当日に頑張る」というやり方では、なかなか成果が出にくい時代になっています。
そこで重要になるのが、「イベントジャーニー」という考え方です。お客様がイベントを知ってから参加し、その後の関係が続いていくまでの一連の体験を、戦略的に設計していくアプローチを指します。
この記事では、この「イベントジャーニー」とは何か、そして従来の集客手法と何が違うのかをわかりやすく解説します。「集客がうまくいかない原因がわからない」「イベントの成果を最大化したい」そんな方にお読みいただきたい内容です。
Index
■イベントジャーニー設計とは
■イベントジャーニー設計のメリット
■イベントジャーニー設計の落とし穴
■集客成果を最大化するイベントジャーニー設計の5ステップ
■効果測定と改善方法
■まとめ
■イベントジャーニー設計とは
「イベントジャーニー」という言葉は聞いたことがあっても、「具体的に何をどう設計するのか」と聞かれると、はっきりと説明するのは難しいかもしれません。
そこで、まずはイベントジャーニーの基本的な定義と、なぜ今この考え方が重要なのかについて解説します。
イベントジャーニー設計の基本概念
イベントジャーニー設計とは、一言でいえば、見込み客の心理状態と行動を時系列で可視化し、それぞれの段階で最適なアプローチを行うことで、集客効果を最大化する手法です。
つまり、お客様の視点に立って、出会いから関係構築までの一連の体験全体をデザインしていくことになります。一方的に情報を発信するのではなく、お客様の気持ちに寄り添い、自然な形で参加意欲を高めていく。それが、イベントジャーニーの基本的な考え方です。
カスタマージャーニーマップとの関係性
この考え方は、マーケティングでおなじみの「カスタマージャーニーマップ」を、イベントという特定のシーンに応用したものです。
通常のカスタマージャーニーが商品購入までの長期的なプロセスを描くのに対し、イベントジャーニーは「イベント」という限定的なプロセスに特化しているのが特徴です。参加前だけでなく、イベント後のフォローアップまで含めて設計することで、その後の長期的な顧客との関係づくりにも大きく貢献します。
■イベントジャーニー設計のメリット
では、イベントジャーニーを設計することで、具体的にどのようなメリットが生まれるのでしょうか。代表的な3つのメリットをご紹介します。
参加者体験(CX)の向上が期待できる
イベントジャーニーを設計する最大のメリットは、参加者の体験価値、すなわちCX(カスタマーエクスペリエンス)が向上することです。
イベントジャーニーマップは、参加者がイベントを認知し、申込、参加し、そしてイベント後に関係性が続いていくまでの一連の行動、思考、感情を可視化します。これにより、「申込フォームが分かりにくい」「会場での案内が不十分だった」といった、これまで見過ごされがちだった具体的な課題や不満を発見しやすくなります。
これらの課題一つひとつに的確な解決策を講じることで、イベント全体の質が向上し、参加者の満足度を大きく高めることができます。
チーム・関係者間での共通認識を醸成できる
イベントの成功には、企画、集客、運営、営業など、様々な立場のチームや関係者の連携が不可欠です。イベントジャーニーマップは、こうした関係者全員が「参加者の視点」という共通認識を持つための強力なツールとなります。
「このタイミングで、参加者はこんな気持ちになっているはずだ」「だから、我々はこういうアプローチをすべきだ」といった具体的な行動指針を全員で共有できるため、部門間の認識のズレを防ぎ、スムーズな連携を促進します。結果として、一貫性のある質の高いイベント体験を提供できるようになります。
新たな集客チャネルや施策の発見につながる
イベントジャーニーを設計する過程では、参加者が「どのような経路でイベントを知り、申込に至るのか」を改めて深く分析することになります。
この分析を通じて、既存の集客チャネルが抱える課題が明確になるだけでなく、「こんなメディアにもアプローチできるのではないか」「こういう切り口のSNS投稿が響くかもしれない」といった、これまで気づかなかった新たな集客チャネルや施策の発見につながることがあります。時代やターゲットの変化に合わせて集客戦略を見直し、最適化していく上で、イベントジャーニー設計は大きなヒントを与えてくれます。
■イベントジャーニー設計の落とし穴
ここでは、多くのイベント主催者が陥りがちな3つの失敗パターンとその解決策を解説します。
落とし穴1:主催者視点の一方的なジャーニー設計
ありがちな失敗が、主催者側の「伝えたいこと」ばかりを優先してしまうパターンです。イベントの概要や立派な登壇者のプロフィールをいくら発信しても、お客様が「知りたいこと」とズレていては、心は動きません。
「このイベントに参加すれば、自分のどんな課題が解決されるんだろう?」お客様が本当に知りたいのは、この一点です。ペルソナの視点に立ち、「何に困っていて、何を知りたいのか」に寄り添い、その答えとなる情報を適切なタイミングで届ける姿勢が、信頼を生みます。
落とし穴2:タッチポイント間の情報分断
「SNSの投稿を見て期待してサイトを訪れたら、書いてあることが微妙に違う…」「メルマガの内容と、申込ページの案内が食い違っている…」
このように、チャネルごとに発信する情報が分断され、一貫性がない状態は、お客様を混乱させ、不信感を与えてしまいます。せっかく高まった参加意欲も、こうした小さな違和感で一気に冷めてしまうのです。すべての接点(タッチポイント)でメッセージを統一し、スムーズな体験を提供することが不可欠です。
落とし穴3:申込直前での不要なハードル設定
「よし、申し込もう!」とお客様の気持ちが一番盛り上がった瞬間に、ずらりと並んだ入力項目や、面倒な会員登録が目の前に現れる…。これは、機会損失に直結する非常に危険な落とし穴です。
まず最も多いのが、入力項目が多すぎるケースです。名前や連絡先だけでなく、アンケートのような質問が延々と続くと、参加者は入力の手間から申し込みを諦めてしまいます。この段階で本当に必要な情報を見極め、必須項目を最小限に絞ることが重要です。
よくある申込みフォームでの問題を下記にまとめましたので、ぜひチェックしてみてください。。
| よくある問題 | 参加者への影響 |
|---|---|
| 入力項目が多すぎる | 入力の手間による離脱 |
| 会員登録が必須 | 追加手続きの煩わしさ |
| 決済方法が限定的 | 希望する支払い方法がない |
| エラーメッセージが不親切 | 問題解決に時間がかかる |
申込フォームは、「いかに手間をかけさせないか」が全てです。最後の最後でお客様をがっかりさせないよう、シンプルで分かりやすい設計を徹底しましょう。
■集客成果を最大化するイベントジャーニー設計の5ステップ
「イベントジャーニーの重要性はわかったけれど、具体的に何から始めればいいのだろう?」そんな疑問にお答えするために、ここでは集客成果に直結する5つのステップを、順を追って解説していきます。
このステップに沿って思考を整理することで、お客様の気持ちに寄り添った、効果的なアプローチが見えてくるはずです。
ステップ1:ペルソナ設定で理想の参加者像を明確化
まず最初の、そして最も重要なステップです。あなたのイベントに、「本当に来てほしい人」はどんな人ですか?
この「誰に」が曖昧なままでは、どんな施策も的が外れてしまいます。イベントジャーニー設計の全ての土台となるのが、このペルソナ設定です。年齢や役職といったデモグラフィック情報だけでなく、その人が「日々どんなことで悩み、何を期待してイベントに参加するのか」「普段、どこで情報を集めているのか」といったサイコグラフィック情報も含めて、具体的な人物像まで深く掘り下げて描くことが成功の鍵となります。
ペルソナ設定時に考慮すべき主要な要素は以下の通りです。
・基本属性(年齢、性別、職業、役職など)
・現在抱えている課題や悩み
・イベントに参加する動機や期待値
・情報収集に使用する媒体やチャネル
・意思決定に影響する要因
ステップ2:ゴールとKPI設定
ペルソナが定まったら、次はこのジャーニーの「ゴール」を決めます。「とにかくたくさんの人に来てほしい」といった漠然とした目標ではなく、「誰に、どうなってほしいのか」を具体的に設定することが重要です。
例えば、「〇〇という課題を持つ担当者100名に申し込んでもらい、参加率は80%を目指す」といった数値目標を設定します。また、ゴールとしての申込数だけでなく、その後の参加率や新規顧客の獲得数など、量と質の両面からKPIを定めることで、施策の方向性がブレなくなります。
ステップ3:行動フェーズの定義と心理状態の把握
ゴールが決まったら、そこに至るまでの「道のり」を具体的に描いていきます。お客様がイベントを知ってから申し込むまでには、いくつかの心理的な段階があります。一般的には「認知」「興味・関心」「比較・検討」「申込」といったフェーズに分けられます。
ここで大切なのは、「この段階にいるお客様は、どんな気持ちで、何を考えているだろう?」と、ペルソナの気持ちになりきって想像することです。この心理状態の理解が、心に響くアプローチの土台となります。
ステップ4:タッチポイントと施策の整理
各フェーズでお客様の心理を想像できたら、次はタッチポイント(顧客接点)と具体的な施策の整理です。
例えば、認知フェーズのお客様には、まずSNS広告で『おっ!』と思わせる。興味を持ってくれた人には、メルマガで登壇者の魅力を伝えて期待感を高めるというように、各段階で最適な接点とコンテンツを戦略的に配置していきます。
それぞれのフェーズごとの施策例は下記の表を参考にしてみてください。
| フェーズ | 主要タッチポイント | 効果的な施策例 |
|---|---|---|
| 認知 | SNS、Web広告、PR | ハッシュタグキャンペーン、プレスリリース |
| 興味・関心 | オウンドメディア、メルマガ | 登壇者紹介記事、過去イベントレポート |
| 比較・検討 | ランディングページ、FAQ | 参加者の声、早期割引特典 |
| 申込 | 申込フォーム、決済画面 | 入力項目最小化、簡単決済導入 |
ステップ5:感情の設計とマッピング
イベントジャーニー設計の最もクリエイティブで重要な部分が「感情の設計」です。各接点でお客様に「どんな気持ちになってもらいたいか」を意図的にデザインしていきます。
最初の広告で「面白そう!」とワクワクさせ、詳細ページで「これは自分のためのイベントだ」と確信させ、申込完了で「当日が待ちきれない!」と期待を最高潮に高める。
このように、参加への期待を高めると同時に、不安や面倒といった障壁を取り除くアプローチを組み合わせることで、お客様の心が自然と「参加したい!」という方向へ動いていくのです。
■効果測定と改善方法
イベントジャーニーは、「作って終わり」ではありません。その効果をきちんと測定し、改善を重ねていくことで、より強力な集客の仕組みへと育てていくことができます。
各フェーズのKPI設定と測定方法
「なんとなく良かった」で終わらせないために、ジャーニーの各フェーズで適切なKPI(重要業績評価指標)を設定し、データに基づいて成果を振り返ることが重要です。
例えば、「認知」フェーズなら広告の表示回数、「興味・関心」フェーズならコンテンツの閲覧時間、「比較・検討」フェーズなら申込ページへのアクセス数、そして「申込」フェーズでは申込完了率、といったように、各段階での目標達成度を測る指標を決め、その数値を追いかけていきます。
改善サイクルの構築とPDCA運用
イベントジャーニーの改善は、一度きりの見直しで終わるものではありません。イベントを開催するたびにPDCA(計画→実行→評価→改善)サイクルを回し、継続的に磨き上げていくことが大切です。
前回のデータから見えた課題を基に、次回のジャーニー設計に改善を加えていく。この地道な積み重ねが、イベントの集客効果を飛躍的に高めていきます。
| フェーズ | 主要KPI | 改善のチェックポイント |
|---|---|---|
| 認知 | リーチ数、インプレッション数 | ターゲティング精度、メディア選択 |
| 興味・関心 | エンゲージメント率、滞在時間 | コンテンツの魅力度、情報の分かりやすさ |
| 比較・検討 | コンバージョン率、離脱率 | 価値提案の明確さ、競合優位性 |
| 申込 | 申込完了率、決済完了率 | フォームの使いやすさ、決済手段の充実 |
■まとめ
この記事では、イベントの集客効果を最大化するための「イベントジャーニー設計」について解説してきました。優れたイベントジャーニーは、単に申込数を増やすだけでなく、参加者の満足度を高め、主催者との長期的な信頼関係を築く土台となります。
まずは自社のイベントジャーニーを客観的に見直し、「お客様をがっかりさせているポイントはないか?」という視点でチェックすることから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな改善の積み重ねが、きっと大きな成果に繋がるはずです。
しかし、ご紹介した考え方を実践しようとしても、「自社だけでは客観的な分析が難しい」「各フェーズでの最適な施策がわからない」といった壁に直面することもあるかもしれません。
私たち博展は、数多くのイベントを成功に導いてきた経験とノウハウを基に、お客様のビジネスに最適なイベントジャーニーの設計から実行、改善までをワンストップでサポートします。ぜひ一度お気軽にご相談ください。