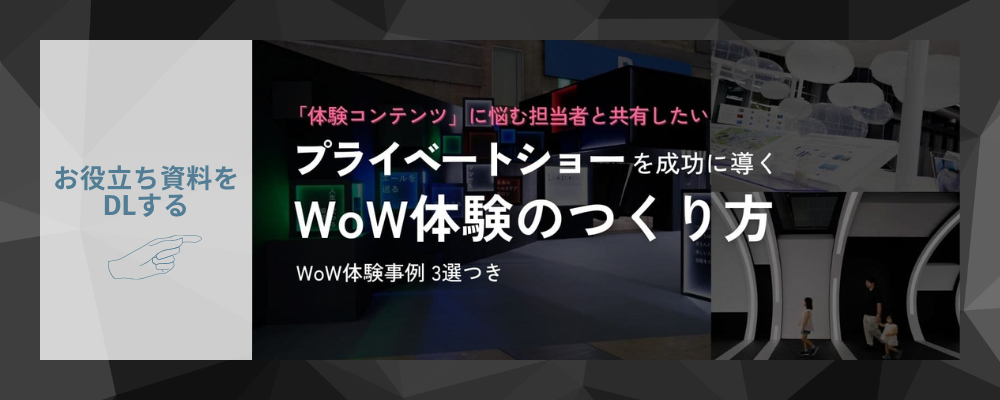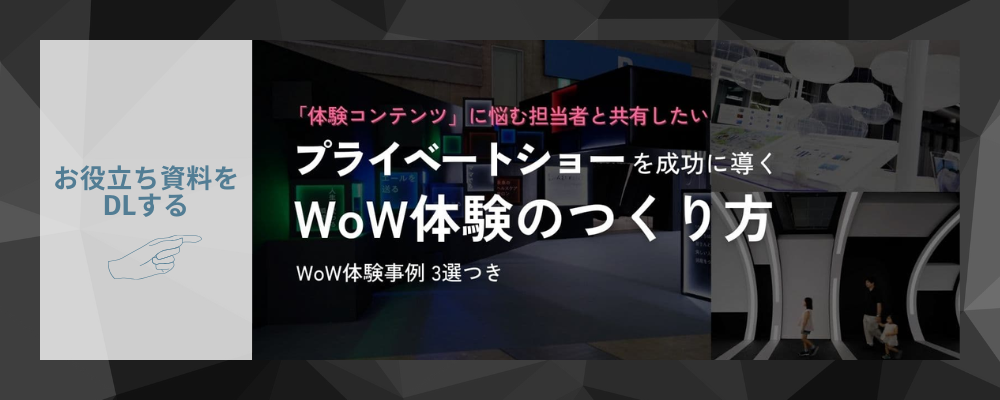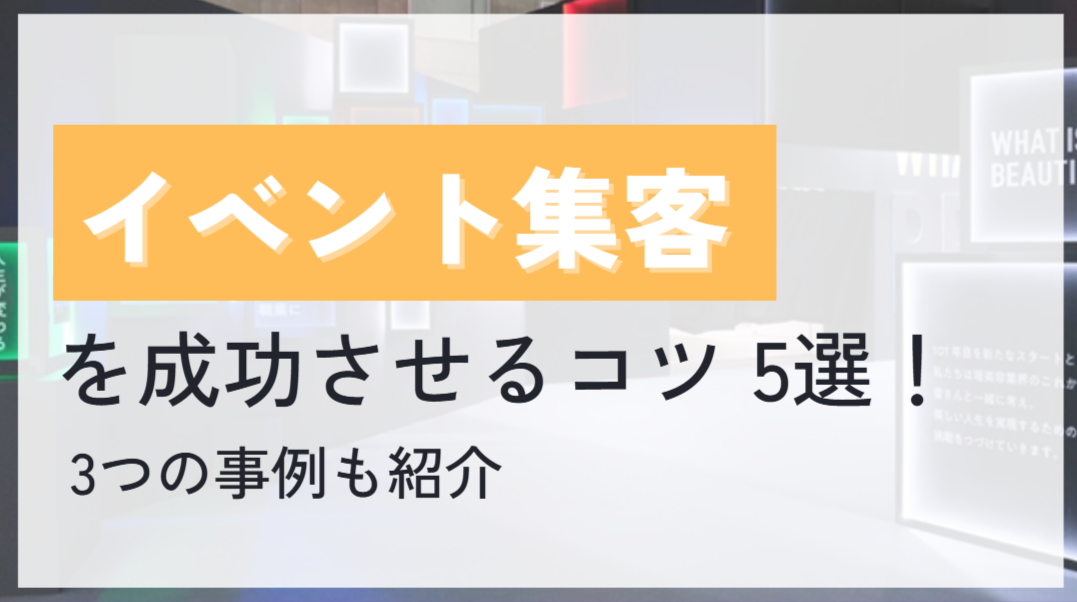イベントマーケティングにおいて、「いかにお客様の心を掴み、記憶に残る体験を提供できるか」という課題は、多くの担当者にとって悩みの種ではないでしょうか。
単に製品を並べて説明するだけでは、お客様の記憶には残りません。これからの時代に求められるのは、お客様の期待を大きく超え、「すごい!」と思わず声が出るような感動的な出会い、すなわち「WoW体験」です。
そこで今回は、この「WoW体験」とは何か、なぜ強力な集客効果を生むのか、そして実践する上で押さえるべきポイントまでを徹底解説します。「やったほうがいいのはわかっているけれど、具体的にどうすれば…」そんな方にお読みいただきたい内容です。
Index
■WoW体験とは?
■なぜ今、WoW体験が求められているのか
■WoW体験が集客に絶大な効果をもたらす3つの理由
■WoW体験を設計するうえで押さえるべきポイントと注意点
■ブランドの価値を伝える、WoW体験の事例
■まとめ
■WoW体験とは?
「イベントで何か特別な体験を提供したいけど、結局ありきたりな内容になってしまう……」
「来場者の心を本当に動かすような、記憶に残る企画はどうすれば作れるのだろう……」
このように、イベント担当者なら誰もが一度は直面する「体験コンテンツ」の悩み。その成功のカギとして注目されているのが「WoW体験」です。
WoW体験とは一言でいえば、それは「来場者が思わずワクワクするような体験」のことです。そして、その「ワクワク」は、主に次の3つの要素から生まれると考えられます。
- 驚き:来場者の期待を心地よく超えていく、斬新な体験
- 感動:来場者一人ひとりの想いとブランドのメッセージが繋がり、心を動かされる体験
- 新たな発見:これまでになかった新しい気づきや、物事の価値を再認識させられる体験
単に製品情報を伝えるだけでは、来場者の記憶には残りません。しかし、WoW体験を通じてブランドの在り方や「らしさ」を共有できれば、それは忘れられない記憶となり、長期的な成果へと繋がっていきます。
■なぜ今、WoW体験が求められているのか
現代において、WoW体験が求められている背景は大きく3つ考えられます。重要性を正しく理解した上で実践することで、より魅力的なWoW体験を作れるようになりますよ。
リアルイベントでしか得られない価値
デジタルでの接点が当たり前になったからこそ、顧客の態度変容を生むきっかけとして「記憶に残る体験」の価値が再認識されています。五感で感じ、心が動かされるような体験は、オンラインでは決して得られないリアルイベントならではの役割なのです。
例えば、自動車メーカーの試乗会を想像してみてください。単に車に乗るだけでなく、オフロードコースやサーキットといった、その車の性能を最大限に引き出せる特別な環境が用意されています。そこで感じるエンジンの鼓動、シートの質感、タイヤが地面を掴む感覚は、スペック表を眺めるだけでは決して伝わりません。また、化粧品ブランドの体験イベントでは、プロのメイクアップアーティストから直接自分に合った製品を提案してもらえます。ブランドの香りに包まれた空間で、美しくなっていく高揚感を味わうことは、ECサイトの画面を眺めるだけでは得られない特別な記憶となるでしょう。
このように、製品やサービスが持つストーリーや価値を、身体を通して実感できる「場」を提供することが、顧客の深いブランド理解とエンゲージメントに繋がるのです。
コモディティ化が進み、「らしさ」の共有が不可欠に
あらゆる業界で製品やサービスの「コモディティ化(均質化)」が進んでいます。機能やスペックだけでは、他社との差別化が非常に難しい時代です。だからこそ、自社ならではの価値観やブランドの「らしさ」を来場者と共有し、共感を得ることが重要になっています。
例えば、あるアウトドアブランドは、製品の展示販売だけでなく、キャンプをしながら楽しめる音楽ライブや、環境問題をテーマにしたワークショップを盛り込んだフェスを開催します。これにより、顧客は製品の機能だけでなく、ブランドが大切にする「自然との共生」という姿勢やカルチャーそのものに共感し、熱心なファンになっていきます。あるいは、一杯のコーヒーにこだわるブランドであれば、バリスタが生産者の想いや焙煎へのこだわりといったストーリーを語りながらテイスティングを行うイベントを開くかもしれません。そうすることで、それは「ただの飲み物」から、「特別な価値を持つ一杯」へと変わり、顧客の愛着を深めます。
イベント空間のデザイン、スタッフの立ち居振る舞い、提供されるコンテンツの全てを通してブランドの「らしさ」を一貫して表現することが、顧客の心の中に自社の確固たるポジションを確立する鍵となるのです。
顧客との「未来共創」への意識の高まり
製品を選ぶ際、その背景にある企業のあり方や姿勢を重視する顧客が増えています。単なる売り手と買い手ではなく、未来を共に創っていくパートナーとしての関係性が求められているのです。
その関係性を築く上で、リアルイベントは顧客を「共創パートナー」へと変える力を持っています。IT企業のユーザーカンファレンスが良い例です。そこでは、新製品の発表に留まらず、ユーザーが製品の改善点や新機能について開発者と直接ディスカッションする場が設けられます。顧客は「単なる利用者」から、ブランドの未来を一緒に創る「当事者」へと意識が変わり、ロイヤリティが格段に向上します。食品メーカーが開催するファンミーティングも、まさに共創の場と言えるでしょう。新商品の試食会で味やパッケージについて顧客から直接フィードバックをもらい、その声が商品に反映されるプロセスを共有すれば、「自分たちの声でブランドが育っていく」という特別な体験が生まれます。
このように、顧客を単なる「受け手」としてではなく、ブランドを共に創り上げていく「パートナー」として巻き込む姿勢を示すことが、長期的な信頼関係の構築に不可欠なのです。
こうした3つの変化に伴い、イベントの成功指標も短期的な「定量(計数)情報」だけでなく、より長期的で「定性的な成果」が重視されるようになっています。
来場者数や商談数といった短期的な指標も依然として重要ですが、これからは「未来共創につながる関係構築」や「ブランドらしさの共有」といった、長期的な視点での成果がより重要になっていくのです。
WoW体験は、この長期的な成果を叶えるための有効なアプローチとなります。
■WoW体験が集客に大きな効果をもたらす3つの理由
WoW体験が集客に大きな効果を発揮する理由は3つあります。
- 1:強力な口コミ(UGC)が生まれ、新規顧客を呼び込む
- 2:ブランドへの注目度が高まり、選ばれる理由を作る
- 3:既存顧客を熱狂的なファンにし、リピート集客を盤石にする
それぞれ詳しく解説していきますね。
理由1:強力な口コミ(UGC)が生まれ、新規顧客を呼び込む
「これ、すごく良かったよ!」と思わず誰かに伝えたくなる。そんな感動的な体験は、SNS上などで自然に口コミ(UGC)を生みます。
人は本能的に、誰かと共有したい生き物です。WoW体験は、この人間心理を捉え、お客様を「単なる利用者」から「熱心な情報発信者」へと変える力を持っています。体験者によるリアルな口コミは何よりも強い説得力を持ちます。
さらに、イベントの写真や動画と共に行われるSNSでの共有は、視覚的なコンテンツとして感動を瞬時に伝え、驚くほど広範囲へ情報を伝播させます。
また、熱心な顧客は自身のブログなどにオンラインレビューとして詳細な体験レポートを公開してくれることもあります。これらは、購入を検討している人が検索した際の意思決定に大きな影響を与える貴重な情報源となります。
体験者が業界のイベントなどで専門家として言及すれば、それは個人の推薦を超え、業界全体への評価を高める強い影響力を持つことになります。
このように、体験者によるリアルな口コミは、どのような広告よりも強い説得力を持つのです。
理由2:ブランドへの注目度が高まり、選ばれる理由を作る
製品やサービスが溢れる今の時代、機能や価格だけで「選ばれる理由」を作るのは、ますます難しくなっています。そんな中で、ユニークで感動的な体験は、それ自体が選ばれる理由になるのです。
「何か面白いことをやっている」といった評判は、メディアやインフルエンサーの関心を引き、自然な形で注目を集めるきっかけを創り出します。
特に、従来の手法では差別化が難しかった業界でも、体験のデザイン次第で独自のポジションを築くことが可能です。この独自性は他社には真似のできない、持続的な競争力となるでしょう。
理由3:既存顧客を熱狂的なファンにし、リピート集客を盤石にする
WoW体験のすごいところは、一度きりのお客様を「このブランドをずっと応援したい!」と思わせる熱狂的なファンに変えてしまう力です。
新規顧客の獲得コストが上がり続ける中で、既存のお客様との関係を深めることは非常に重要な戦略です。ファンになってくれたお客様は、製品を買い続けてくれるだけでなく、友人や知人を連れてきてくれる「歩く広告塔」のような存在になります。
さらに、そうして紹介された新規のお客様は、すでにある程度の信頼感を持って接触してくれるため、その後の成約率やLTV(顧客生涯価値)も高くなる傾向にあります。
■WoW体験を設計するうえで押さえるべきポイントと注意点
ここまでの理論を、より具体的なシーンに落とし込んでみましょう。今回は多くの企業が力を入れる展示会やイベントを例に、押さえるべきポイントと、陥りがちな落とし穴について解説します。
顧客と直接対話できる貴重な機会だからこそ、WoW体験がもたらす印象的な出会いは非常に効果的です。この場で生まれるポジティブな感情が、顧客との長期的な関係性を築くための重要な第一歩となります。
1:自己満足な演出になっていないか
企業側が「これはすごいだろう!」と考える演出が、実は来場者にとっては「だから何?」と思われている…。これは、非常によくある失敗です。
例えば、ある製造業の展示会で、自社の精密部品を紹介するために、巨大なLEDスクリーンに美しいCG映像だけを延々と流しているケースを想像してみてください。しかし、そのブースを訪れた設計担当者が本当に知りたいのは「その部品を使うと、自社製品の耐久性がどれだけ向上するのか?」といった具体的なデータです。映像の美しさだけでは、その問いに答えられません。
最新技術を使った派手な演出も、来場者の課題解決や興味関心と結びついていなければ、記憶に残りません。大切なのは、来場者の視点で「この体験が、自分にどんな良いことをもたらすのか」が明確に伝わることです。
事前の来場者リサーチや過去の展示会での反応分析により、ターゲット層の真のニーズを把握することが成功の鍵となります。
2:体験のプロセスが複雑すぎないか
せっかくの素晴らしい体験も、そこに至るまでの手順が複雑だったり、時間がかかりすぎたりすると、お客様は感動する前に疲れてしまいます。
どのようなイベントであれ、お客様が使える時間や集中力には限りがあります。体験の設計では「シンプルさ」と「インパクト」のバランスを考え、ストレスなく核心的な価値が伝わる構成を心がけることが重要です。
3:感動を「一回きり」で終わらせていないか
イベント当日の会話で得たヒントを基に、相手が「まさにこれが欲しかった」と思うような情報を、予期せぬタイミングで届ける。これは、関係性を一気に深めるチャンスです。
それは、単なるフォローアップを超えた、新たなWoW体験の始まりです。相手の関心事に特化した業界レポートや、課題解決のヒントになるような事例など、相手にとって本当に価値のある情報を提供することが鍵となります。
4:顧客からのアクションを「待つだけ」になっていないか
会話の中から相手のライフスタイルや価値観を読み取り、まだ言葉になっていない「隠れたニーズ」を予測し、その一歩先をゆく提案する。
これができれば、企業は単なる「売り手」ではなく、「人生に寄り添うパートナー」として認識されます。「今後のことを考えると、将来的には〇〇といった選択肢もありますよ」といった先回り提案は、「私のことをを深く理解してくれている」という強い信頼感を与えます。
■ブランドの価値を伝える、WoW体験の事例
では、実際にどのようなイベントが「WoW体験」を生み出しているのでしょうか。ここでは、ブランドの価値を深く伝えることに成功した3つの事例をご紹介します。
事例1:HANEDA INNOVATION CITY様 PRISM_geographic(TOKYO CREATIVE SALON 2025)
羽田空港近隣の空きテナントを活用し、地球上を行き交うフライトデータの軌跡をプリズムの光の点と線で表現したアート作品の展示イベントです。
床には羽田周辺の世界の空港の位置を元にプリズムを配置し、羽田と世界中の空港を結ぶ航路ネットワークが有機的に浮かび上がります。来場者は管制塔のように照明の角度を任意に操作でき、それによって新たな光の航路を生み出す参加型の体験が設計されています。
本作品は国内最大の空間デザインアワード「日本空間デザイン賞」で銀賞を受賞しました。
事例2:GINZA SIX リテールマネジメント株式会社様 ROOF TOP ORCHESTRA -音を奏でる庭園-
銀座最大の屋上庭園を舞台に、「作曲者がいないオーケストラ」をテーマとして、音と光
とテクノロジーが融合した参加型のサウンド・インスタレーションです。
サカナクション・山口一郎氏が発起人である『NF』がプロデュースし、銀座の夜景を背景に来場者が主役となって音を奏でる体験を作り上げました。
この取り組みは、企画・空間デザインの斬新さが評価され、「日本空間デザイン賞2020」入賞および「NDF2020」奨励賞を受賞しています。
事例3:Spotify Japan株式会社様 Spotify Sessions
事業者・広告会社向けに2日間にわたって実施されたカンファレンスイベントで、参加者が楽しみながらSpotify広告のビジネス活用への理解を深めることを目的としています。
会場各所に、場所のテーマとリンクしたオリジナルプレイリストに繋がるSpotifyコードを忍ばせ、参加者に発見してもらう体験を設計。さらに、アーティストのパフォーマンスや、Spotifyロゴの刻印が入ったフード、Spotifyカラーのオリジナルカクテルを提供するなど、空間全体でSpotifyらしい “Playful” な要素を演出し、サービスへの理解とビジネス活用のきっかけを創出しました。
■まとめ
この記事では、WoW体験について解説してきました。
WoW体験は、単なる一過性の施策ではありません。顧客との関係を深め、単なる「ユーザー」を「ブランドを支えてくれるファン」へと育てていくための、長期的で本質的なアプローチです。
この記事でご紹介したポイントを実践する上で、「自社だけでは何から手をつければいいかわからない」「もっと具体的なアイデアが欲しい」と感じることもあるかもしれません。
私たち博展は、企業のコミュニケーション活動を長年支援してきた経験と実績に基づき、プライベートショーをはじめとするイベントでの「WoW体験」創出を、企画からデザイン、制作・運営までワンストップでサポートします。ぜひ一度お気軽にご相談ください。