2025年、博展はオフィスや商業施設などの常設空間を手がける「商環境事業部」を設立しました。
近年博展では、我々の創業のルーツである展示会や、ビジネスの主流であるイベントプロモーションに加え、企業ショールームやミュージアム、オフィスなど、常設空間のプロデュース案件が増えてきており、このタイミングでの商環境事業部の設立は自然の流れでした。
「体験デザイン」を追求する博展が、常設空間のデザインにどのように取り組んでいくのか。商環境事業部で事業部長を務める齋藤祐太とクリエイティブ局長を務める堀田純希の二人が、今後の意気込みについて語りました。
企業のターニングポイントとなる常設空間のデザイン
-2025年より、博展のあらたな事業部として商環境事業部が立ち上げられました。設立にいたるまでにはどのような背景があったのでしょうか?
齋藤:BtoBおよびBtoCを問わず、様々なクライアントとのビジネスを通じて、徐々に常設空間のプロデュースビジネスの位置付けが変わってきているのを感じていたことが、事業部組織の立ち上げを決意するにいたった背景にあります。企業ショールームやミュージアム、オフィス空間や店舗のデザインといった常設空間の仕事の実績を積み重ねてきたことで、近年はクライアントの事業のターニングポイントとなるような案件にもお声がけいただけるようになってきました。“人と社会のコミュニケーションにココロ通わせ、未来へつなげる原動力をつくる”という博展のパーパスのもと、常設空間をプロデュースすることで高い付加価値を提供し、市場で勝負できているという感覚が芽生えました。

堀田:もともと2013年頃から商環境事業部の前進となる組織として「建装推進室」という部署があり、当初はおもに施工を請け負う部署として活動していたんです。最初は数名だけの組織でしたが、徐々に常設空間のデザインも手がけるようになるにつれて所属メンバーが増えていった経緯があります。今回事業部として再編されるにあたっては、41名のメンバーが所属することになりました。
齋藤:商環境事業部が発足した現在では、博展のパーパスはもちろん、事業部として新たに掲げた”明日の感動を創る”スローガンを大切に日々活動しています。我々が介在し、プロデュースした施設や店舗やオフィスなどで、来場者はもちろん、そこで働く従業員の方々や、その地域がゆたかになり、顧客のビジネスだけにとどまらないポジティブな原動力を生み出していきたいと考えています。

-さきほどのお話にあった、クライアントのターニングポイントとなった常設空間の代表的な事例を教えてください。
齋藤:たとえば、株式会社エイチ・アイ・エス様の新宿にある旗艦店の企画・デザインを手がけたプロジェクトは、企業のターニングポイントに関わることができている実感が得られた仕事だったと思います。新宿が創業の地であるエイチ・アイ・エス様にとって、この旗艦店はもっとも象徴的な店舗で、全国に店舗があるなかでも、お客様とのコミュニケーションにおいて特に重要な拠点として位置付けられていました。エイチ・アイ・エス様とはそれまでに複数のお仕事をご一緒しており、我々博展の仕事に期待していただける関係をつくることができたことが、こういった仕事のご依頼にもつながったんだと思います。
堀田:イベントや展示会などの仮設空間のデザインをルーツに持つ博展は、常設空間の領域においては後発ですが、これまでの事業を通して様々な空間のデザインにチャレンジしてきました。そんな我々の考え方や感性に共感していただいたクライアントから、指名いただくことが増えてきているんです。地道に一歩ずつステップを踏んできたことで、徐々に常設空間の仕事を評価していただけるようになってきた感覚がありますね。
過去のエイチ・アイ・エス様とのお仕事例

「いま」を掴んだ空間を提案する、後発だからこその視点
-クリエイティブの面ではどのような点がクライアントに評価されていると感じていますか?
堀田:我々は当然ながら、社内に「こうすべき」といった前例を持っていません。だからこそ、「いま」を捉えるために様々なジャンルのクリエイションからヒントを探し、プロジェクトと真摯に向き合い、いま自分たちが欲しい場所、本当にいいと思える場所を提案してきました。枠にとらわれない横断型の感覚こそが、クライアントや一緒にプロジェクトを進めるパートナーの方々に抱かれる新鮮さや共感につながっているのかも知れません。
たとえば先ほどのエイチ・アイ・エス様のコンセプト型ショップ、たまプラーザ店のプロデュースでは、お客様に旅行体験を提供する新しいコミュニケーションや店舗のあり方を考えています。お客様にパンフレットをご覧いただきながらカウンターで接客する、従来の旅行会社の空間では、こういったアンティーク家具が並ぶような空間を提案することはまずなかったと思うのですが、ファミリー層のお客様が多い立地の特性を活かし、旅関連の書籍や絵本に触れることができるコミュニティ空間として、こういったチャレンジをすることができました。
「いままで」の参考から積み上げるのではなく「これから」を提案したいという意識から、ここだけにしかないものをつくりましょうと提案することが多いです。結果的に、マテリアルや家具などのセレクトなどにおいても従来の考え方やセオリーとは異なるスタイリングになっていることも多いと思うので、今後もそういったデザイン面でのキャラクターを出していければと考えています。
ー常設空間のデザインに取り組む上で、クライアントから何を求められていると感じますか?
堀田:クライアントは常に顧客との新しい接点を探しているので、ビジネスの変化に合わせた新しい提案をしていくためには、時代の中で生まれている新しい価値観に敏感でいなければならないと思っています。メーカーのプレゼンテーションの場としてショールームが求められていた時代から、オープンイノベーションを目的とした共創スペースへの注目が高まったように、ビジネスにおける常設空間の流行は3年から5年ぐらいのスパンでゆるやかに変わっていくのを感じています。


常設空間における「再訪性」
-博展では「体験デザイン」をキーワードにプロジェクトに取り組んでいますが、仮設空間と常設空間の大きな違いはどこにあると思いますか?
齋藤:残り続ける空間をつくる点では大きな違いがありますが、われわれが重視している体験デザインの考え方においては、基本的には同じだと思っています。
我々が体験デザインを考える時、あくまで空間はユーザーやお客様とのタッチポイントのひとつであり、空間の中で生まれるリアクションだけにフォーカスしているわけではないんです。たとえば、さきほどのエイチ・アイ・エス様の企画・デザインの場合、僕らがデザインしなければならない「体験」とは、旅行会社の空間はもちろん、お客様がそこで受ける接客の時間や、これからの旅に思いを馳せる時間、渡航中の時間、誰かと一緒に過ごす旅の時間など、一連のすべての時間を含めたものだと捉えています。我々にとってのいい仕事とは、その場で生まれたコミュニケーションや経験を通して、訪れた人の中にポジティブな反応が起こり、豊かな体験として持ち帰っていただけるような空間をデザインすることなのではないかと考えています。それは訪れる方々だけではなく、そこで働く方々にとっても同様だと考えます。
堀田:クリエイティブの面での大きな違いを挙げるとすれば、イベント空間の多くは「ハレ」の場。たとえば空間に配置するものについて考える時に、毎日訪れる使い手の視点や、当然ながら数年後の未来を取り入れる必要はかならずしもありません。訪れたユーザーがその空間で何をして過ごすのかを考え、それらを描いたこの場限りの一枚の絵を空間に拡張することが、イベント空間のデザインに求められることの本質だと思います。

一方で、常設空間のデザインの場合、その場所に何度も訪れる方がいるという「再訪性」や長時間過ごすことが前提にあるため、家具一つの機能が空間体験に大きく影響します。空間に配置される家具や素材を選択するために、来訪者の視点に深く入っていき、「また来たい」「また使いたい」と思える使い勝手や居心地について考えた空間を提案していきます。仮説空間とはつくりあげる要素が大きく異なるため、空間の「ムード」といったものも全く異なります。このあたりは仮設空間の仕事との大きな違いだと思います。
コミュニケーションのコアとなる多目的ルームは、リアルイベントやオンラインセミナーといった用途を想定した、可変式プラットフォーム型のスペースとなっている。
詳細はこちら>>

「明日の感動を創る」商環境事業部としての挑戦
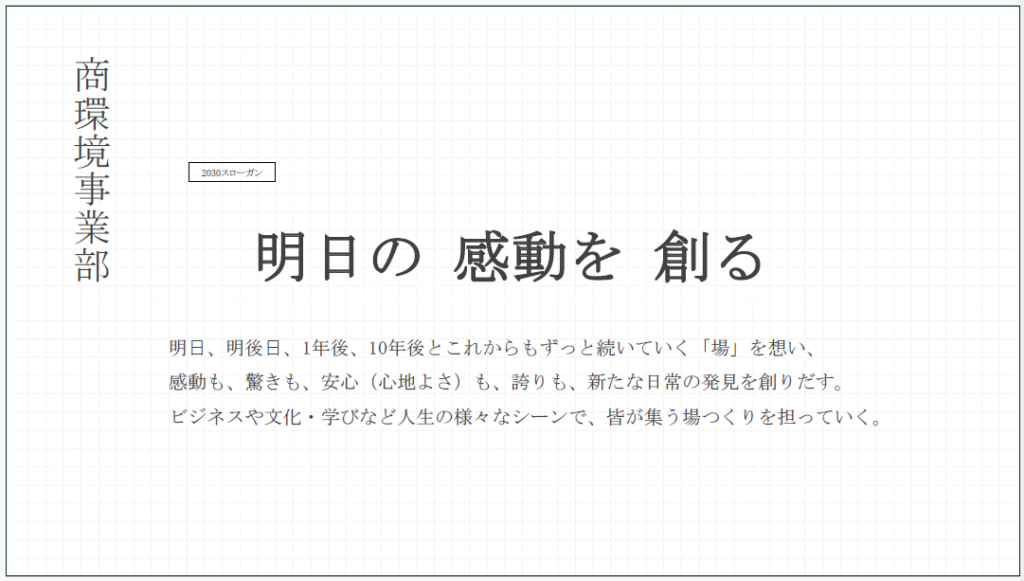
-事業部の立ち上げにあたり、これから博展が仮設空間と常設空間のどちらにも挑戦するからこそ生まれる強みはなんだと思いますか?
堀田:仮設空間のスピード感と、ある意味での「ラフさ」に加え、常設空間のムード、機能性、UX(ユーザーエクスペリエンス)を両立したデザイン感覚を身につけることができれば、後発というポジションでも十分勝負していけるのではないかと思います。まだまだわれわれも勉強中ですが、イベント空間をルーツに持つ会社の中にそういった肌感覚を持つメンバーの数が増えれば、会社の空気も変わってくるのではないかと思いますね。ここ数年でもその変化は感じていますし、何より自身のつくり上げた空間をユーザーが体験している情景を見ることに、喜びを感じるクリエイターは多いはずです。
齋藤:商環境事業部の制作部長が、博展のサステナビリティ推進部の事業部長を兼務しているため、今後は「空間へのサステナビリティ実装」を博展のオリジナリティとして伸ばしていきたいと考えています。同時に、博展にはデジタルコンテンツの企画から実装までできるコンテンツデザイン局チームがあります。彼らは辰己の共創空間「T -BASE」で日々実証検証をおこなっているので、今後はさらに常設空間のデザインとの相乗効果を生むための取り組みを実践していきたいですね。体験デザインはデジタルとの相性がいいですし、社内にこういったチームがいる企業は業界では稀有な存在なので、一つの強み・武器にしていきたいと思います。
-最後に、あらためてこれからの商環境事業部の活動にかける思いをお聞かせください。
堀田:商環境事業部の立ち上げにあたり、僕らは「明日の感動を創る」をスローガンに掲げました。再訪性のある常設空間のデザインは、訪れる方々にとっての「明日」をつくる仕事でもあるので、常にこの言葉について考えながら新しい価値を生み出せる場所をつくっていきたいと思っています。
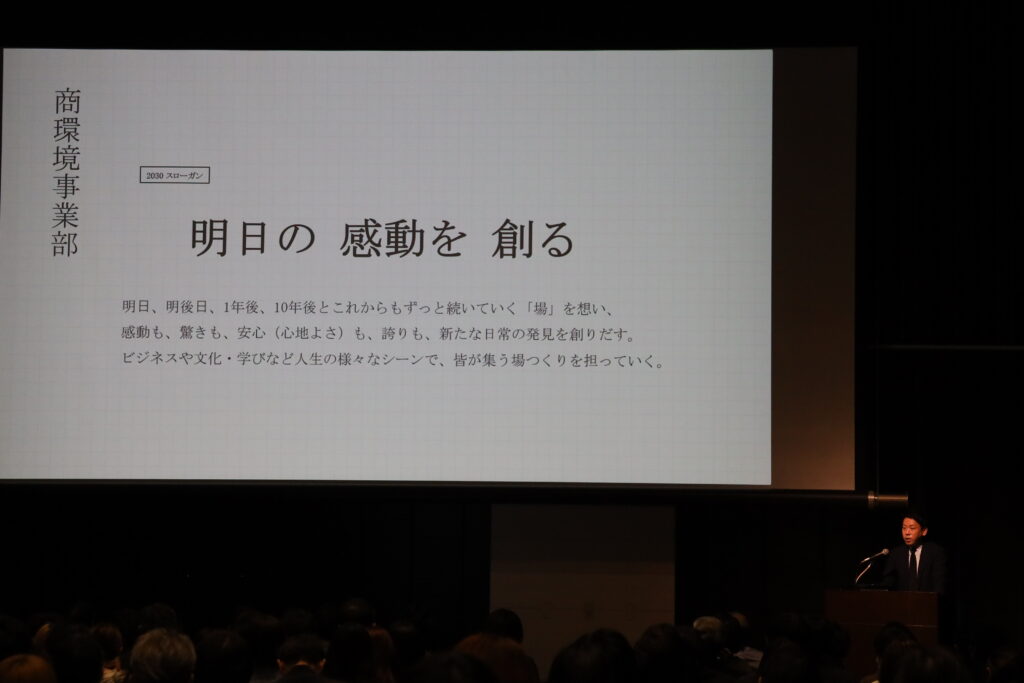
ちなみに、このスローガンに行き着くまでに、これまで常設空間の仕事に関わってきたメンバーにヒアリングを実施したんですね。たとえば部門の立ち上げ当初、商業施設の看板を制作する仕事で、取り付けた瞬間にテンションが上がっているアルバイトスタッフの姿が印象的だった話や、完成したばかりの空間を汚したくなくて、思わず靴を脱いでしまったというクライアントの声、30年以上働いた店舗のリニューアルを感慨深く見守っている方の姿に、思わずもらい泣きしてしまったスタッフのエピソードなど、仕事を通して見ることができた様々な情景について聞くことができました。僕らの仕事にとって、こうした情景をちゃんと覚えていくことが大切なのではないかと思います。その空間を使う人たちのためにどんな提案ができるだろうと考える感覚を大切にしながら、現状に留まることなくしっかりと「これから」を提案し、次の仕事につなげていきたいと思います。
齋藤:さきほどお話ししたエイチ・アイ・エス様の店舗でも、スタッフの方々が日々ポジティブな気持ちで働くことができているという声をいただいています。商環境事業部は、スローガンと合わせて「施設と企業の特性をクリエイティブの力で磨き上げ、顧客の事業活動の原動力を生み出すこと」を事業部方針として掲げているので、ステークホルダーの方々の日々を豊かにできる空間をつくると同時に、クライアントの事業の原動力となる仕事に挑戦していきたいと考えています。

<Credit>
Editor/Writer| 堀合 俊博
Editor | 渡邉 怜楠、浅井 亜紀子










