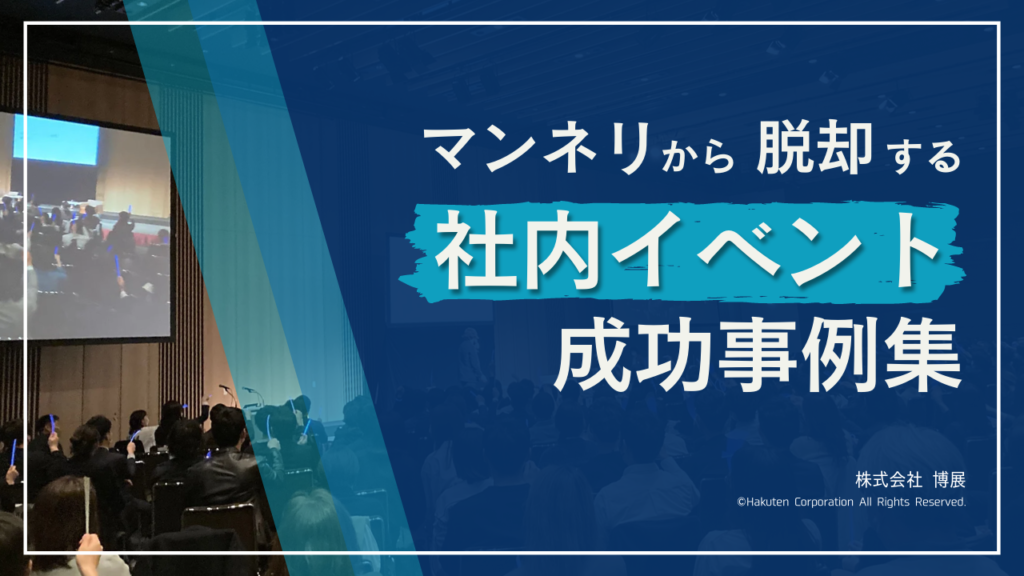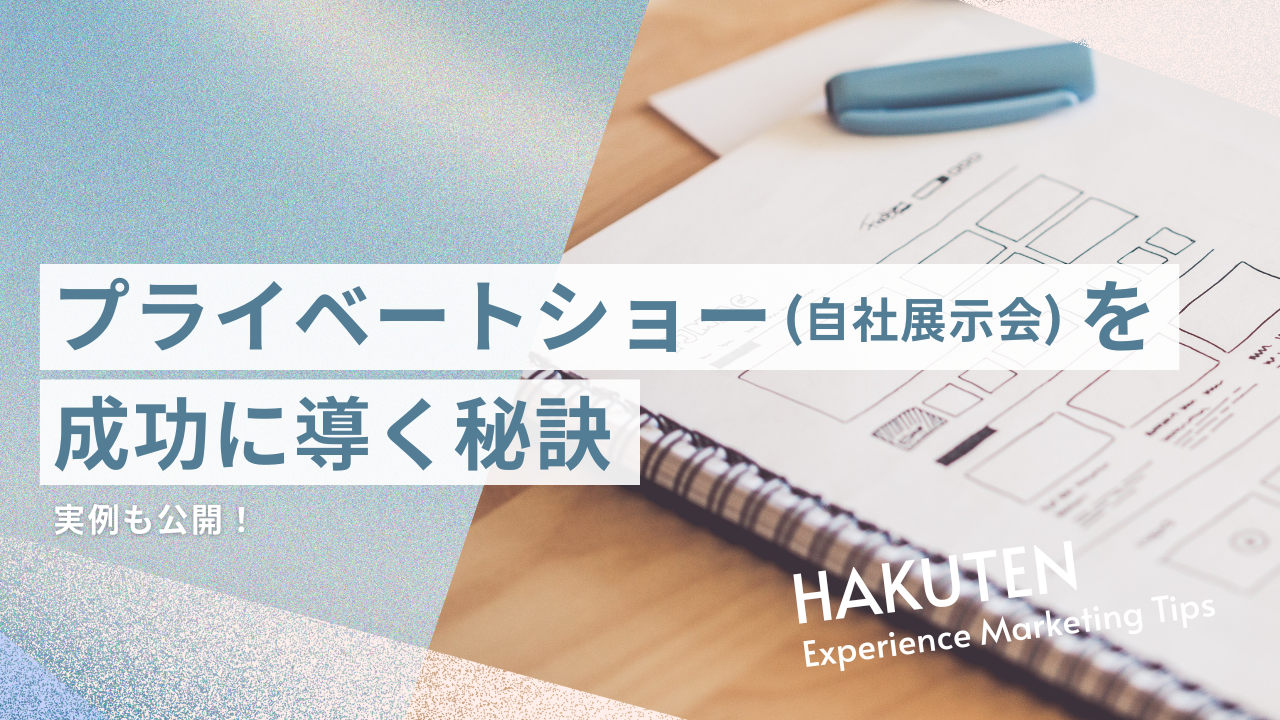社員総会やキックオフなど、多くの企業が毎年「社内イベント」を実施しています。その目的は、全社方針やビジョンの共有、社員表彰などを通じて会社の事業を前に進めることにあるでしょう。
しかし、イベントが無事に終了する一方で、「当初の目的はどれだけ達成されているのか?」という課題を感じている企業も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、博展が行った社内イベントに関するアンケート調査をもとに、その実態を読み解きながら、イベントを成功に導くためのポイントを解説します。
Index
■社内イベントとその効果に関する調査について
■調査で明らかになった「社内イベント成功の4つのポイント」
■社内イベントのジャンル別分析の結果
■社内イベントのコンテンツ別調査の結果
■社内イベントの企業規模別調査結果
■社内イベント後の継続したフォローの必要性
■社内イベントの事例
■まとめ
■社内イベントとその効果に関する調査について
社内イベントとは
社内イベントとは、社内へのビジョンや方針の共有を目的として、定期的に開催されるものです。具体的には、キックオフや社員総会のように、全社の方針発表や社内交流のために多くの社員が参加するイベントを指し、一体感の醸成やモチベーション向上、コミュニケーションの活性化などの効果が期待されます。
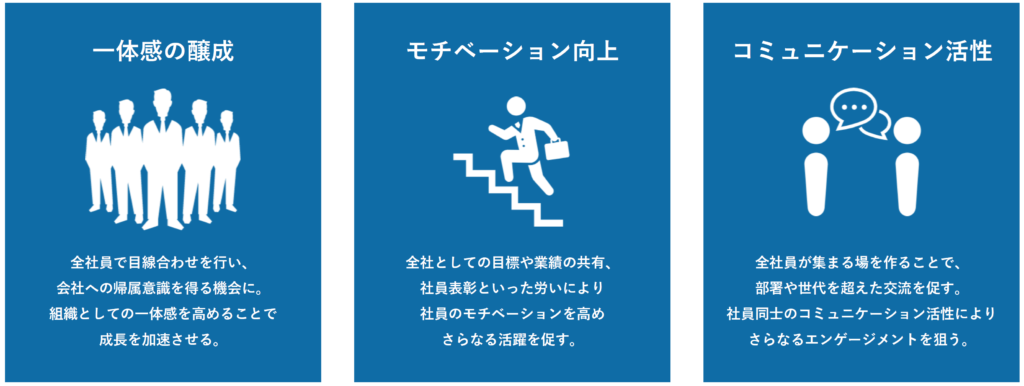
調査概要と方法
今回行った調査は、社内イベントの実態を把握し、参加した社員の満足度や心理・行動、そして社内にもたらす変化への影響を明らかにすることで、より効果的なイベントの実施方法を考察することを目的としています。
調査は2023年3月にWebアンケート形式で実施されました。本調査における「社内イベント」とは、キックオフや社員総会など、全社の方針発表や社内交流を目的に定期的に開催されるものを指し、朝礼や社員旅行などは含まれません。
主な調査内容は以下の通りです。
・社内イベントで実施されたプログラム
・社内イベント実施後の継続的なフォローの場の有無
・社内イベントへの参加方法(オンライン/リアル)
・心理変容(方針への共感/帰属意識/社員同士の交流/モチベーション)
・行動変容(方針の記憶/実務への反映/コミュニケーション量/帰属意識/社員同士の交流/モチベーション)
・社内変化(社員間で意見交換、業務への反映/コミュニケーション量/帰属意識/モチベーション)
・イベントの総合満足度
■調査で明らかになった「社内イベント成功の4つのポイント」
今回の調査結果から、社内イベントをより効果的にし、成功に導くための4つの重要なポイントが明らかになりました。
リアル参加の方が満足度が高い
まず、イベントへの参加方法が満足度に大きく影響することが分かりました。
調査では、イベント会場で直接参加した「リアル参加」が56.6%でした 。そして、オンライン参加者と比較して、このリアル参加者の方がオンライン参加者よりイベントへの満足度が高い傾向にあります 。
フォロー施策が効果を高める
イベントを一過性のものにせず、その後のフォローアップがいかに重要かも示されています。回答者の約65%が、イベント終了後に内容を継続して共有する機会があったと回答しました。このようなフォロー施策が「実施済み」または「予定あり」のグループは、「実施しない」グループに比べ、「社内でビジョンや方針について意見交換する機会が増えた」と回答する割合が多いという結果が出ています。
双方向コンテンツで満足度アップ
イベントの内容も満足度を左右する重要な要素です。特に、「社員同士のワークショップ」や「社員表彰」、「飲食を伴う社内交流」といった、参加者が受け身になるだけでなく、双方向のコミュニケーションが生まれるコンテンツが含まれている場合、それらがなかったイベントに比べて満足度が高くなる傾向が見られました。
若手社員ほど満足度が高く、社内コミュニケーションも増える
世代別に見ると、若手社員の方が社内イベントへの満足度が高い傾向にあります。また、イベント後の社内変化についても、若手社員は「他の社員とのコミュニケーションが増えた」と回答した割合が他の世代より高く、特にコミュニケーションの活性化という面で高い効果を感じていることが分かりました。
■社内イベントのジャンル別分析の結果
世代別分析
ここでは、回答者を「若手社員(25-34歳)」「中堅社員(35-49歳)」「ベテラン社員(50-59歳)」の3つの世代に分けて分析します。
世代別の分析結果から、以下のことが分かりました。
イベントの総合満足度は、若手社員が最も高く、年齢が上がるにつれて低下する傾向が見られました。
一方で、イベント後の心理的な変化を見ると、「中長期ビジョンや方針に共感できた」と肯定的に回答した割合は、ベテラン社員が45.8%と最も高くなっています。これに対し、「社員同士の親交が深まった」と肯定的に回答した割合は、若手社員が最も高く、他の世代との差が見られました。
この結果から、社内イベントは若手社員にとっては社内交流の促進という面で、ベテラン社員にとっては会社方針への理解・共感という面で、それぞれ異なる効果をもたらしている可能性が示唆されます。
参加方法別分析
ここでは、イベントへの参加方法を「イベント会場に行って参加した(リアル)」と「オンラインで参加した」の2つに分けて分析します。調査では、リアル参加が56.6%、オンライン参加が43.2%でした。
イベントの総合満足度では、リアル参加の方がオンライン参加よりも高いことが分かりました。
実施されるコンテンツにも違いが見られます。オンラインでは「業績や方針の共有」といったプレゼン形式のコンテンツが中心になる一方、リアルでは「ワークショップ」や「社員表彰」、「社内交流」といった双方向のコンテンツが多くなる傾向がありました。
参加方法による最も大きな差は、コミュニケーションに関する項目に表れました。
心理変容:「社員同士の親交が深まった」と肯定的に回答した割合は、リアル参加が46.3%だったのに対し、オンライン参加は27.3%に留まりました。
行動変容:「他の社員とのコミュニケーションが増えた」という項目でも、リアル参加の45.2%に対し、オンライン参加は24.5%と大きな差が出ています。
社内変化:「中長期ビジョンや方針について社員間で意見交換する機会が増えた」「仕事以外でのコミュニケーションが増えている印象を受ける」という2項目では、リアルとオンラインで肯定的な回答の割合に20%以上の差が開きました。
これらの結果から、リアル参加はオンライン参加に比べて、社員同士のコミュニケーションを活性化させる効果が非常に高いことが示されています。実際に、心理・行動・社内変化のほぼ全ての設問において、リアル参加の方がオンライン参加よりも肯定的な回答の割合が高い結果となりました 。
■社内イベントのコンテンツ別調査の結果
ここでは、社内イベントで実施されたコンテンツの有無が、参加者の満足度にどのような影響を与えたかを分析します。また、この調査結果から、社内イベントにはどんなコンテンツが必要かを考えていきます。
調査では、最も多く実施されたコンテンツは「プレゼン形式での業績や中長期経営計画の共有」(66%)でした 。次いで、「社員同士のワークショップ」や「社員表彰」、「飲食を伴う社内交流のパート」がそれぞれ3割前後で続きました。
これらのコンテンツの有無と満足度の関係を見ると、「業績や経営計画の共有」の有無では、満足度に大きな差は見られませんでした 。しかし、その他の項目では顕著な差が現れました。
特に、「社員のワークショップ」と「社員表彰」が実施されたグループは、実施されなかったグループに比べて満足度が大きく向上する結果となっています。このことから、業績共有のような一方向の情報伝達だけでなく、社員が参加したり、主役になったりする双方向のコンテンツが、イベント全体の満足度を高める上で非常に重要であると言えます。
社内イベントにはどんなコンテンツが必要か
この調査結果から、特に参加者の心理や行動に良い影響を与え、満足度向上に貢献する3つのコンテンツ、「社員同士のワークショップ」「社員表彰」「飲食を伴う社内交流」について、その効果を解説します。
社員同士のワークショップ:ワークショップは方針の自分ごと化を促し、社員間のコミュニケーションを活性化させる上で非常に効果的なコンテンツであると言えます。
社員表彰:表彰によって、社員の活躍を称える場を設けることが、個人のモチベーションを高め、組織の一員であるという意識を強める上で重要な役割を果たします。
飲食を伴う社内交流:飲食を伴うリラックスした雰囲気での交流は、部門や役職を超えた横のつながりを生み出す上で不可欠な要素です。
■社内イベントの企業規模別調査結果
ここでは、回答者が所属する企業の従業員数別に、実施されたコンテンツとイベントの満足度を分析します。
実施コンテンツの傾向
企業規模によって、実施されるコンテンツにいくつかの違いが見られました。特に、従業員数500人〜999人の企業では、他の規模の企業に比べて「社員同士のワークショップ」の実施率が低い結果となりました 。また、5,000人〜9,999人規模の企業では、「飲食を伴う社内交流パート」の実施率が高い傾向にありました。
満足度の傾向
イベントの総合満足度を見ると、1,000人以上の規模の企業グループ間では大きな差は見られませんでした 。しかし、500人〜999人の企業グループにおいては、他の規模のグループと比較して満足度が低い傾向にあることが分かりました。
■社内イベント後の継続したフォローの必要性
社内イベントを一過性のものにせず、その効果を最大限に高めるためには、イベント後の継続的なフォローアップが不可欠です。
調査では、イベント後に内容をフォローする取り組みが「継続して共有される機会があった」と回答した人は65.8%、「まだ行われていないが、今後共有される機会が予定されている」と回答した人は15.6%で、合計で8割以上がフォロー施策を実施または予定していることが分かりました。
実際にフォロー施策を「実施済み」のグループは、「予定あり」や「なし」のグループと比較して、イベント後の心理・行動・社内変化の全ての項目において、肯定的な回答をする割合が高い傾向にありました。
特に、以下の項目でその差が顕著に現れています。
心理の変化: フォロー実施済みのグループは、「ビジョンや方針へ共感した」「自社への帰属意識が高まった」と回答した割合が特に高くなりました。
行動の変化: イベントで共有された内容が実務に反映されているかという点で、フォローの有無が大きく影響しました。「方針が実務にいきてきる」「自社への帰属意識を持って業務に取り組んでいる」といった項目で大きな差が見られます。
社内の変化: 会社全体への影響として、「共有された方針が個々の業務に活きている」「社内全体がイベント直後のモチベーションを保っている」の2項目で、フォロー実施済みのグループが他のグループを大きく上回りました。
ビジョンや目標を共有し、全社で同じ方向を向くための社内イベントですが、単発開催だけでは、理解することはできても共感して実践に移すところまで到達しません。継続的な発信の場を設けることで、社員の実務レベルまで落とし込むことが重要です。
社内イベントを単発イベントではなく継続的な事業として捉える必要があるといえるでしょう。
■社内イベントの事例
これまでに解説した成功のポイントが、実際のイベントでどのように活かされているのか、具体的な事例を見ていきましょう。
事例:博展「57th HAKUTEN KICK OFF」
イベント概要
博展が2025年1月に開催した、期のスタートを切るための全社員参加型キックオフイベントです。イベントは丸一日かけて行われ、第一部では昨期の優れた実績を表彰する「HAKUTEN AWARD」と経営方針の共有、第二部では立食形式の「懇親会」という二部構成で実施されました。
「表彰」と「方針共有」を組み合わせたプログラム
第一部では、永年勤続やMVP、優れたプロジェクトなどを称える表彰式(HAKUTEN AWARD)が行われました。これは調査結果でも満足度向上に繋がるとされた「社員表彰」にあたります。社員が主役になる時間と、経営陣からの方針共有という真剣な時間を組み合わせることで、参加者のモチベーションと会社への共感を両立させています。
コミュニケーションを活性化させる双方向の「懇親会」
第二部の懇親会は、部署や役職が異なる社員同士が交流できるよう、ランダムなテーブル分けが工夫されていました。また、チーム対抗のクイズ大会や社員によるパフォーマンスなど、参加者全員が楽しめる双方向のコンテンツが企画されており、活発なコミュニケーションを生み出す仕掛けが施されています。これは、調査で明らかになった「飲食を伴う社内交流」の効果を最大化する取り組みと言えます。
企業の価値観を体現するサステナブルな取り組み
表彰式で授与されたトロフィーは、事業活動で発生した鉄板の端材や廃棄予定のカーペットを再利用して制作されました。イベントの備品一つひとつにまで企業のサステナビリティへの姿勢を反映させることで、参加者は自社の価値観を再認識する機会となります。
イベントの成果と考察
イベントレポートでは、参加した若手社員から「挑戦的で優れたプロジェクトと真摯に取り組む先輩たちのことを学べた」「今後の博展の強みを真剣に考える場となった」「博展社員全員で楽しむことができた」といった声が上がっており、学習、方針理解、一体感の醸成という複数の目的が達成されていることが伺えます。
単に情報を共有するだけでなく、表彰や交流といった体験を通じて社員のエンゲージメントを高め、組織全体で同じ方向を向くきっかけを創出した好事例と言えるでしょう。
■まとめ
本記事では、調査データに基づき、社内イベントを成功させるための秘訣を解説しました。成功する社内イベントは、単なる情報伝達の場ではなく、社員のエンゲージメントを高め、組織を活性化させるための戦略的な機会です。
調査結果から見えてきた特に重要なポイントは以下の通りです。
・リアルの場で体験を共有することで交流を活性化
・部署や役職を超えて双方向型のコミュニケーションを
・単発イベントではなく継続的な事業として捉える
これらの要素を意識することで、形骸化しがちなイベントを、社員一人ひとりの心に響く「体験」へと昇華させ、会社全体の一体感を醸成することができるでしょう。
貴社の社内イベントを成功に導くために、
「もっと効果的な社内イベントを企画したいが、何から手をつければ良いか分からない」
「マンネリを脱し、社員の記憶に残るイベントにしたい」とお考えでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
博展では、本記事で紹介したような調査データと豊富な実績に基づき、貴社の課題解決に繋がる社内イベントを戦略の策定から企画・実行まで一貫してサポートします。
また、今回の調査結果を分かりやすくまとめた資料を公開しています。博展だけでなく、他企業の社内イベント事例も複数掲載していますので、下記よりぜひダウンロードしてみてください。