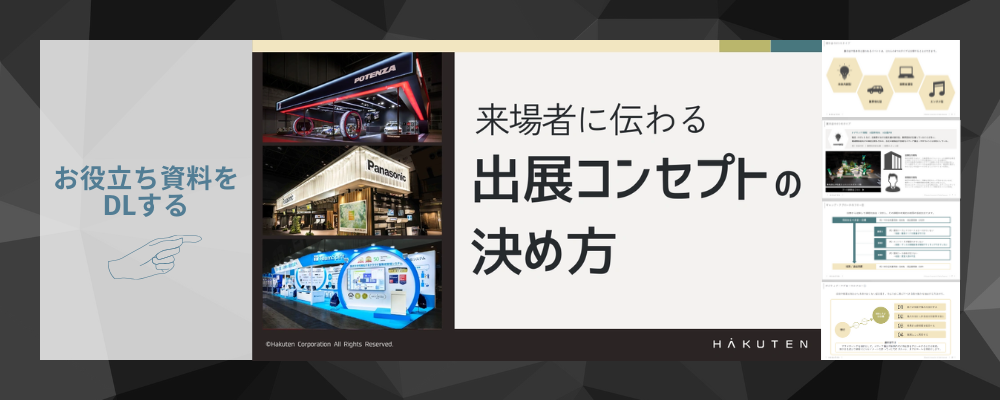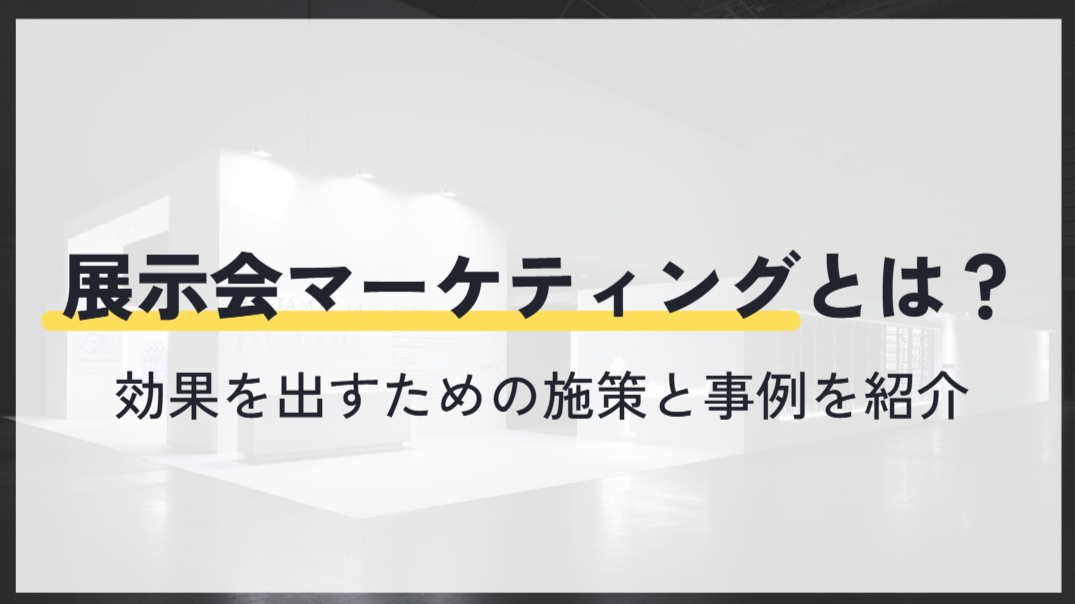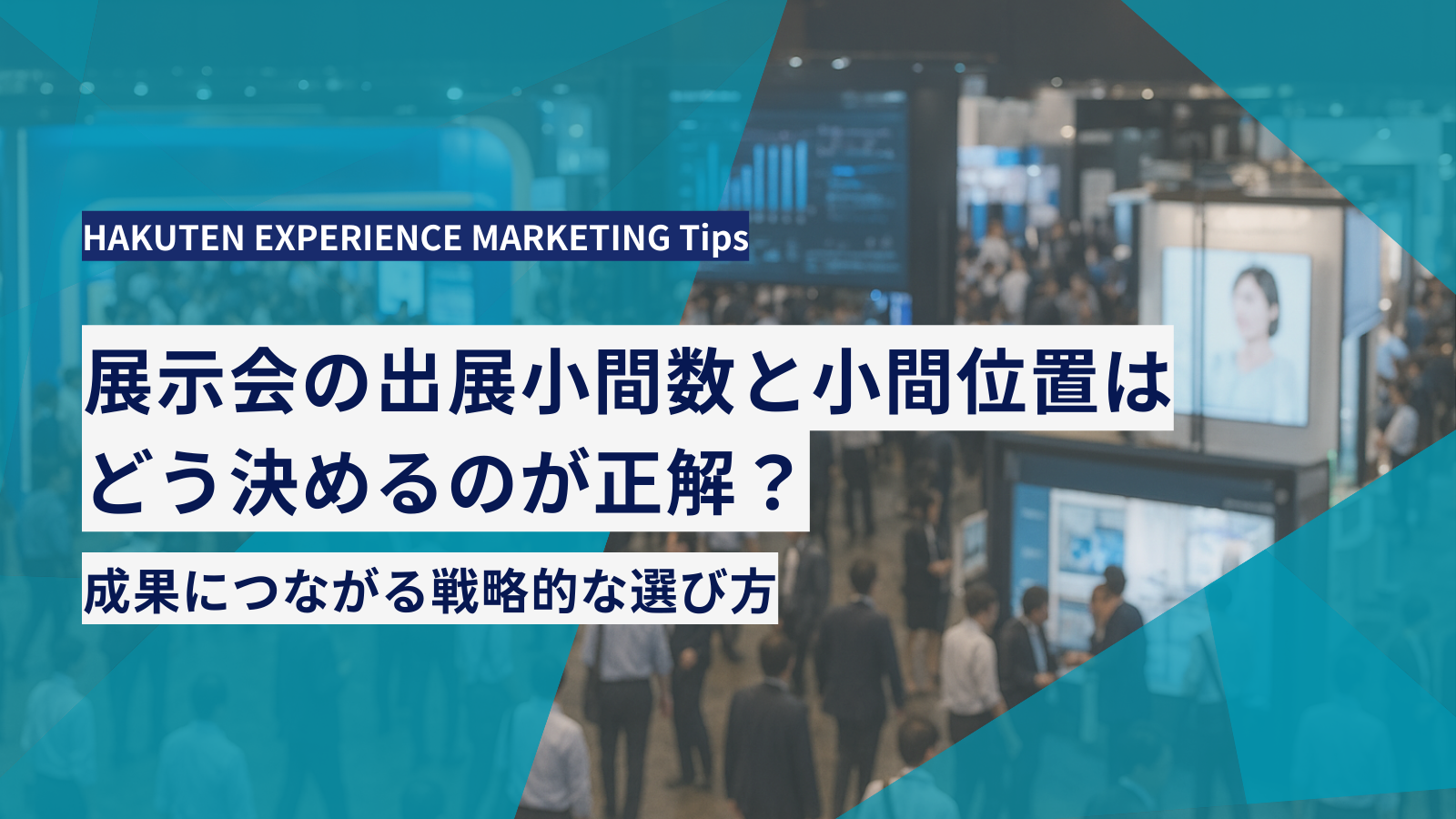「展示会に出展したけれど、思ったほど効果がなかった」「高い費用をかけて出展する意味があるのか疑問」といった声をよく耳にします。しかし、適切な戦略と準備があれば、展示会は新規顧客開拓や認知度向上において非常に効果的な手段となります。
本記事では、展示会への出展によって実際に得られる効果と、その成果を最大化するための具体的な方法について詳しく解説します。
Index
■展示会への出展で得られる主な効果
■「展示会は意味がない」と言われる理由
■展示会の種類と来場者特性の理解
■展示会の成果を最大化するための具体的戦略
■効果測定と継続的改善のためのKPI設定
■まとめ
■展示会への出展で得られる主な効果
展示会への出展は、BtoBビジネスにおいて多岐にわたる効果をもたらします。単純な商品紹介の場ではなく、企業のマーケティング戦略において重要な役割を果たす施策です。
新規顧客獲得における効果
展示会への出展は、特定のテーマに関心を持つ見込み顧客が多数来場するため、短期間で効率的に新規リードとの接点を創出できます。一般的な営業活動では1日に訪問できる顧客数は限られていますが、展示会では数百から数千の来場者と直接接触する機会があります。
獲得できる名刺の枚数は、もちろんブースの規模や位置、企画内容によって大きく変動しますが、1つの目安として、中規模の展示会(来場者数2万人程度)では、1社あたり平均200~300件の名刺交換が可能とされています。このうち、有効なリードとして活用できるのは約30~50%程度で、最終的に商談に発展する割合は10~20%というデータがあります。
既存の顧客との関係強化の効果
展示会は新規顧客獲得だけでなく、既存顧客との関係深化にも大きな効果があります。既存顧客を招待し、新製品やサービスを直接紹介することで、普段の商談以上に深い理解を促進できます。また、検討段階にある顧客の背中を押す「クロージングの場」としても極めて有効です。商談中の顧客を会場に招き、製品に直接触れてもらうことで導入への最終的な懸念を払拭し、契約へと導く強力な一手となり得ます。
展示会という特別な場での接触は、顧客との信頼関係を強化し、優良顧客化やリピート促進につながる重要な機会となります。実際に、展示会での既存の顧客との接触後、取引量が20~30%増加したという企業もいます。
販売促進における直接的な効果
展示会では、製品やサービスを来場者に直接見せ、触れてもらうことで、オンラインでは伝えきれない魅力を訴求できます。特に、複雑な製品や技術的な説明が必要なBtoB商材では、この直接的な体験が購買意欲を大きく左右します。
展示会場でのデモンストレーションや実機体験は、顧客の理解度を飛躍的に向上させ、その場で具体的な商談やアポイントメントにつながる可能性が高まります。実際に、展示会でのデモ体験後の商談成約率は、通常の営業活動と比較して2~3倍高くなったという企業もありました。
認知度の向上とブランディング効果
展示会への出展による認知度の向上効果は、単純な広告宣伝とは異なる特徴があります。数千から数万人規模の来場者に対し、社名やブランドを効果的に露出し、業界内での知名度と存在感を向上させることができます。
特に、業界の関係者が集まる専門展示会では、競合他社の動向を把握しながら自社の位置づけを明確にできます。また、メディアの注目度も高く、プレスリリースやメディア露出の機会も増加します。
市場調査・テストマーケティングの場としての効果
展示会は、開発中の新製品や新サービスを市場投入前に披露し、ターゲット層から直接的なフィードバックを得る絶好の機会となります。来場者のリアルな反応や意見は、製品の改善、価格設定、マーケティング戦略の策定において非常に価値のあるデータとなります。
アンケートやヒアリングを実施することで、定量・定性の両面から市場のニーズを把握し、事業リスクを低減させる効果が期待できます。
■展示会は効果がないと言われる理由
一方で、展示会への出展に否定的な意見も少なくありません。その背景には、適切な戦略や準備不足による失敗事例が多いことが挙げられます。ここでは、よくある失敗パターンとその対策について詳しく説明します。
目的が不明確な出展による失敗
多くの企業が陥りがちな失敗として、「とりあえず出展してみる」という目的不明確な参加があります。新規リード獲得、ブランディング、既存顧客との関係強化など、複数の目的を同時に追求しようとして、結果的にどの目的も達成できないという結末に陥りがちです。
展示会への出展においては、最も優先する目的を一つに絞り、その目的に最適化した戦略を立てることが成功の鍵となります。目的が明確になることで、出展する展示会の選定、ブースのコンセプト、スタッフの配置、KPIの設定まで、一貫した戦略を構築できます。
目的設定で変わるアプローチの具体例
出展の主目的を一つに絞ることで、ブースの設計から当日の運営まで、すべての施策に一貫性が生まれます。ここでは、代表的な目的を例に、具体的な展開を見ていきましょう。
主目的:新規リード獲得数
- ブース設計: 一度に多くの来場者の注目を集められるよう、ミニセミナー用のステージや大型モニターを設置。通路からブース奥まで見通せる、開放的なレイアウトにする。
- 運営手法: 通路の来場者に積極的に声をかける呼び込みスタッフを多めに配置し、ブース内へ人の流れを絶やさないようにする。
主目的:質の高い商談の創出
- ブース設計: 落ち着いて製品デモや説明ができるよう、半個室の商談スペースやデモコーナーを十分に確保する。通路からのアクセスは確保しつつも、周囲の騒音を気にせず会話できる環境を重視する。
- 運営手法: 一人ひとりの来場者に時間をかけられるよう、製品知識の豊富な説明員を配置。その場で具体的な課題をヒアリングし、解決策を提示できる質の高い対話を重視する。
準備不足による集客力の低下
展示会当日の集客だけに頼った出展は、期待した効果を得られない主要な原因の一つです。特に、大規模な展示会では数百の企業が出展するため、事前の告知活動が不足していたり、ブースのデザインやレイアウト設計そのものが魅力的でなかったりといった「準備不足」の状態では、数百の企業が出展する会場でブースへの来場者数を確保することは困難です。
効果的な事前の集客施策として、SNSを活用した出展情報の発信、既存の顧客や見込み客リストに対するメールマーケティング、自社サイトでの告知などが重要です。これらの施策により、展示会での認知度を事前に高め、当日の集客力を向上させることができます。
フォローアップ体制の不備
展示会で獲得したリードに対する適切なフォローアップがなされていないケースも多く見られます。BtoBの商談展における来場者の約75%は、具体的な購入目的ではなく「情報収集」の段階にあるため、展示会後の継続的なアプローチが極めて重要です。
展示会終了後48時間以内のお礼メール送付、リードのランク分けとそれに応じたフォロー戦略の実行が、展示会効果を最大化する決定的な要因となります。多くの企業がこの重要な段階を軽視しているため、せっかくの投資が無駄になっているのが現状です。
■展示会の種類と来場者特性の理解による効果向上
効果的な展示会戦略を立てるためには、展示会の種類と来場者の特性を正しく理解することが不可欠です。それぞれの特徴に応じた最適なアプローチを選択することで、投資対効果を大幅に向上させることができます。
BtoB商談展の特徴
BtoB商談展は、企業間の取引を目的とした展示会で、来場者の多くはビジネス関係者です。主な目的は情報収集、市場調査、新規パートナー開拓であり、決裁権を持つ担当者の来場率が高いことが特徴です。
近年、コロナ禍以降の傾向として、目的意識の低い来場者が減少し、解決すべき課題や予算を持つ決裁権者の来場割合が増加しています。これにより、来場者数は以前より少なくても、リードの質は向上しており、一回の商談の価値が高まっています。
パブリックショーと専門展(BtoB展示会)の違い
パブリックショーは一般消費者を対象とし、製品のプロモーションやその場での販売を主な目的とします。東京ゲームショウやジャパンモビリティーショー(旧名:東京モーターショー)などがこれに該当し、幅広い認知度の向上には効果的ですが、BtoB商材の場合は直接的な商談機会は限定的です。
一方、専門展は特定の業界や技術分野に特化した展示会で、ターゲットが明確に絞られています。来場者数は少なくても、自社の商材に関心の高い見込み客との接点を効率的に創出できるため、BtoB企業にとって非常に有効です。
■意味のある展示会にするために決めておくべきこと
振り返ってみた時に意味のある展示会にするためには、事前準備から事後フォローまでの一貫した戦略設計が必要です。ここでは、実際に成果を上げている企業が実践している具体的な手法について詳しく解説します。
高い効果が期待できる展示会を選ぶ方法
自社のターゲット層と合致するテーマの展示会を選ぶことが、効率的なリード獲得の鍵となります。幅広い層にアプローチしたい場合は大規模な合同展示会、ニッチな層を狙う場合は専門展が適しています。
展示会選定の際は、過去の来場者データや出展企業の業界分布を詳細に分析し、自社のターゲット設定と照らし合わせることが重要です。また、競合他社の出展状況も調査し、自社の差別化ポイントを明確にできる展示会を選択することで、より効果的な成果を期待できます。
効果的なブースデザインと体験型コンテンツ
ブースデザインは来場者の注意を引く重要な要素です。単純な製品展示だけでなく、体験型コンテンツや実機デモンストレーションを組み込むことで、来場者の関心を高め、記憶に残る印象を与えることができます。
また、専門スタッフによる技術説明や来場者からの疑問に答える個別相談の時間を設けることで、来場者との深いコミュニケーションを実現できます。
スタッフの教育と当日オペレーション
展示会当日のスタッフ対応は、獲得するリードの質を大きく左右します。ブースへの呼び込み、名刺交換、アポイント獲得までの一連の流れを具体的に設計し、スタッフ全員で共有することが重要です。
スタッフには、来場者の課題やニーズを短時間で的確に把握し、適切な提案につなげるスキルが求められます。事前のロールプレイングや、よくある質問への回答集の準備など、十分な準備が成功の要因となります。
デジタル技術を活用した効率化
近年、展示会運営にデジタル技術を活用することは当たり前になっています。QRコードを使った名刺交換、タブレットを活用したアンケート収集、リアルタイムでの顧客情報の管理など、効率的な運営が可能になっています。
■展示会の効果測定と改善のためのKPI設定
展示会出展には本当に意味があるのかを判断するには、効果を客観的に評価する仕組みが必要です。最後に展示会を振り返る時にチェックするべき定量・定性両方の指標を解説します。
展示会の成果を検証する方法
展示会の意義を明らかにし、成果を最大化するには、複数のKPIを組み合わせて総合的に評価することが重要です。短期的な成果にとどまらず、中長期的なビジネス貢献まで視野に入れた分析を行い、出展の本質的な「意味」を把握しましょう。
| 指標名 | 説明 | 測定方法 |
|---|---|---|
| 名刺交換数 | 獲得したリードの総数 | 会期中の名刺交換件数を集計 |
| デモ実施数/接客数 | 接客した顧客数に対し、製品デモを実施できた割合 | 会期中の名刺交換件数及びデモ実施分の名刺数から集計 |
| 有効名刺数 | ターゲット層に該当する質の高いリード数 | 事前に設定した条件でフィルタリング |
| アポ獲得数 | 具体的な商談アポイントの獲得数 | 展示会後1か月以内の商談設定数 |
| 案件化数 | 商談から具体的な提案に進んだ数 | 営業フェーズの進捗管理 |
| ROI | 投資対効果の測定 | (売上-費用)÷費用×100 |
特に重要なのは、名刺獲得数の向上だけでなく、獲得したリードの質を向上させる施策の効果測定です。単なる数の多さに注目するだけでなく、どれだけターゲットに近いリードを獲得できたか、またそこからどれだけ商談に結びついたかといった質的側面も併せて追跡することで、展示会出展の成果がより明確になります。
投資対効果の正しい算出方法
展示会のROIを正しく測定することで、その出展がビジネスにどれほど寄与したか、すなわち出展の「意味」を数値で把握できます。単なる売上だけでなく、認知度向上や信頼醸成といった間接的効果も含めて評価する視点が求められます。
また、展示会にかかる費用は出展料だけでなく、ブース制作、人員配置、旅費なども含めた総コストで算出することが重要です。これにより、投資に見合う成果を正確に測定できるようになります。
来場者を分析する手法と次回への活用
展示会出展の意味をさらに深めるには、来場者リードの詳細な分析が欠かせません。業種、企業規模、役職、関心分野などをもとにターゲットとの整合性を確認することで、自社の製品・サービスがどれだけ訴求できたかを評価できます。
加えて、商談化率の高いリードの共通点を分析し、次回の出展ではより効率的に成果が出せるよう戦略を立て直すことが、展示会を「意味ある活動」とするための重要なステップとなります。
■まとめ
展示会への出展は、適切な戦略と準備があれば、新規顧客獲得、既存の顧客との関係強化、認知度向上において非常に効果的な手段となります。しかし、目的が不明確な出展や事前準備不足、フォローアップ体制の不備などにより、期待した効果を得られない企業も少なくありません。
成功の鍵は、明確な目的設定、戦略的な展示会選定、効果的なブースデザイン、スタッフ教育、そして最も重要な展示会後のフォローアップ体制の構築にあります。また、適切なKPI設定による効果測定と継続的な改善により、展示会への出展の投資対効果を最大化することが可能です。
もしこれから展示会への出展を検討する中で、「何から手をつければいいか分からない」「投資対効果を最大化する具体的な方法が知りたい」といったお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。博展は年間多数の出展を成功に導いてきた実績と、戦略立案から空間デザイン、製作、効果測定まで一貫して支援する総合力で、皆さまの課題解決に貢献します。