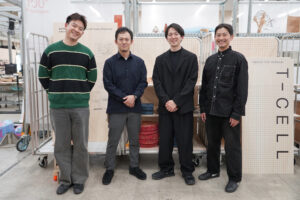2025年11月6日、東京ドームシティ アトラクションズに8年ぶりの全面リニューアルを果たした「暗闇婚礼 蠢(おごめ)一族お化け屋敷」がオープンした。昭和20年代後半の山奥の村「土神村」を舞台に、禁忌の秘儀が生み出す恐怖を全感覚没入型で体験できる本アトラクション。その制作を担当した博展のチームと、お化け屋敷プロデューサーの五味弘文氏、(株)東京ドーム(以下、東京ドーム)の担当者が一堂に会し、企画から完成までの道のりを振り返った。そこには、互いに「チャレンジ」を選んだ制作陣の、試行錯誤と創意工夫の日々があった。
Index
「全員でチャレンジする」という選択
手探りで始まった世界観の共有
「リアリティ」と「想像力」のバランス──バス演出の試行錯誤
お客様とお化け屋敷の「新しい関係性」
これからの展望
「全員でチャレンジする」という選択
──リニューアル後の手応えはいかがですか?
鈴木(東京ドーム アミューズメント部):手応えはありますね。やはりお化け屋敷というコンテンツ自体が、日本人にすごく愛されているコンテンツだなと感じています。ソフト的にもハード的にも同じ方向を向いてリニューアルできたので、それをしっかりとお客さんに届けられたことが、今の結果に結びついていると思います。
五味(お化け屋敷プロデューサー|オフィスバーン 代表取締役):今回は新しい試みをいろいろ取り入れているので、不安要素がなかったわけではありません。それが自分の中ではチャレンジだったのですが、そのチャレンジがちゃんといい形でお客様に受け入れられたという実感があるので、そこはすごく嬉しいです。「新しいタイプ」「新しい境地に入った」という言われ方をしたりもします。

浅井(博展 プランナー):施工が終わってからも何度も様子を見に来ているのですが、平日なのに40分待ちとか行列ができていて驚きました。SNSを通じて拡散しているという感じですね。
横川(博展 デザイナー):お客様の、特にカップルの会話が面白かったですね。男性が強がっていて、待ち時間のときには饒舌に話しているのに、出てくるときは無言で。そのギャップが面白かったです。でも最後は出口のところでみんな写真を撮っていく。自分が体験したものを残そうという動きがあって、それを見たときに「これは大事だな」って感じました。
熊崎(博展 プロダクトマネジメント):これまで僕の仕事を妻と子供が見たいと言うことは滅多になかったんですが、今回は「行きたい」と言ってくれて。この前の日曜日に行ったんです。でも、ポスターを見たら怖がってしまって、結局入らずじまいでした(笑)。息子は9歳です。それでもそう思ってくれたのは父親として嬉しかったですね。
五味:ワーッと言って飛び出してきて笑い転げるというようなお客様も多いですよ。お化け屋敷は、エンターテインメントなので、恐怖を乗り越えた先にある「楽しい」という境地に行ってほしいと思っています。安心できる日常世界に戻れた、すっきりしたという爽快感みたいなものが、お化け屋敷の本質的な部分だと思いますから。
──今回、リニューアルにあたってのコンペで、東京ドームさんと、五味さんは、博展という新しいパートナーを選ばれました。その理由を教えてください。
五味:自分の中では今回チャレンジをしたいという気持ちが強くあったんです。選択肢は二つありました。一つは、自分ひとりがチャレンジするから、安心感のあるスタッフに自分のわがままを聞いてもらうという考え方。もう一つは、新しいスタッフと一緒にチャレンジをしていこうという考え方です。
博展の提案を聞いて、博展となら共に新しいことができそうだと考え、最終的には思い切って、自分もスタッフも全部含めてチャレンジの方に向かうという判断をしました。
浅井:私たちとしても、お化け屋敷を作ったことがなかったので、そこの実績は謳えません。ですので、提案のときはできる領域の広さを見せようと考えました。企画、デザイン、映像、造作、音響などの体験周りのほか、コピーやグラフィックなどの販促周りまで、一貫して対応できることをアピールしました。
鈴木:まさに全員チャレンジだったなと。お化け屋敷というコンテンツの難しさを、博展さんもすごく感じた10ヶ月だったと思います。

手探りで始まった世界観の共有
──博展チームにとって、五味さんとの世界観の共有は大きな課題だったのではないでしょうか。
浅井:最初は、どうしていいか分からないことが結構ありました。五味さんと一回ちゃんとこの作品についてすり合わせた時間があって、2時間くらい話したかな。そこでだいぶ解像度が上がりました。何を大切にして、今までの作品と今回の『暗闇婚礼』ではどう違っていて、どういうテーマなのか。そこで初めて共通認識が取れてきました。
横川:五味さんの頭の中にしっかりとした世界観があるのですが、私たちはその一部分、つまり点でしか考えられていないところがたくさんありました。話をお伺いしながら、点でしか理解していなかった蠢一族のストーリーを線で理解することで、だんだんと期待に応えられるようになっていった感覚があります。そうした意味で、五味さんのお化け屋敷演出すべてを学ばせていただいたのは、すごい経験でした。
──転換点となった瞬間はありましたか?
熊崎:バスの演出に関してミーティングした日があって、最初はプロジェクターで映像を見せようという方向で進めていたんです。でも、そこで博展チームが「こういう振動があって、こういう照明で演出したらうまくいくんじゃないか」という提案ができたときに、初めて同じ土俵に立ったんだなという気がしました。
浅井:社内にDIチームがいることで、すぐに試作して提案できたのもよい流れだったと思います。
五味:お互いに手探りで進めていく中で、どこかのタイミングで手を結べる瞬間があるんですよ。それを積み重ねることで、「こういうふうに進めればいいのか」というようなことがだんだん見えてきました。
実際、現場で物を作り始めると、お互いに言葉では必ずしも伝えられない思いや感覚がけっこうあるものです。特に僕の場合、頭の中だけじゃなくて現場で考えることが多くて、他の人に比べて圧倒的に現場に行く回数が多いんですよ。お化け屋敷ってライブ感というか、生の現場ですから。その共同作業を「楽しい」と思えるかどうかが、チームでの制作にはすごく大事なことなんです。
「リアリティ」と「想像力」のバランス──バス演出の試行錯誤
──今回のお化け屋敷で特に印象的なのが、入口のバスの演出です。どのような狙いがあったのでしょうか?
五味:以前のお化け屋敷では、何もない真っ暗な空間でストーリーを聞いて、世界が構築されていきます。でも今回は、ポンといきなり冒頭からその世界に放り込んでしまおうと思っていて、そこが一つ今までと違うところです。
そのためにはいかにしてその世界に入ったと感じさせるかがものすごく大事で、リアリティが求められるだろうなと思いました。実際にバスに乗って行くのだったらいいのですが、そうじゃないわけですから、その足りない部分をいかに想像力で補わせるか。そこにあるリアルなものから想像力を働かせることによって、そのあとに出てくるおばけが本物らしくなる。そのために、どうリアリティを作るか、ということが大きな課題でした。
横川:今回の時代設定は、昭和20年代後半なんです。でも、昭和20年代のバスってまず現代に存在しなくて、古い資料から当時のバスの内装を調べました。壁が板張りになっているとか、曲線の角の窓など、特徴的な要素を入れることで当時のバスらしさを演出しました。
熊崎:来場者が最初にその世界観に入っていく場所なので、よりリアリティを出すために椅子は本物でなければならないと思いました。そこで、実際に路線で走っていた古いバスの椅子を購入しました。
五味:本物の椅子を手配できたのはすごくよかったです。そこが足がかりになって、次に窓や、ドア、つり革と、具体的な物質的な空間が生まれていきました。あとは、そこに照明、映像、振動などで、バスの中にいるような表現を加えていきました。

──そこでは、どのような試行錯誤がありましたか?
五味:先ほども話に出ましたが、最初は導入部分を映像でやろうと思って、車窓に映る具体的な景色を映し出してみたりもしました。でもなにか違うと思い、徐々に照明を使った、抽象的な方法に移行していきました。そこはかなり試行錯誤がありましたね。
浅井:その映像を最初に見た時、映画みたいだったんです。「バスで向かう」という主観的な体験になってない。ここはバスでどこかに向かっていくんだって、誰もが思いつつ、あまり客観的にならないようにするためには、リアルな映像ではなく、光と影の演出がいいんじゃないかなと。実際に試してみたら、すごく良かったので採用したという流れです。
五味:僕はもともとお化け屋敷で映像を使うのは難しいなと思っていたんです。でも、チャレンジしたいって気持ちは常にあって。でも結局、人は2次元の映像を見ている時と、リアルな3次元の世界にいる時では、脳の働きが違うんですね。博展さんと実物を作って検証したうえでやはりこっちがいいと、ベストな方法を見つけることが出来たと思います。
お客様とお化け屋敷の「新しい関係性」
──今回のリニューアルで最も意識したことは何でしょうか?
五味:「お客様とお化け屋敷の関係性」を変えることでした。今まで作ってきたお化け屋敷は、あらかじめ“時間軸でこういうことが起こりました、その後にお客様が入って体験します”、という関係性でした。この考え方を変え、ストーリーのあり方をよりお客様の主観に近づけ、自分が入ったことによってストーリーが動き出す、というような作り方をしたかったんです。「お客様がこういうことしちゃったから、この物語が動き出した」という因果関係ですよね。自分のせいでこうなったっていう、より強い関係性を作りたいと思いました。
浅井:恐怖をエンターテインメントにすることですね。怖いけれども楽しいという絶妙なバランス。どこまでできたか分かりませんが、少しでも五味さんのイメージに近づけられていれば、嬉しいですね。
横川:意識したというか感じたことなんですが、とにかく五味さんすごいなって。30年以上お化け屋敷を作ってらっしゃるのに、細部にまでこだわって、チーム全体を一つの方向に向かわせる。オープンまでしっかり見届ける。精神的にも肉体的にもとてもアグレッシブで、頭が下がる思いでした。
熊崎:体験者と距離がものすごく近くて、ここまでリアルに反応が返ってきて、体験者のリアクションを考えなきゃいけない物作りっていうのはあんまりしたことがなかったので、そこをどう自分の中で吸収していくかを意識しましたね。まさに、内装と演出が融合した作品。みんなが蓋を開けるシーンがあるんですけど、どういうリアクションをするだろうと思って監視カメラで見ていたら、ちゃんと、こわごわとやってくれるんですよね。「あ、そういうリアクションするんだ!」って(笑)。とにかく勉強になりました。

これからの展望
──今後の展望についてお聞かせください。
鈴木:お化け屋敷という常設イベントは、波を作っていく必要があると思っています。今回一旦ベースの作品を作ったので、プラスアルファでどんな要素を付加してお客様に楽しんでいただける空間を作れるかを通年で考えていきます。特に夏に向けてどうしていくのか。終わったというよりは始まったという印象です。これからも集客しつづけられるコンテンツに育てていかなくてはならない、という使命があります。
──最後に、五味さんからまだ体験されていないお客様へメッセージをお願いします。
五味:今回は今までとは違う形で次の段階に移ったと感じています。今まで来て楽しんでくださったお客様はもちろん、お化け屋敷とは距離があったお客様も、これを機にお越しください。怖いんだけども、出てきたときにすごい爽快感を持った楽しさを感じられる、素晴らしいエンターテインメントを味わっていただけたら嬉しいです。

未経験のチームが、ベテランプロデューサーと共に挑んだ「全員でのチャレンジ」。その試行錯誤の先に生まれた「暗闇婚礼 蠢一族お化け屋敷」は、お化け屋敷という日本の伝統的エンターテインメントの新たな可能性を切り開いたと言えるだろう。

(取材・文 いからしひろき)
OVERVIEW
| CLIENT | 株式会社東京ドーム |
|---|---|
| PROJECT | 暗闇婚礼 蠢一族お化け屋敷 |
| VENUE | 東京ドームシティ アトラクションズ ラクーアゾーン1F |
|
2025年11月6日、東京ドームシティ アトラクションズに8年ぶりの全面リニューアルを果たした「暗闇婚礼 蠢(おごめ)一族お化け屋敷」がオープンした。昭和20年代後半の山奥の村「土神村」を舞台に、禁忌の秘儀が生み出す恐怖を全感覚没入型で体験できる本アトラクション。その制作を担当した博展のチームと、お化け屋敷プロデューサーの五味弘文氏、(株)東京ドーム(以下、東京ドーム)の担当者が一堂に会し、企画から完成までの道のりを振り返った。そこには、互いに「チャレンジ」を選んだ制作陣の、試行錯誤と創意工夫の日々があった。 |
|
| WEB | https://www.at-raku.com/attractions/laqua/obakeyashiki/ |