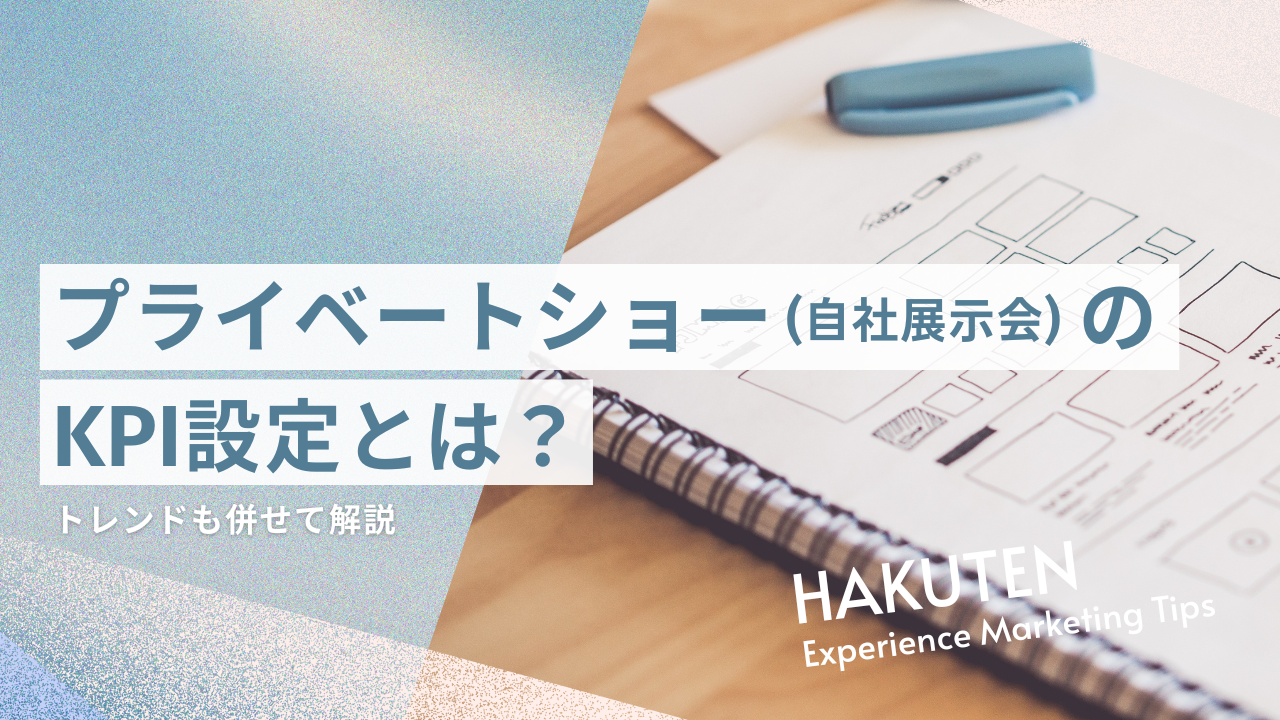「多くの来場者で賑わい、盛況のうちに終わったはずのイベント。しかし、いざ上司に『で、成果はどうだった?』と聞かれると、具体的な数字で答えられず、言葉に詰まってしまった……」
多くのイベント担当者が、このような「成果の“見えなさ”」という課題に直面しています。
「イベントをやって終わり」では、かけたコストや労力が本当に報われたのか分からず、次につながる貴重な学びの機会も失いかねません。
そこで本記事では、イベントの効果測定について、その重要性から具体的な指標設定、そして次回の成功につなげる改善アクションまで、体系的に解説します。
Index
■イベントの効果測定がもたらす3つのメリット
■【大前提】イベントの効果測定の精度を高める2つの基本原則
■イベント効果測定の進め方3ステップ
■イベント効果測定におけるSMART原則
■SMART原則を用いたイベントの目的別KPIの具体例
■効果測定を次回のイベント成功につなげるコツ
■まとめ
■イベントの効果測定がもたらす3つのメリット
イベントの担当者なら誰もが一度は直面する「このイベント、本当に投資に見合った価値があったんだろうか?」という問い。この問いに具体的な数字で答えられないままでは、かけたコストや労力が正当に評価されず、次につながる貴重な学びの機会も失いかねません。
イベントの効果測定は、単なる報告書づくりのための作業ではなく、イベントを単発の施策で終わらせず、組織全体のマーケティング力を底上げする強力なエンジンに変えるための、きわめて重要なプロセスです。
ここでは、その主な目的とメリットを3つのポイントに整理して解説します。
「誰に響いたのか?」がわかり、顧客理解が深まる
アンケートデータなどを分析すれば、どんな属性の参加者が、どのコンテンツに強く反応したのかが手に取るようにわかります。ターゲット顧客の解像度が上がることで、イベントだけでなく、日々のマーケティング活動全体の精度向上にもつながります。
勘や経験だけに頼らない、「勝てる戦略」を描けるようになる
過去のデータは、未来の成功確率を高めるための貴重な資産です。成功パターンを再現し、失敗要因を避けることで、企画の精度は飛躍的に向上します。データという根拠があるからこそ、自信を持って次のアクションを決定できます。
「このイベントには価値がある」と、数字で証明できる
イベントの成果を具体的な数値で示せれば、社内での協力や理解も得やすくなります。特に、商談化数や受注額といった売上に直結するデータは、経営層の納得感を引き出し、継続的な投資を得るための力強い後押しとなるでしょう。
■【大前提】イベントの効果測定の精度を高める2つの基本原則
イベントの効果測定を「やりっぱなし」にせず、意味のあるものにするためには、測定を始める前に押さえるべき2つの基本原則があります。それは「ゴールから逆算して指標を設定すること」と「定量指標×定性指標の両輪で評価すること」です。この土台を固めることで、測定の精度と納得感が格段に上がります。
KGIから逆算してKPIを設定する
イベントの効果測定で最も重要なのが、イベント全体のゴール(KGI)から逆算して、中間指標であるKPIを設定するという考え方です。
例えば、KGIが「新規商談の獲得」なら、KPIは「商談につながるアンケート回答の獲得数」や「特定の製品デモへの参加者数」などが考えられます。最初にKGIを明確に定めることで、KPIがブレず、イベントのすべての施策がゴール達成に一貫します。
定量指標×定性指標の両輪で評価する
イベントの価値を正しく捉えるには、来場者数やアンケートスコアといった定量指標だけでなく、SNSの反響や自由記述コメント、現場で得た声といった定性指標も組み合わせて評価します。
「来場者数は未達でも、満足度や推奨度が非常に高く熱量の高いファンが生まれた」など、定量だけでは見えない成功を取り逃がさないための視点です。
■イベント効果測定の進め方3ステップ
「理屈はわかったけど、具体的にどう動けばいいの?」という方のために、ここでは効果測定の具体的な3ステップを解説します。
ステップ1:データの収集方法の決定&「量」を測る
効果測定の成否は、イベントの「前」に、ほぼ決まるといっても過言ではありません。どのデータを、どうやって集めるのか。この収集方法を事前に設計し、当日の運営オペレーションに組み込んでおくことが成功の第一歩です。
まず、会場での「リアルな熱量」を捉えるために、受付での来場者数やブース訪問者数を正確にカウントする仕組みを用意します。例えば、QRコード受付などを導入すれば、誰が・いつ来たかといった行動履歴までデータ化できます。
また、獲得した名刺はスキャナーアプリなどで即座にデータ化し、フォローアップのスピードを上げるのも効果的です。加えて、オンライン上の「見えない反響」を拾うためには、Google Analyticsでのサイト流入計測や、SNSモニタリングツールでの言及数をチェックするのも有効ですね。
ステップ2:アンケートを実施して「質」を測る
来場者数という「量」のデータだけでは、参加者がイベントをどう感じたかという「質」の部分が見えてきません。そこで不可欠なのが、参加者の満足度やブランドへの印象といった、目に見えない価値を可視化するアンケートです。
満足度スコア(5段階評価など)や、他者への推奨度を測るNPS(ネットプロモータースコア)といった定量データで、イベントの成功度を客観的な数値として把握します。
さらに、「最も印象に残ったコンテンツは?」「改善してほしい点は?」といった自由記述の質問を用意することで、数値だけでは見えない参加者の“生の声”を集めましょう。そこには、次回の成功につながる貴重なヒントが隠されているはずです。
- 満足度スコア:
イベント全体への満足度を5段階などで評価してもらう、最も基本的な指標。 - NPS(ネットプロモータースコア):
「このイベントを友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」を0〜10点で評価してもらい、参加者のロイヤルティ(愛着度・推奨度)を測る指標。 - 各コンテンツへの評価:
「最も役に立ったセッションはどれですか?」など、個別のプログラムに対する評価を集めることで、人気のコンテンツや改善点を具体的に把握できる。 - 自由記述コメント:
「イベントの感想」や「改善点」を自由に書いてもらうことで、数値だけでは分からない具体的な改善のヒントや、思わぬ称賛の声を発見できる。
ただし、参加者の貴重な時間を奪わないよう、質問は厳選し、「これだけは絶対に聞きたい」という項目に絞り込むのが成功のコツです。
ステップ3:投資対効果(ROI)を算出する
「で、結局このイベントは儲かったの?」という問いに明確に答えるための最終指標が、投資対効果(ROI)です。
ROIは「(イベントによる利益 – イベント投資額) ÷ イベント投資額 × 100」という計算式で算出でき、イベントが事業の収益にどれだけ貢献したかを客観的な数値で示せます。
ここで重要なのは、「利益」と「投資額」を正しく捉えることです。
「利益」には、会場での直接的な売上だけでなく、イベント後の営業活動から生まれた間接的な売上も含まれます。BtoBの場合は特に、長期的な追跡が不可欠です。この長期的な追跡とは、イベントで接点を持った顧客との関係性を、時間をかけて育てていくプロセスを指します。
例えば、獲得した見込み客に対し、リードナーチャリングとしてメールやDMで継続的に情報を提供し、徐々に信頼関係を構築しながら購買意欲を高めていくことで売上に繋がったケースなども計算に含めるのが適切です。それと同時に、個別相談会や次回の業界セミナーの案内といった継続的な営業タッチポイントを設けることで、顧客の検討フェーズに合わせたアプローチを続けます。
さらに、その関係性は契約後も続きます。受注後のフォローアップとして定期的な満足度調査などを通じて顧客との関係を維持・強化すれば、アップセルやクロスセルといった新たなビジネスチャンスに繋げることも可能です。
このように、イベント直後だけでなく、その後の地道な活動から生まれた売上までを「利益」として正しく計測することで、イベント投資の真の効果を評価できるようになるのです。
また、「投資額」には、会場費や設営費はもちろん、スタッフの稼働時間といった見えにくい人件費も忘れずに含めましょう。
算出されたROIを他のマーケティング施策と比較することで、イベントという投資の有効性を客観的に判断し、次回の予算獲得に向けた強力な根拠とすることができます。
■イベント効果測定におけるSMART原則
KPIを「絵に描いた餅」で終わらせないための強力なフレームワークが「SMART原則」です。これは、指標が以下の5つの要素を満たしているかを確認するものです。
- Specific:具体的か
- Measurable:測定可能か
- Achievable:達成可能か
- Relevant:KGIと関連しているか
- Time-bound:期限が明確か
例えば単に「来場者の満足度を上げる」では曖昧ですが、「イベント終了後24時間以内に(T)配信するアンケートで、満足度スコア5段階中4以上を80%(S/M)獲得する。目標はKGI(顧客ロイヤルティ向上)と関連(R)し、昨年比+10ptで現実的(A)。」とすれば、SMARTを満たした具体的なKPIになります。
■SMART原則を用いたイベントの目的別KPIの具体例
ここでは、イベントの目的ごとにSMART原則を満たしたKPIの例を紹介します。
認知度向上・ブランディング目的のKPI
「まずは、より多くの人に自社のことを知ってもらいたい」
「ブランドのファンになってもらうきっかけを作りたい」
このような、認知度向上やブランディングを目的とするイベントでは、「どれだけ広く、深く、ポジティブな印象を残せたか」を測る指標が中心となります。
まず基本となるのが、イベントの規模や熱量を測る来場者数です。さらに、その内訳である新規来場者率を見ることで、新しい層にアプローチできたかどうかを評価できます。
また、イベントの効果は会場内だけにとどまりません。イベント期間前後のウェブサイト流入数の変化や、SNSでのインプレッション、いいね、シェア数といったSNS反応を追うことで、オンラインでどれだけの波及効果や話題性を生み出せたかを可視化できます。
| 指標カテゴリ | 主要指標 | 測定のポイント |
|---|---|---|
| 基本指標 | 来場者数、新規来場者率 | 過去データとの比較、競合他社との比較 |
| デジタル指標 | ウェブサイト流入数、SNS反応 | 期間別変化、エンゲージメント率 |
| メディア指標 | メディア掲載数、記事の質 | 掲載媒体の影響力、記事の好意的評価 |
| ブランド指標 | ブランド認知度、好感度 | イベント前後のアンケート調査 |
このように、会場内の熱気(基本指標)と、オンラインやメディアでの波及効果(デジタル・メディア指標)、そしてブランドイメージの変化(ブランド指標)を総合的に評価することが、ブランディングイベントの成功を測る鍵となります。
リード獲得目的のKPI
リード獲得目的のイベントで重要になるのが、「量」と「質」の両面から成果を評価する視点です。
SMART原則を意識した設定例としては、例えば「イベント終了後24時間以内にアンケート回収率70%以上を達成する」といったものがあります。
まず「量」を測る指標として、名刺獲得数やアンケート回収率が挙げられます。これは、どれだけの見込み顧客と接点を持てたかを示す基本的な数字です。
しかし、本当に重要なのはその「質」です。獲得したリードの中から、自社のターゲットに合致する有効リード数やターゲット条件適合率を算出しましょう。
さらに、ブースでの資料配布数やWebでのホワイトペーパーダウンロード数なども、見込み顧客の具体的な関心度を測るための重要な手がかりとなります。
商談創出・売上向上目的のKPI
商談や売上への貢献を最終ゴールに置く場合、イベントから営業活動、そして受注までを一連の流れとして捉えた指標設定が不可欠です。
SMART原則を意識した設定例としては、例えば「イベント後1か月以内に商談化率30%以上を達成する」といった具体的な数値目標があります。
まず、イベント当日の成果として会場での商談数やその場での受注数があります。これはイベントの熱量が最も高いうちに得られた、直接的な成果です。
しかし、BtoBではここからが本番。イベント後にどれだけの「アポイントが獲得できたか(アポイント獲得数)」、そしてそれが「実際の商談に発展したか(商談化率)」を追跡することが極めて重要です。
そして最終的には、受注件数や受注金額といった、売上への直接的なインパクトを測定します。BtoBでは成約まで時間がかかるケースも多いため、短期的な成果だけでなく、中長期的な貢献度までをしっかりと見届ける視点が求められます。
■効果測定を次回のイベント成功につなげるコツ
さて、イベントの効果測定を終え、手元にはたくさんのデータが集まりました。しかし、このレポートをただ眺めているだけでは、次回の成功にはつながりません。
「やりっぱなし」を防ぎ、イベントを継続的に成長させる資産へと変えていくためには、データから得られた学びを具体的な「次の一手」に反映させることが不可欠です。
ここからは、集めたデータを次回の成功に変えるための、具体的な改善アクションプランについて解説します。
KPTで「良かった点・課題・次の打ち手」を整理する
データが手元にあっても、「さて、どこから手をつけるべきか…」と途方に暮れてしまうことは少なくありません。そんなとき、チームでの振り返りをスムーズに進めるためにおすすめなのが、「KPT(ケプト)」というフレームワークです。
これは、振り返りを以下の3つの観点で整理するシンプルな手法です。
- Keep(良かったこと・続けるべきこと):イベントの成功要因を分析し、次回も継続すべき強みを特定する。
- Problem(課題・改善すべきこと):目標未達の原因や参加者からの不満など、改善すべき課題やボトルネックを特定する。
- Try(次に取り組むこと):特定した課題(Problem)に対して、具体的な解決策と次回のイベントに向けたアクションプランを策定する。
この3つの視点で振り返りを行うことで、次に繋がる具体的な学びを得ることができます。
まず「Keep」では、目標を達成した指標や、アンケートで特に評価が高かったコンテンツなどを挙げ、「なぜうまくいったのか?」という成功の要因を深掘りします。この“成功のレシピ”は、次回のイベントでも再現すべきチームの強みとなります。
次に「Problem」では、目標未達だった指標や参加者からの不満の声に真摯に向き合い、「どこにボトルネックがあったのか?」を特定します。集客プロセスの問題や当日の運営トラブルなど、目をそらさずに事実を洗い出すことが重要です。
そして最後に、洗い出した「Problem」を基に、「では、次はどうする?」という具体的な解決策を「Try」として考えます。これが、次回のイベントに向けた明確なアクションプランの土台となるのです。
データを分析し、集客の「勝ちパターン」を見つける
どの集客チャネルが、最も効率的に『来てほしいお客様』を連れてきてくれたのかを把握するため、各チャネルの費用対効果を徹底的に分析し、次回の予算配分を最適化します。
例えば、Web広告やSNS、メルマガといったデジタル施策については、Google Analyticsなどを活用して、どのチャネル経由の申込率が高かったのか、一件あたりの獲得コストはいくらだったのかを比較検証します。同様に、DMやパートナー経由といった従来型の施策も、成果を数値で評価しましょう。
また、「どんな言葉やデザインが響いたのか」というメッセージの分析も重要です。クリック率や申込率が高かった広告のキャッチコピーやクリエイティブを分析し、自社の集客における「勝ちパターン」を導き出します。
アンケートの“生の声”を、コンテンツと運営に活かす
参加者アンケートは、改善のヒントが詰まった宝の山です。数値データと自由記述の“生の声”を組み合わせることで、次回の満足度を飛躍的に高めることができます。
まず、コンテンツの改善です。「どのセッションが一番人気だったか?」を満足度データから特定し、その理由(登壇者、テーマ、形式など)を深掘りします。成功要因を分析し、次回のプログラム構成に活かしましょう。
次に、運営オペレーションの改善です。「受付で待たされた」「会場のWi-Fiが遅い」といった不満の声はなかったでしょうか。こうした参加者の小さなストレスを一つずつ解消していくことが、イベント全体の体験価値向上に直結します。
最後に、フォローアップの改善も忘れてはなりません。イベント後のメール開封率や商談化率を分析し、アプローチのタイミングや内容が適切だったかを検証します。リードを次のステップへ引き上げるための、より効果的なコミュニケーションを設計しましょう。
・セッション改善:満足度上位の登壇者・テーマの分析、プレゼン形式の最適化
・運営改善:受付効率化、動線設計、スタッフ配置の見直し
・フォローアップ改善:アプローチタイミング、コンテンツ、頻度の最適化
・技術改善:音響・映像設備、WiFi環境、配信システムの強化
■まとめ
本記事では、イベントの効果測定について、その重要性から具体的なKPI設定、実践的な測定方法、そして改善アクションまでを解説してきました。
イベントの効果測定は、単なる報告書作りのための作業ではなく、イベントを「やりっぱなし」にせず、次につながる“勝てる施策”へと育てていくための、きわめて重要なプロセスです。
はじめは、来場者数のカウントや簡単な満足度アンケートからで構いません。大切なのは、まず「測ってみる」という文化をチームに根付かせ、データを見ながら次の一手を考える習慣をつけることです。
とはいえ、「自社だけで戦略的な効果測定の仕組みを構築するのは難しい」「もっとイベントの成果を最大化したい」と感じることもあるかもしれません。
私たち博展は、長年の経験と実績に基づき、イベントの企画から制作、そして成果を可視化する効果測定までをワンストップで支援しています。データに基づいたイベント戦略にご興味のある方、次のイベントを絶対に成功させたいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。